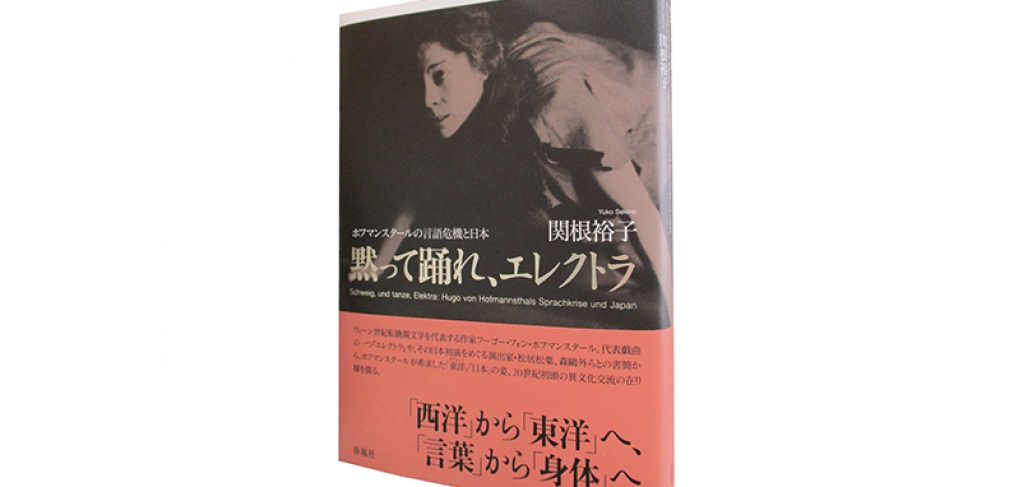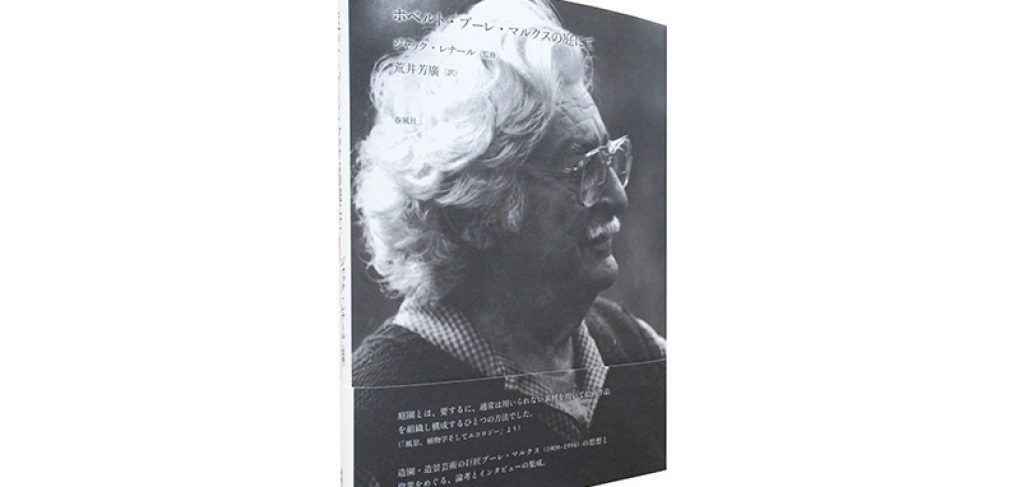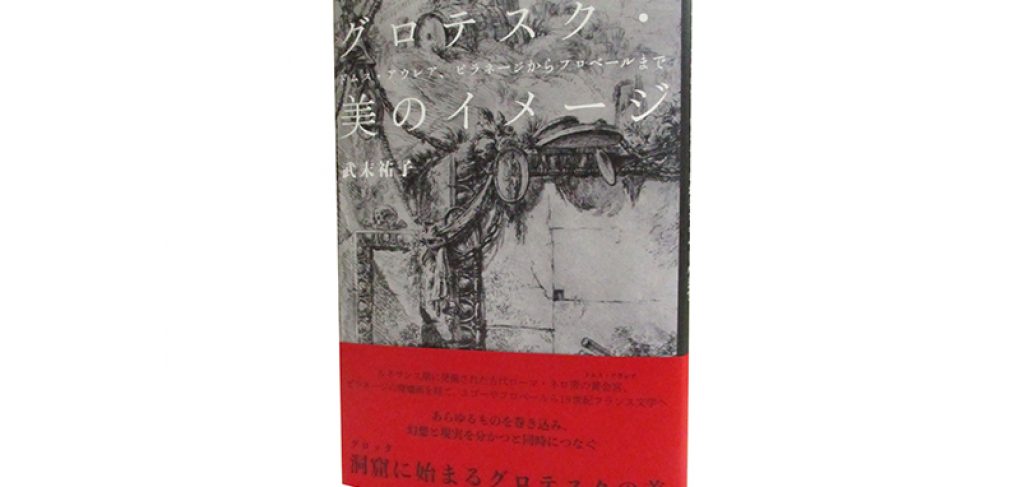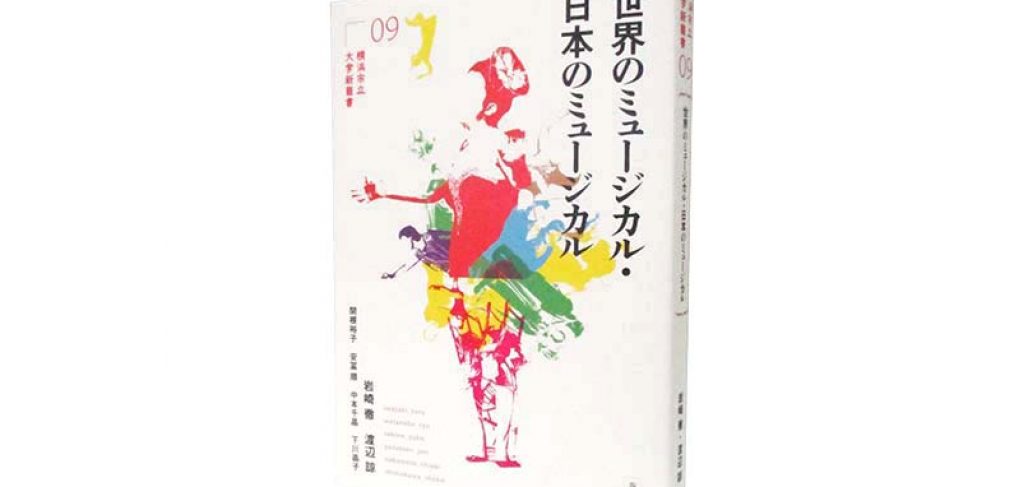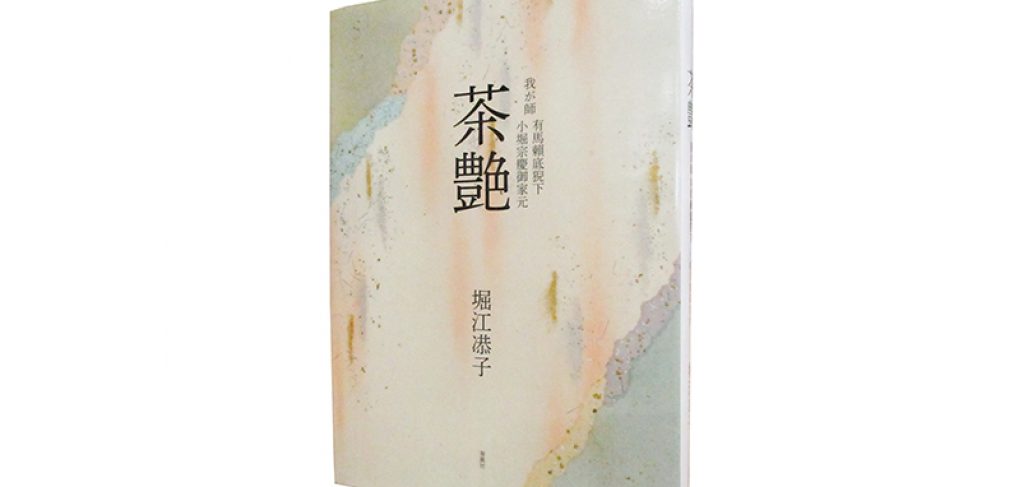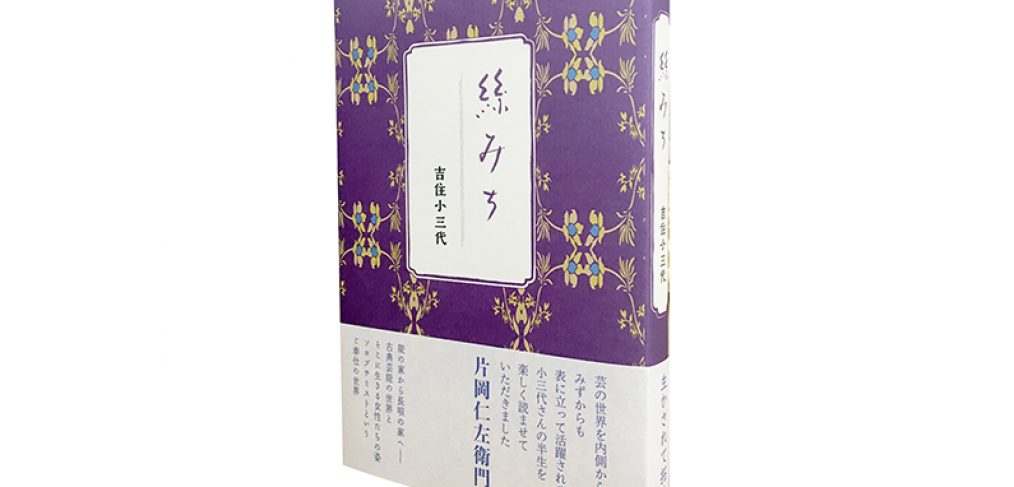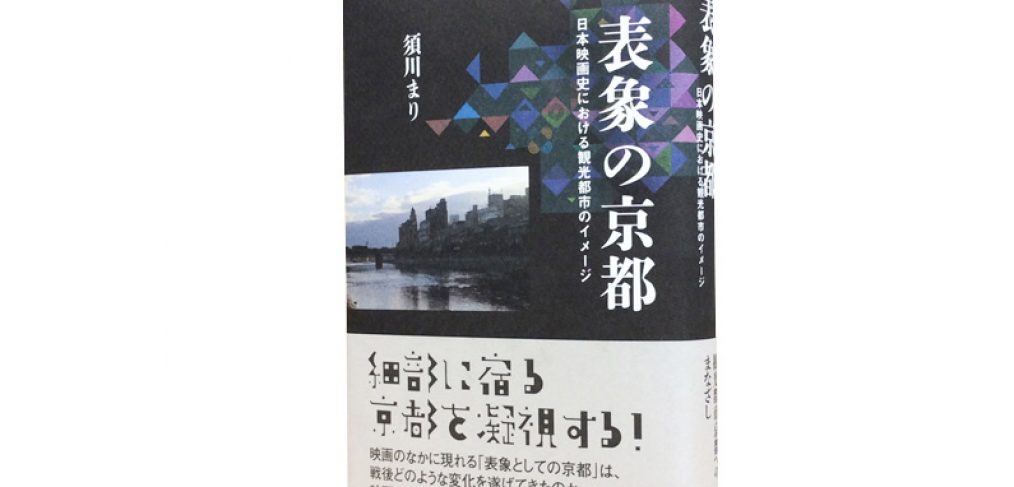黙って踊れ、エレクトラ
ホフマンスタールの言語危機と日本
- 関根裕子(著)/2019年3月
- 4200円(本体)/A5判上製396頁
- 装丁:間村俊一
「西洋」から「東洋」へ、「言葉」から「身体」へ
ウィーン世紀転換期文学を代表する作家フーゴー・フォン・ホフマンスタール。代表戯曲の一つ『エレクトラ』や、その日本初演をめぐる演出家・松居松葉、森鷗外らとの書簡から、ホフマンスタールが希求した「オリエント」「日本」の姿、20世紀初頭の異文化交流の在り様を探る。
(ISBN 9784861106378)
目次|contents
序論 二通の書簡―「西洋」と「東洋」の交差
第Ⅰ章 ホフマンスタールの「オリエント」像
第1節 言語危機と「オリエント」
第2節 ドイツ語圏のオリエンタリズムとホフマンスタール
第Ⅱ章 ギリシア関連作品に表われたオリエント性
第1節 『エレクトラ』
第2節 『恐れ/対話』
第3節 『ギリシア』
第Ⅲ章 ホフマンスタールの日本像とその変遷
第1節 ジャポニスム以前の日本に関する関心
第2節 「若きウィーン派」とジャポニスム
第3節 ホフマンスタールとハーン
第4節 『心』のホフマンスタール作品への影響
第5節 人間存在の超個人性
第6節 『エレクトラ』のなかの「プレエクシステンツ」と「エクシステンツ」
第Ⅳ章 非西欧的身体表現
第1節 「未知なる言語」を求めて
第2節 貞奴の印象
第3節 モダン・バレエの先駆者たちからの影響
第4節 『エレクトラ』の踊り
第Ⅴ章 松居松葉による『エレクトラ』日本初演
第1節 明治・大正期のホフマンスタール受容
第2節 松居の『エレクトラ』公演
第3節 『エレクトラ』の反響
結論 憧れと錯覚の文化交流―新たな自己創造のために
あとがき
参考文献
索引
著者|author
関根裕子(せきね・ゆうこ)
国立音楽大学卒業後、高校の音楽教員を経て、埼玉大学で独文学を専攻、筑波大学大学院博士課程満期単位取得退学。ウィーン大学留学。博士(文学)。専門は、ホフマンスタールを中心としたウィーン世紀転換期文学と文化、音楽文化史。
現在、早稲田大学、明治大学、学習院大学、日本女子大学、武蔵大学、上智大学等で非常勤講師を務める傍ら、合唱指揮者としても活躍。
主な著書に、『世界のミュージカル・日本のミュージカル』(共著・横浜市大新叢書、春風社)、『ようこそ、ウィーンへ!』(白水社)、訳書に、『僕は奇跡なんかじゃなかった―ヘルベルト・フォン・カラヤン - その伝説と実像』(音楽之友社)、共訳書に『ブラームス回想録集』(全3巻 音楽之友社)などがある。