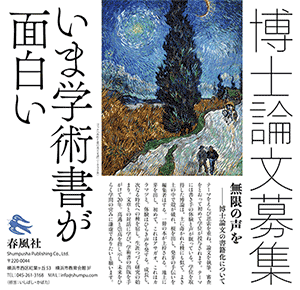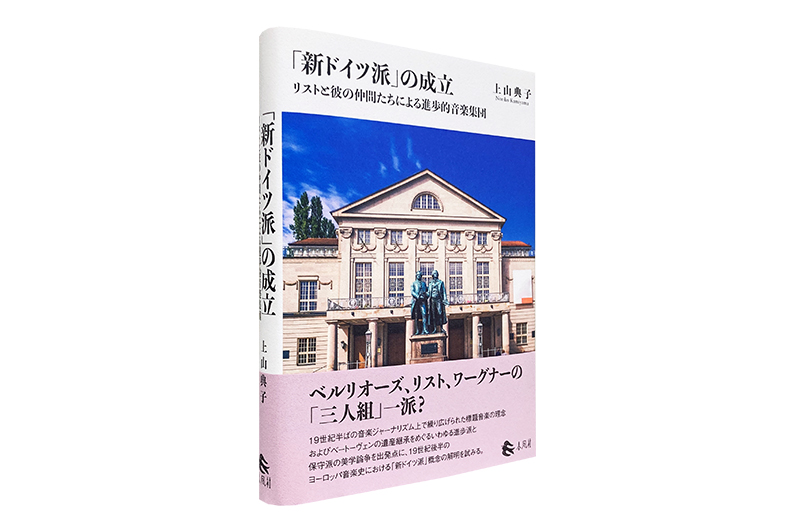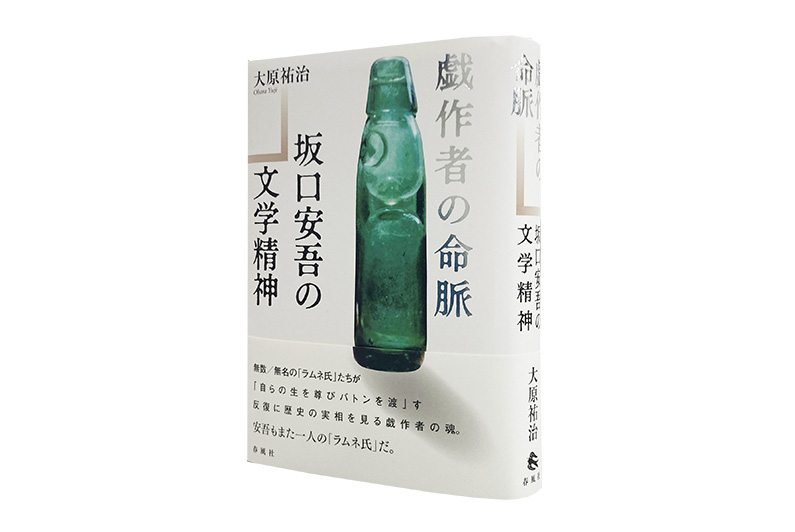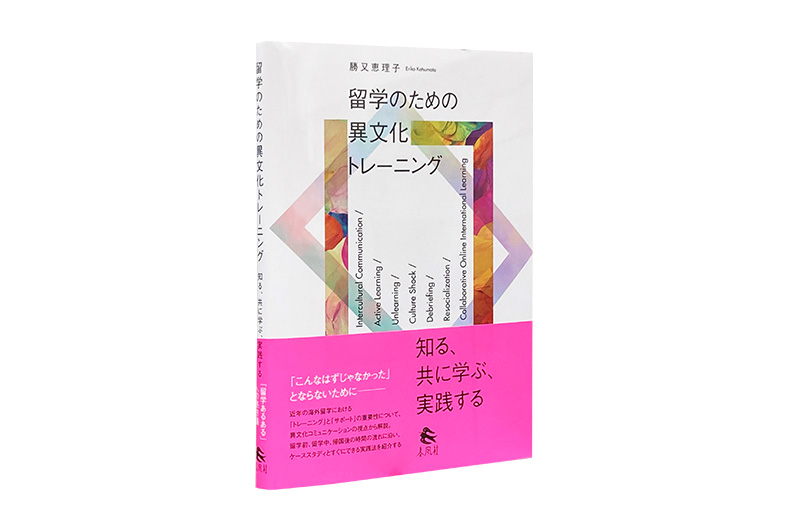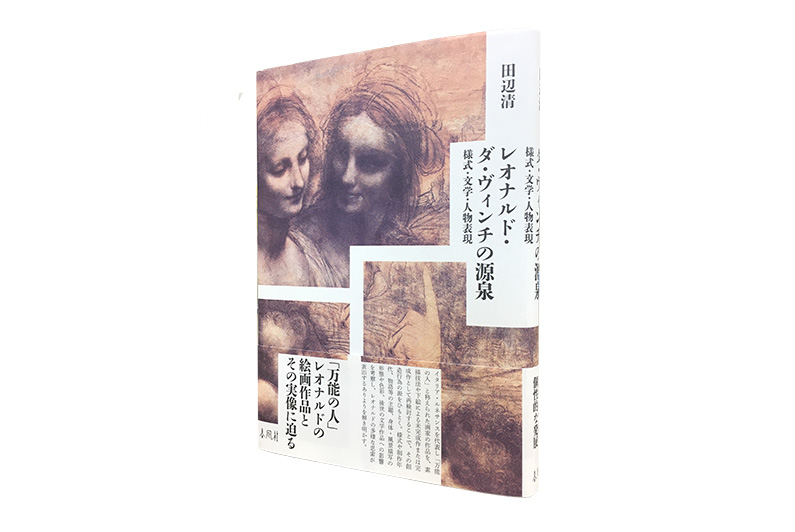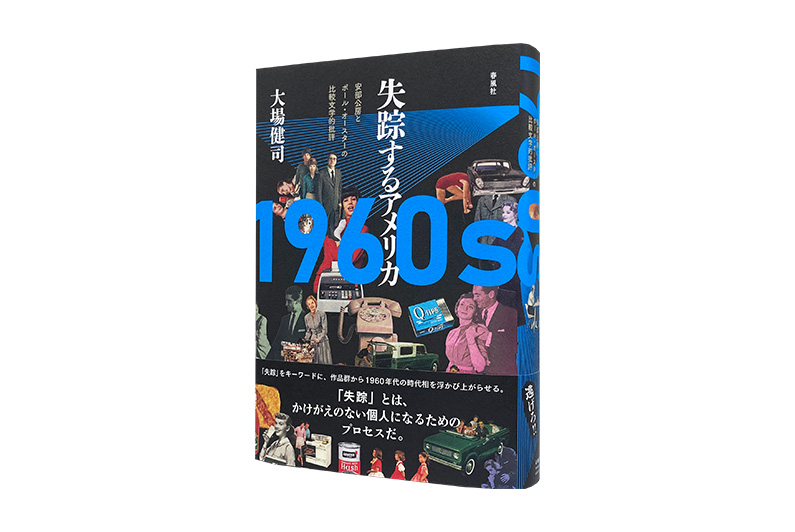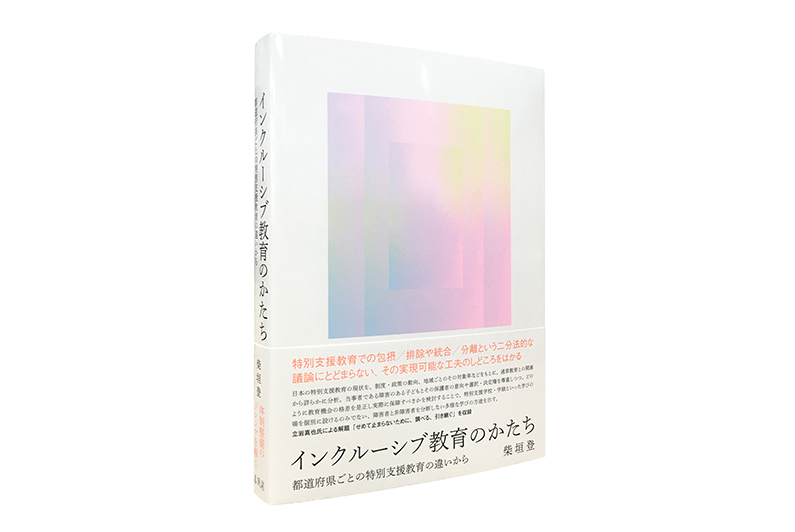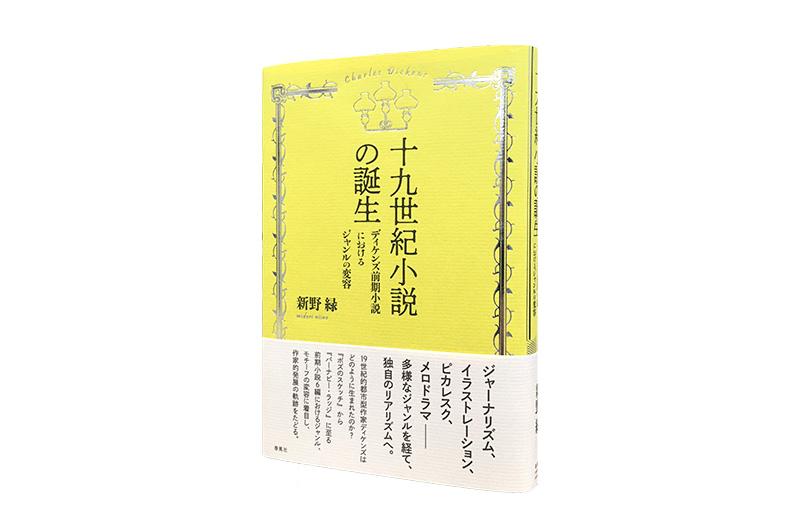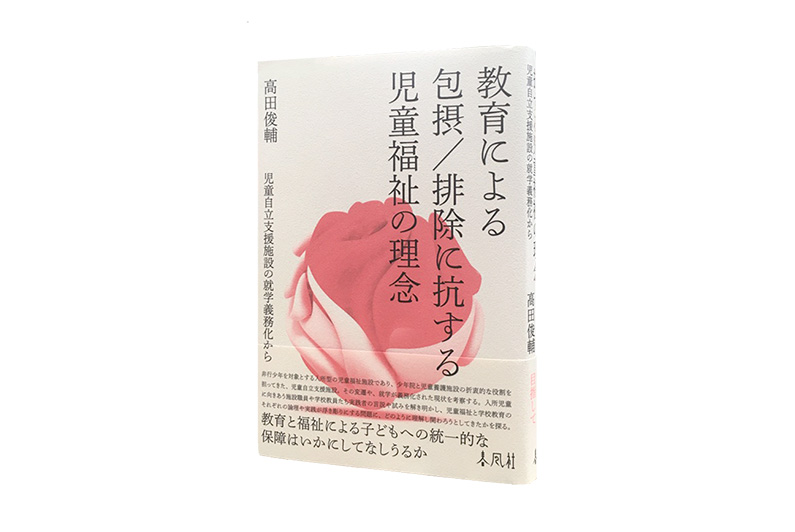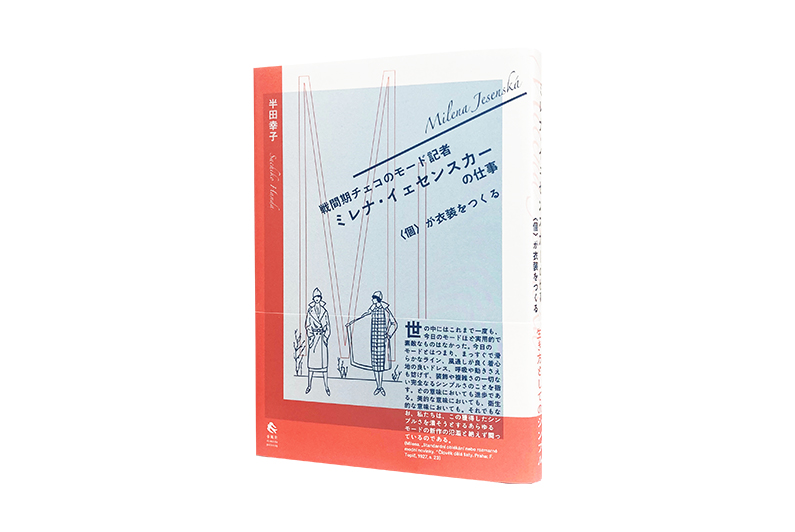無限の声を――博士論文の書籍化について
テーマをえらび思索を重ね、論文を執筆、審査をとおって初めて学位が授与されます。テーマには書き手の体験と声が眠っている。学位を取得した博論は、土に蒔かれた種にも似て。よき土の中で殻が破れ、根を出し、発芽の手伝いを編集者はする。一冊の本が上梓される。地上に芽を出し、初めて、これはアサガオ、これはカラマツと。体験はひらき声を発する。成長し、次なる時代への種を宿し。生涯つづく研究の始まり。文章との対話に学び、学術書の出版を手がけて20年。高邁と崇高を指し示し、未来をひらく学問の営みに謙虚でありたいと願います。
当社代表の三浦衛によるブログ「よもやま日記」の以下ページもご覧ください。
以下の画像をクリックしていただくと、原寸大のポスターが表示されます。