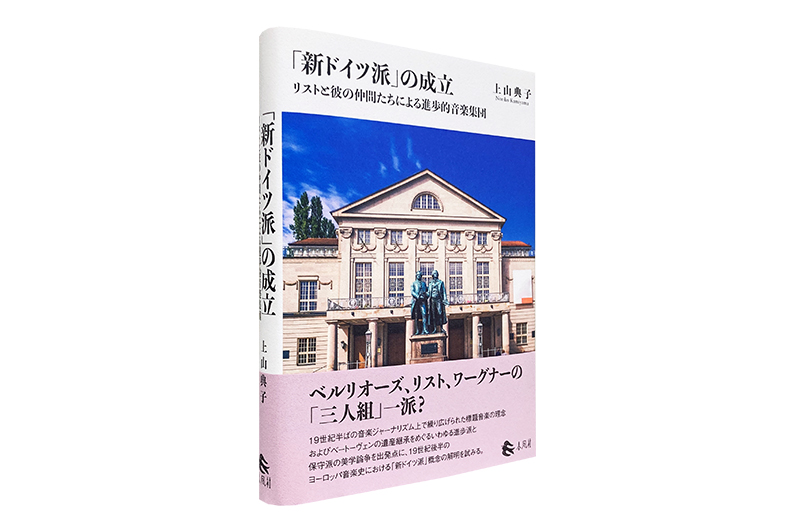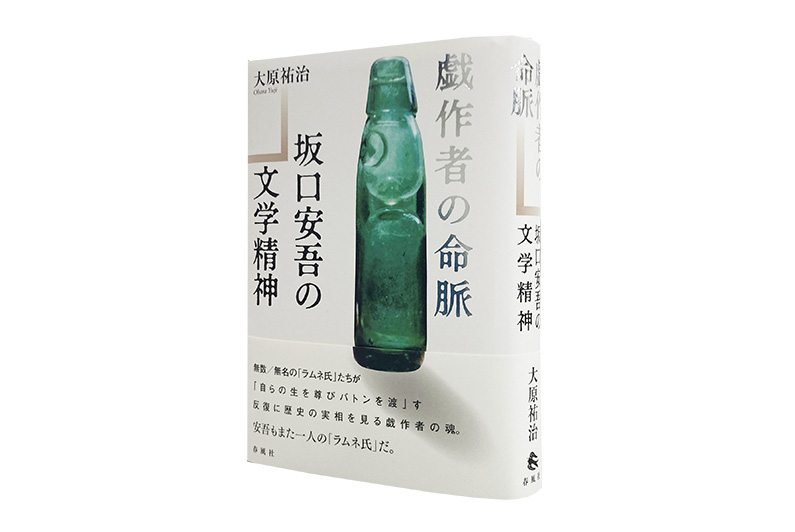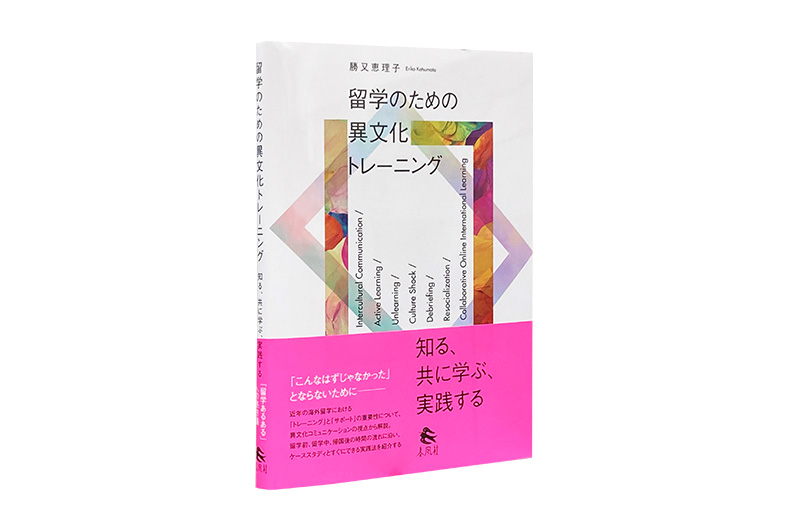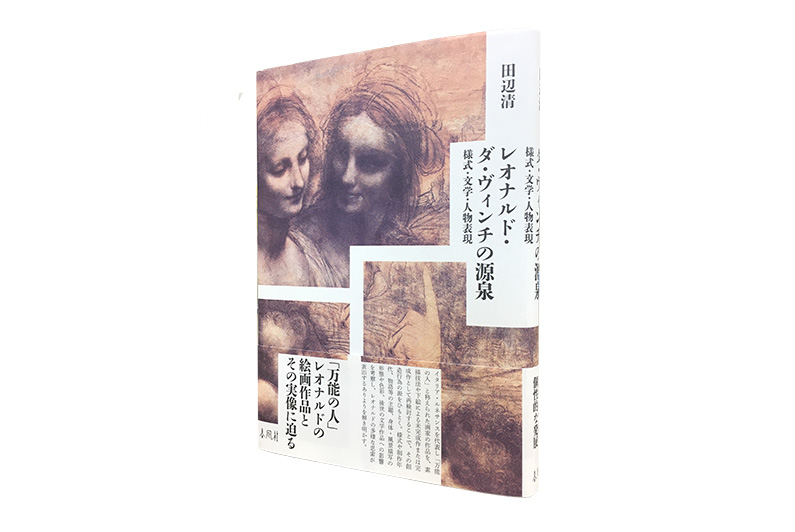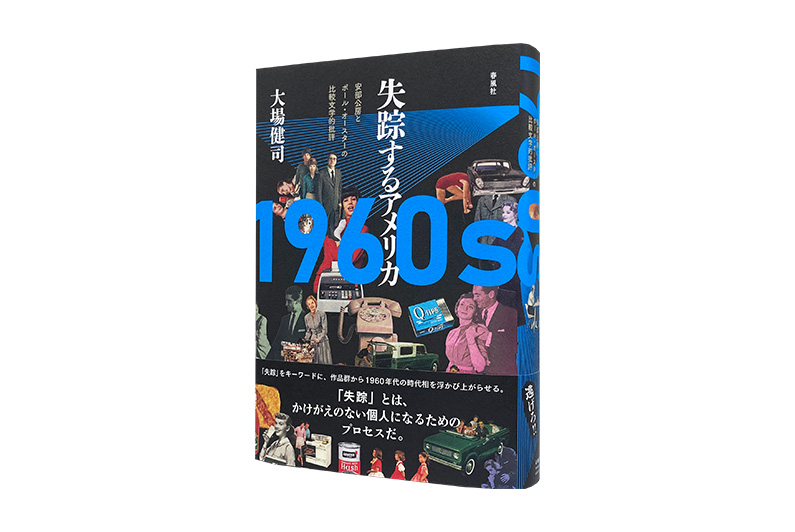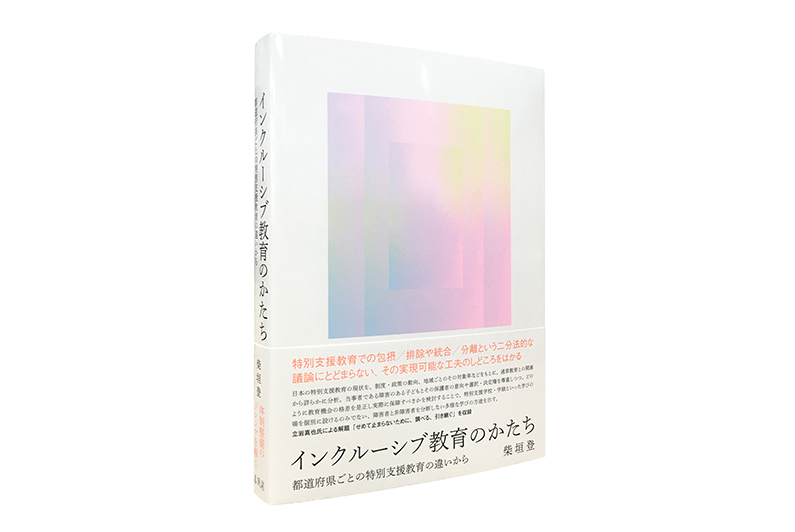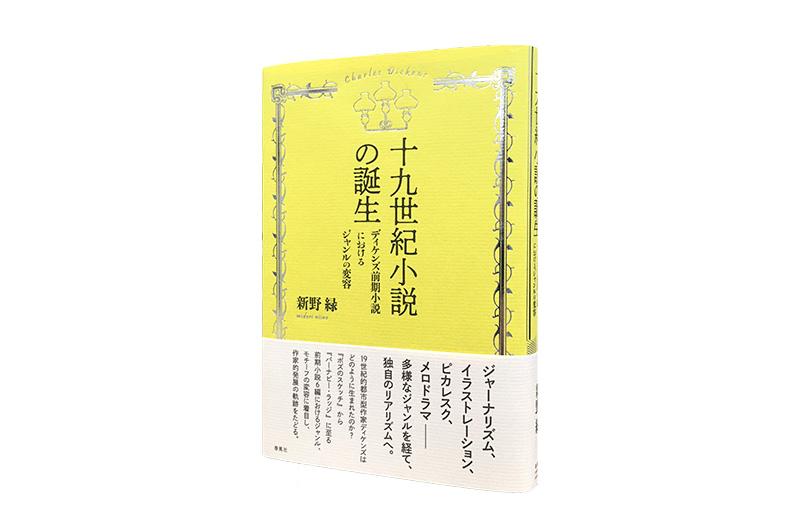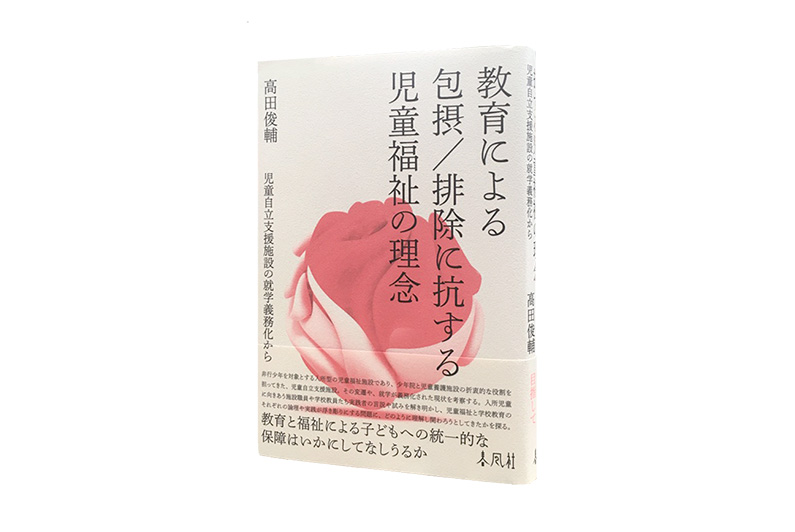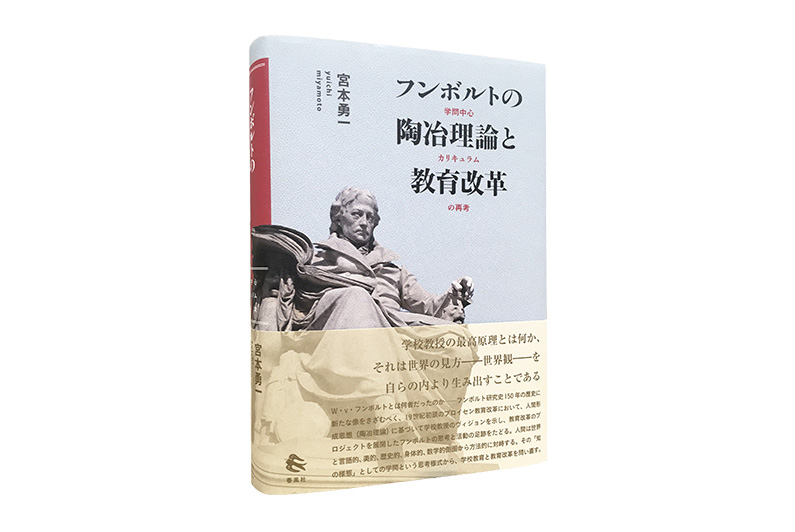美学会編『美学』第264号(2024年7月)に、上山典子著『「新ドイツ派」の成立―リストと彼の仲間たちによる進歩的音楽集団』の書評が掲載されました。評者は長野順子先生(大阪芸術大学)です。「複雑な様相を見せる「新ドイツ派」の成立と変遷を考察した本書は、広範な資料を丹念に読み解きながら当時の音楽家、音楽史家、批評家たちの錯綜した相関関係を解きほぐし、時代の一局面を活写した」
『戯作者の命脈―坂口安吾の文学精神』(大原祐治 著)、『留学のための異文化トレーニング―知る、共に学ぶ、実践する』(勝又恵理子 著)の電子書籍を配信開始しました。電子書籍は Amazon Kindle、楽天Kobo、Google Play などの電子書店でお求めになれます。
美学会編『美学』第264号(2024年7月)に、田辺清著『レオナルド・ダ・ヴィンチの源泉―様式・文学・人物表現』の書評が掲載されました。評者は池上英洋先生(東京造形大学)です。「「レオナルドへの/レオナルドからの」という二方向の源泉の流れの指摘に加え、それが素描や絵画における主題と技法という異なるレイヤーとの繋がりの可能性までを視野に入れている」
2024年6月8-9日に開催された日本比較文学会第86回全国大会にて、大場健司氏および著書『1960s 失踪するアメリカ―安部公房とポール・オースターの比較文学的批評』が、第29回日本比較文学会賞を受賞されました!
◆学会ウェブサイトはこちらよりご覧になれます。
『ミスター・パートナー』No.386/2024年7月10日発売号で、臼井雅美著『イギリス湖水地方 ピーターラビットのガーデンフラワー日記』が紹介されました。「その美しさや花々に関する知識を与えてくれる」「旅行の友にふさわしいのではないか」
『ミスター・パートナー』No.386/2024年7月10日発売号で、新野緑著『十九世紀小説の誕生―ディケンズ前期小説におけるジャンルの変容』が紹介されました。「英国における出版事情の変遷を解説してくれる、読みやすい研究書」
『日本教育新聞』2024年7月15日号に、高田俊輔著『教育による包摂/排除に抗する児童福祉の理念―児童自立支援施設の就学義務化から』の書評が掲載されました。「就学義務化以降の福祉と教育という異分野での連携・協働の実態と、その可能性を探っている」
▶書評は、下記日本教育新聞ウェブサイト「NIKKYO WEB」よりお読みいただけます。
2024年6月に開催された日本スラブ学研究会総会にて、『戦間期チェコのモード記者 ミレナ・イェセンスカーの仕事―〈個〉が衣装をつくる』の著者・半田幸子先生(東北大学)が、同書により、2022-2023年度日本スラヴ学研究会奨励賞を受賞されました!
◆学会ウェブサイトは下記よりご覧になれます。
日本スラヴ学研究会公式サイト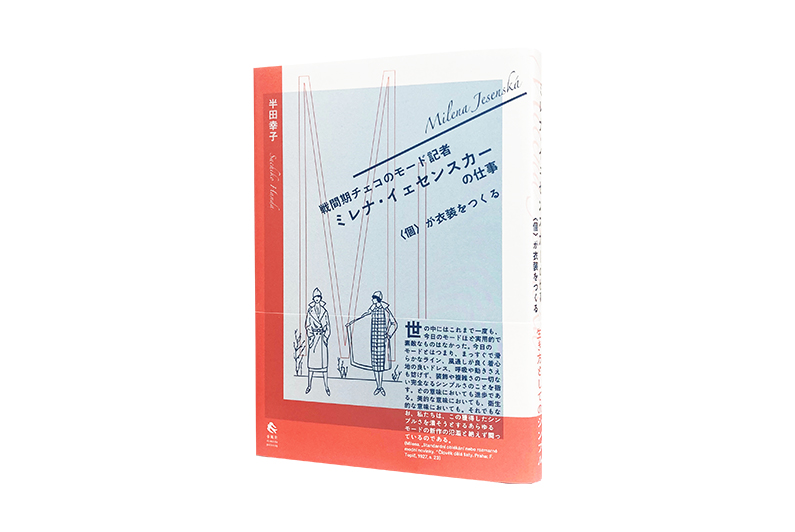
2024年7月6-7日に開催された日本カリキュラム学会第35回大会で、宮本勇一氏(岡山大学)および著書『フンボルトの陶冶理論と教育改革―学問中心カリキュラムの再考』が、2023年度研究奨励賞を受賞いたしました。おめでとうございます。
▶学会ウェブサイトは下記よりご覧になれます。
https://jscs-info.jp/