2024年7月6-7日に開催された日本カリキュラム学会第35回大会で、田中怜氏(筑波大学)および著書『学校と生活を接続する―ドイツの改革教育的な授業の理論と実践』が、2023年度研究奨励賞を受賞いたしました。おめでとうございます。
▶学会ウェブサイトは下記よりご覧になれます。
https://jscs-info.jp/
2024年7月6-7日に開催された日本カリキュラム学会第35回大会で、田中怜氏(筑波大学)および著書『学校と生活を接続する―ドイツの改革教育的な授業の理論と実践』が、2023年度研究奨励賞を受賞いたしました。おめでとうございます。
▶学会ウェブサイトは下記よりご覧になれます。
https://jscs-info.jp/
『図書新聞』3646号(2024年7月6日付)に吉村竜 著『果樹とはぐくむモラル:ブラジル日系果樹園からの農の人類学』の書評が掲載されました。評者は根川幸男先生(国際日本文化研究センター)です。「かつて味わったこの地の柿の甘さを久しぶりに思いだす」
『留学のための異文化トレーニング―知る、共に学ぶ、実践する』(勝又恵理子 著)オンデマンド版が出来しました。オンデマンド版は、Amazonウェブサイトにてお求めになれます。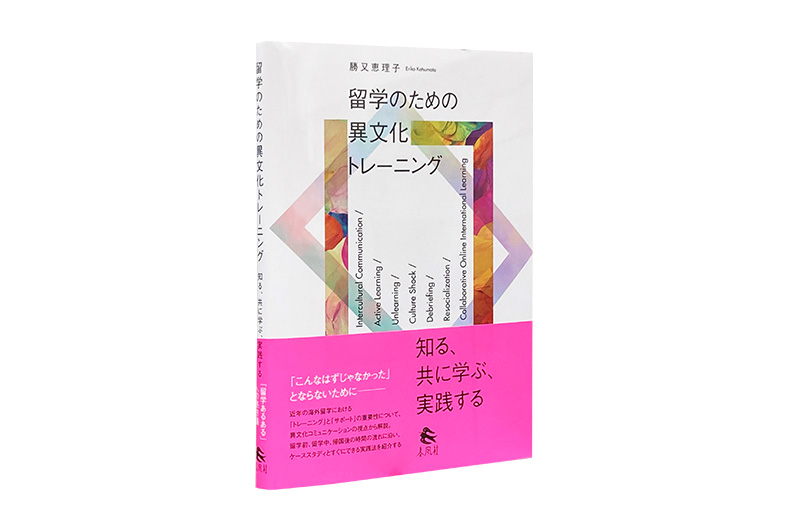
『ローカル・フードシステムと都市農地の保全―庭先直売、移動販売、産消提携の立地と生産緑地』(佐藤忠恭 著)の書評が『農業経済研究』(2024年6月)に掲載されました。評者は高橋克也氏(農林水産政策研究所)です。「今後の経営意向を含めた実際の都市農家の詳細な経営実態など多くの示唆を与えており,都市農業を研究するうえでの必読すべき一冊である」
『週刊読書人』第3543号/2024年6月14日号にオスカー・G・ブロケット、ロバート・J・ボール、ジョン・フレミング、アンドルー・カールソン著、香西史子訳『エッセンシャル・シアター 西洋演劇史入門』の書評が掲載されました。評者は武田寿恵先生(明治大学兼任講師)です。「過去の演劇上演を「生」の演劇へと塗り替える演劇研究の入門書」
『スラブ学論集』第27号に半田幸子(著)『戦間期チェコのモード記者 ミレナ・イェセンスカーの仕事―〈個〉が衣装をつくる』が掲載されました。評者は藤田教子先生(カフカ研究者)です。
「チェコのジャーナリズムに対しては、ペンで闘う人々であるというイメージをいつしか持っていた。しかし、本書と巡り合う幸運を得、チェコのジャーナリズムの明るい側面にも知見を広めることができた」
本文はこちらで公開されています。
原爆文学研究会編『原爆文学研究』第22号(2024年2月)に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学(テクスト)化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は後山剛毅先生(立命館大学)/加島正浩先生(富山高等専門学校)です。
「今ある沖縄の〈声〉を掬いあげるためにこそ、過去から到来する〈声〉に耳を傾ける」/「これまでに「何が」(暴力的に)排除されてきたのかを明らかにし、それを読み取ることのできる身体を構築しなおす」
『図書新聞』第3644号/2024年6月22日号に、山﨑眞紀子、江上幸子、石川照子、渡辺千尋、宜野座菜央見、藤井敦子、中山文、姚毅、鈴木将久、須藤瑞代著『日中戦時下の中国語雑誌『女声』―フェミニスト田村俊子を中心に』の書評が掲載されました。評者は高田晴美先生(四日市大学総合政策学部教授)です。「抗日下の上海にて日本軍の支援で刊行された中国語雑誌の分析」
『日本経済新聞』2024年6月8日朝刊、「読書」面記事「安部公房生誕100年で再び注目 超現実が問う21世紀の現実」の中で、岩本知恵著『安部公房と境界―未だ/既に存在しない他者たちへ』が紹介されました。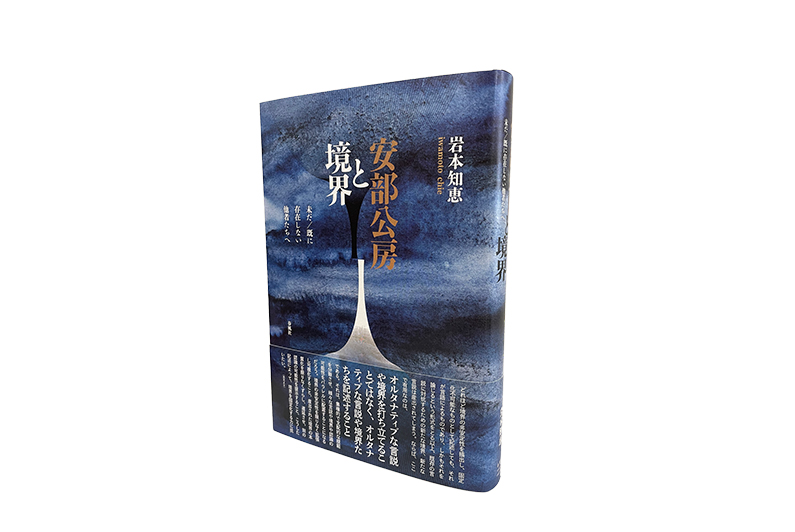
『ラテンアメリカ・レポート』2024年41巻1号に谷口智子(編)『タキ・オンコイ 踊る病:植民地ペルーにおけるシャーマニズム、鉱山労働、水銀汚染』の書評が掲載されました。評者は村井友子氏(アジア経済研究所)です。
「スペイン植民地支配下にあった16世紀ペルーの歴史的真実に迫る意欲作」
全文はこちらで公開されています。