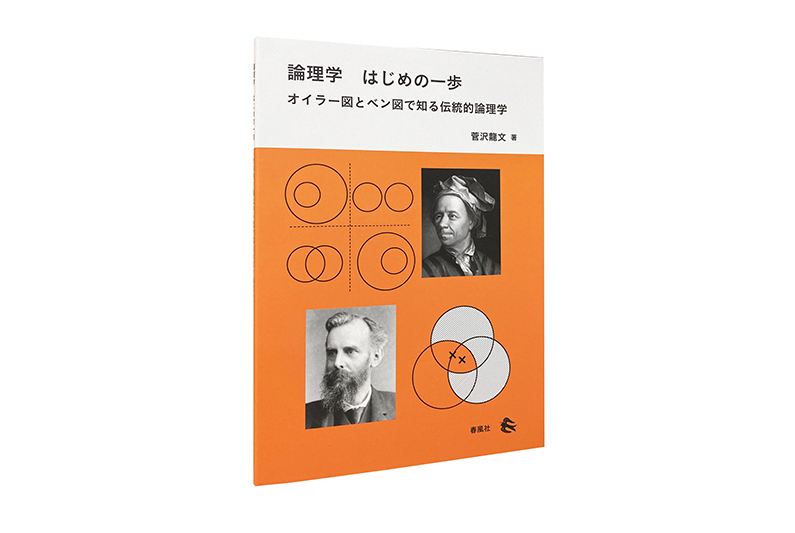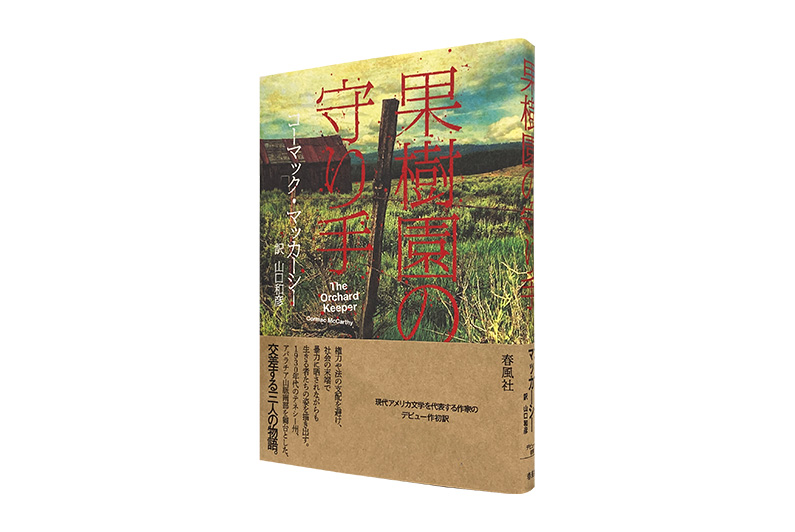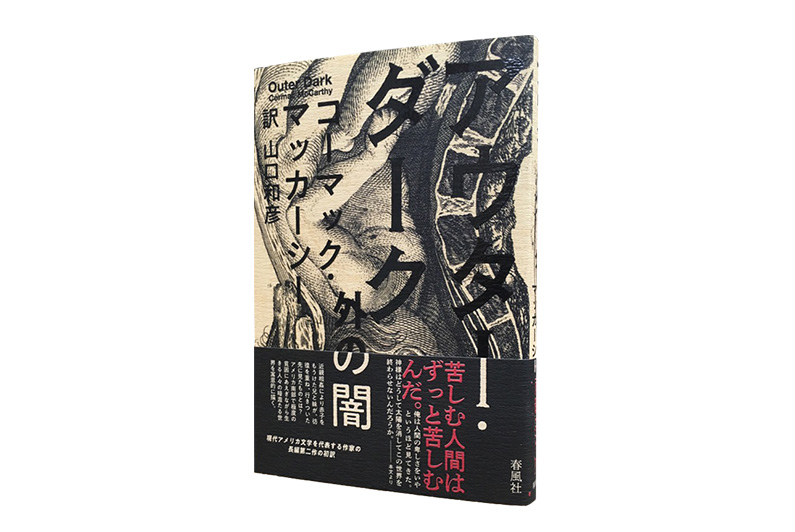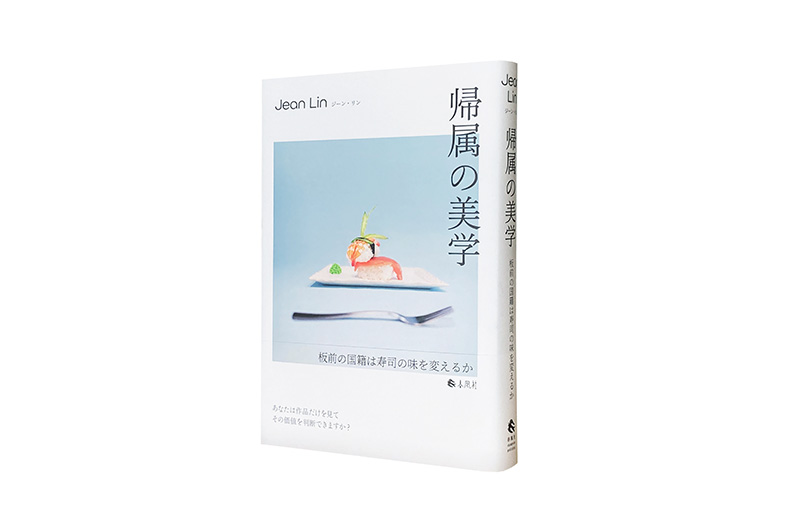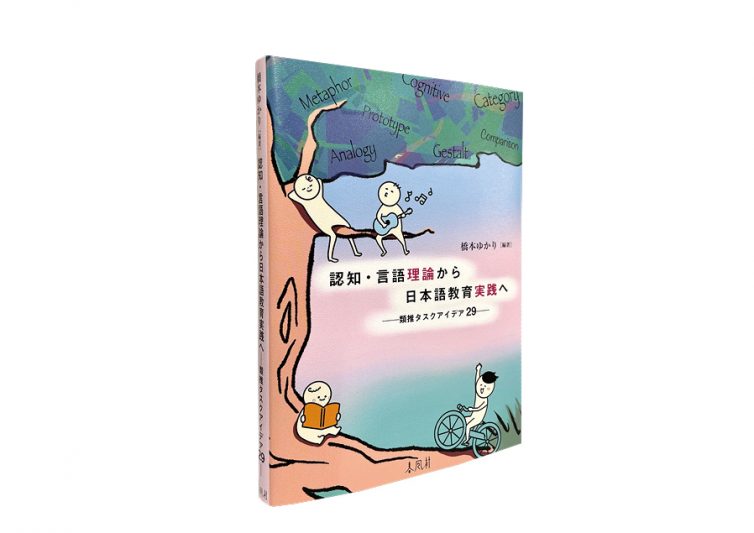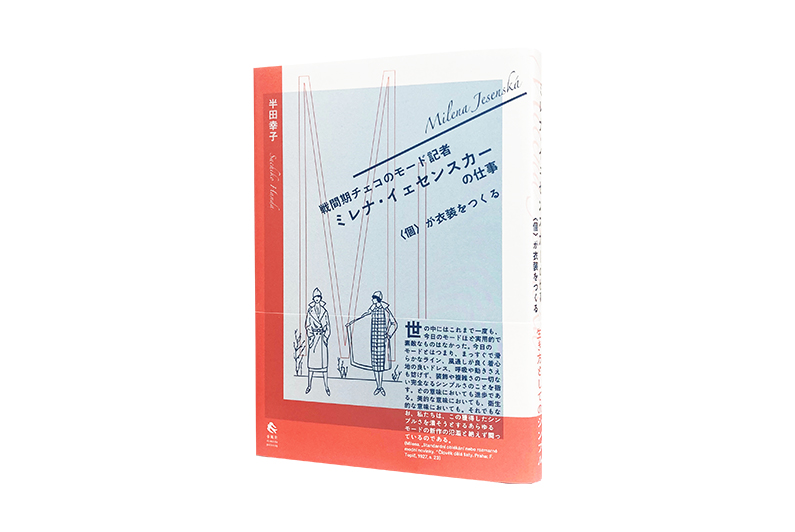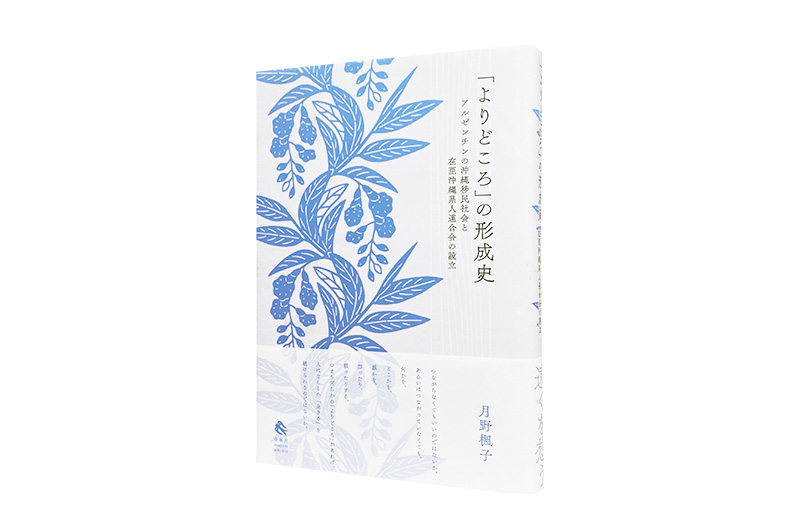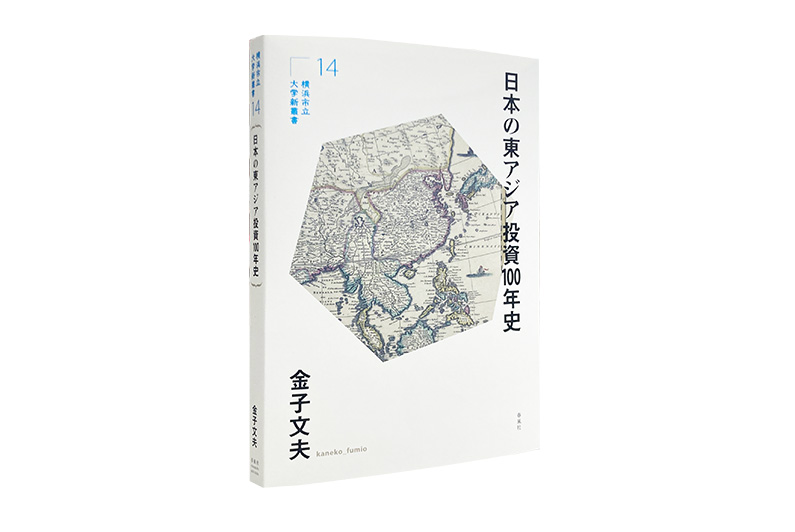『異文化間教育』第59号(異文化間教育学会編)に、勝又恵理子著『留学のための異文化トレーニングー知る、共に学ぶ、実践する』の書評が掲載されました。評者は岡村郁子先生(東京都立大学教授)です。「著者の…長年にわたる留学経験および帰国後の大学における留学相談の経験による知見に裏打ちされた、実用的な良書」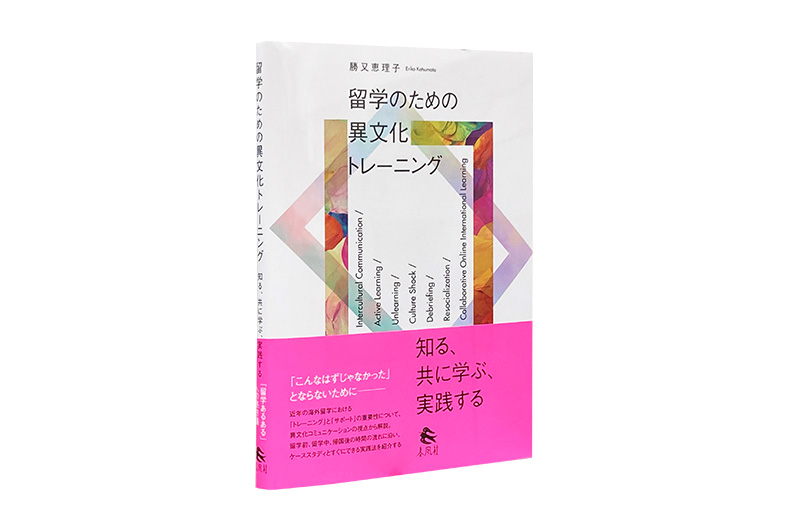
『図書新聞』第3635号/2024年4月13日号に、コーマック・マッカーシー著/山口和彦訳『アウター・ダークー外の闇』の書評が掲載されました。評者は小平慧氏(翻訳者/ライター)です。「人間の意識と無意識の構造を射抜く現代的な射程 貧しい人々の暮らしの描写は「生活感」にあふれている」
東京大学学術成果刊行助成(東京大学而立賞)に採択された著作を著者自らが語る広場である「UTokyo BiblioPlaza」で、Jean Lin著『帰属の美学:板前の国籍は寿司の味を変えるか』紹介されました。著者による本書の紹介がお読みになれます。
『インターカルチュラル』22(日本国際文化学会年報)に、半田幸子著『戦間期チェコのモード記者 ミレナ・イェセンスカーの仕事—〈個〉が衣装をつくる』の書評が掲載されました。評者は葉柳和則先生(長崎大学)です。「本書が生み出したイェセンスカー研究の土台で、(中略)美学的・デザイン学的系譜の輪郭が浮かび上がるときが楽しみである」
『インターカルチュラル』22(日本国際文化学会年報)に、月野楓子著『「よりどころ」の形成史―アルゼンチンの沖縄移民社会と在亜沖縄県人連合会の設立』の書評が掲載されました。評者は目黒志帆美先生(東北大学)です。「本書は、個人の「よりどころ」へのまなざしを通じて文化間接触のダイナミズム解明に迫る研究であり、国際文化学における新たな視座をここにみることができる」
『経営史学』第58巻第4号に金子文夫著『日本の東アジア投資100年史』の書評が掲載されました。評者は須長徳武先生(立教大学)です。「本書はマクロ統計と進出企業活動をバランス良く接合し、日本のアジア投資100年の時期的変化と特質を通史として描出した初めての研究成果である。各時期の的確な論点提示や先行研究に対する周到な目配りから、今後の研究進展に随伴する優れた水先案内となろう。」