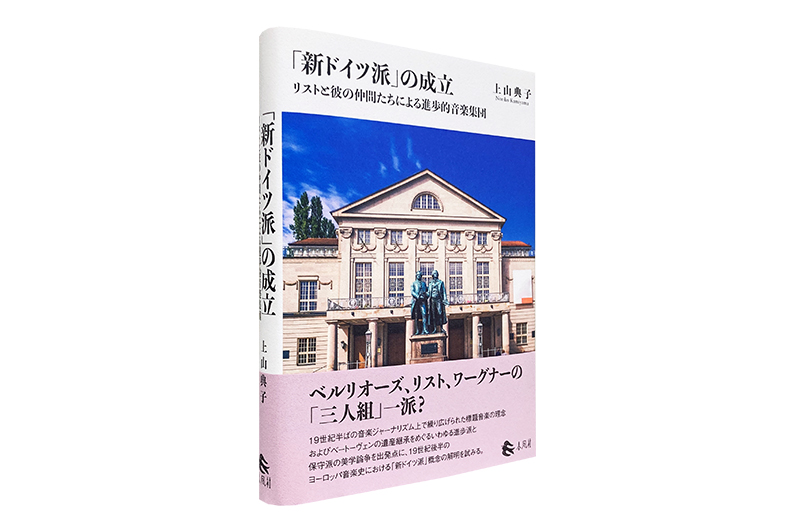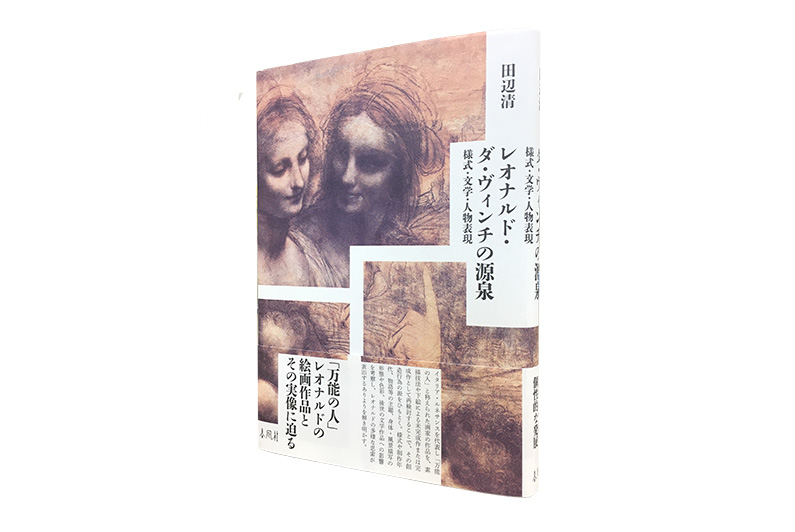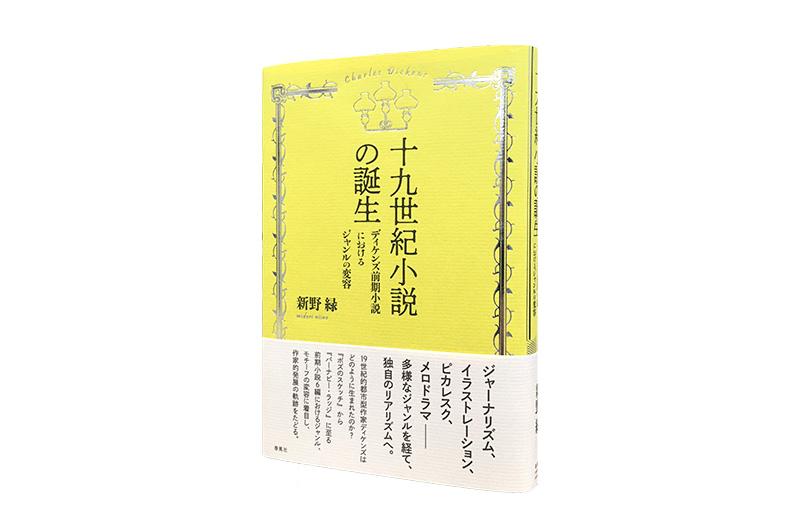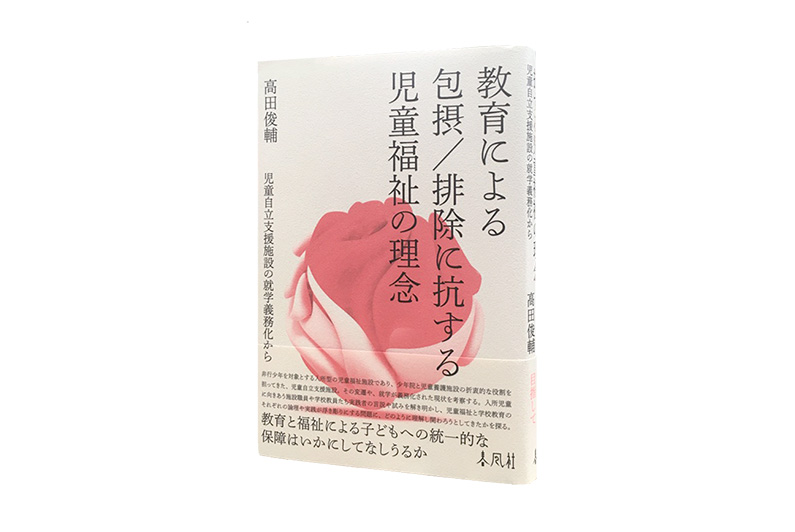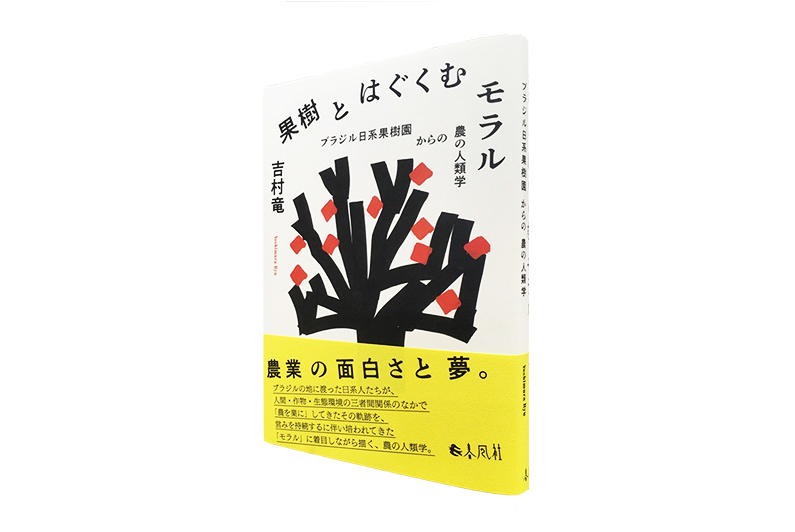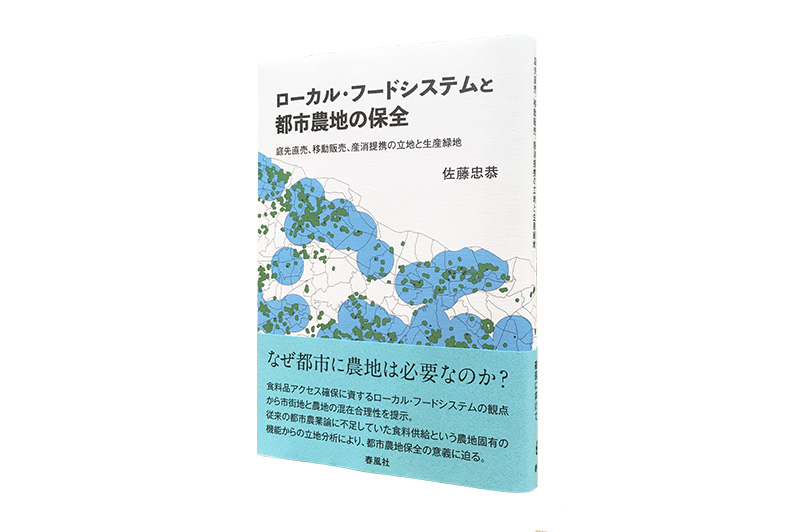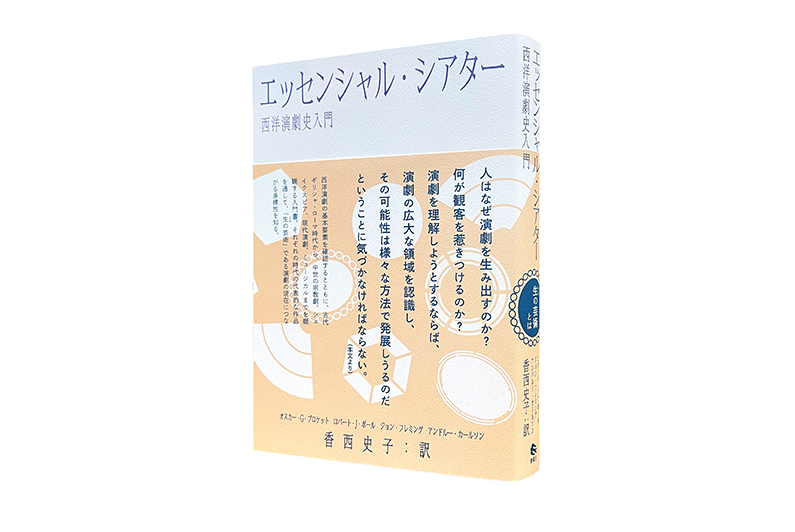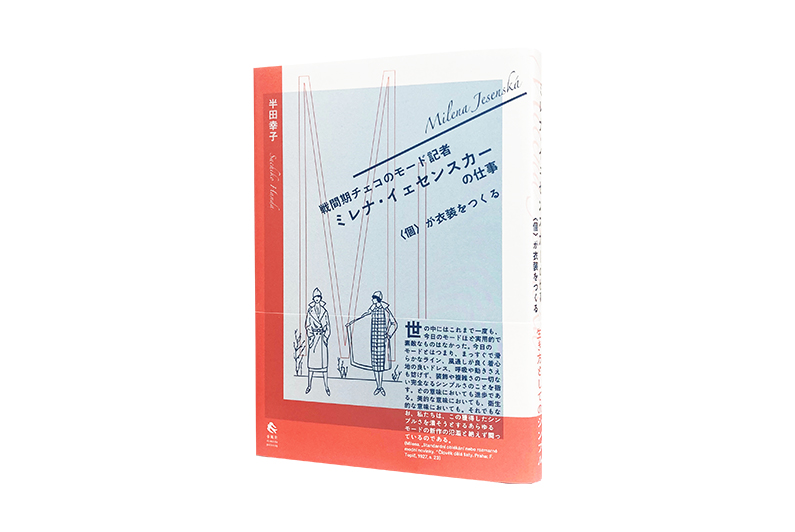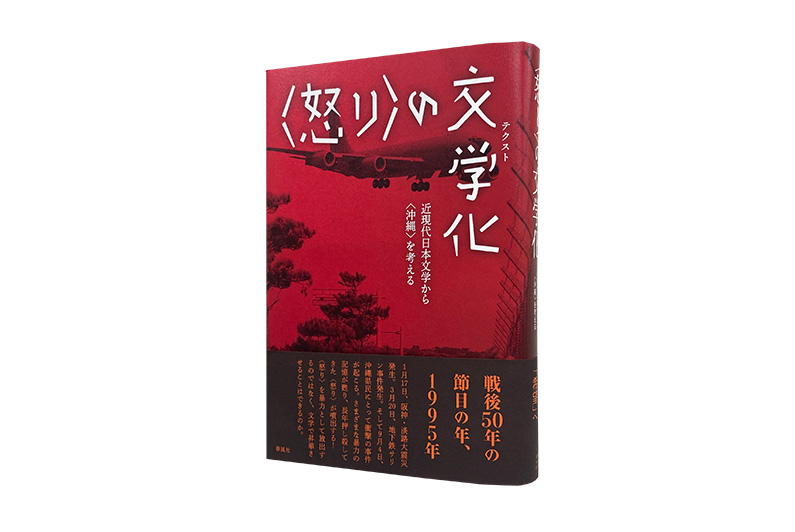美学会編『美学』第264号(2024年7月)に、上山典子著『「新ドイツ派」の成立―リストと彼の仲間たちによる進歩的音楽集団』の書評が掲載されました。評者は長野順子先生(大阪芸術大学)です。「複雑な様相を見せる「新ドイツ派」の成立と変遷を考察した本書は、広範な資料を丹念に読み解きながら当時の音楽家、音楽史家、批評家たちの錯綜した相関関係を解きほぐし、時代の一局面を活写した」
美学会編『美学』第264号(2024年7月)に、田辺清著『レオナルド・ダ・ヴィンチの源泉―様式・文学・人物表現』の書評が掲載されました。評者は池上英洋先生(東京造形大学)です。「「レオナルドへの/レオナルドからの」という二方向の源泉の流れの指摘に加え、それが素描や絵画における主題と技法という異なるレイヤーとの繋がりの可能性までを視野に入れている」
『ミスター・パートナー』No.386/2024年7月10日発売号で、臼井雅美著『イギリス湖水地方 ピーターラビットのガーデンフラワー日記』が紹介されました。「その美しさや花々に関する知識を与えてくれる」「旅行の友にふさわしいのではないか」
『ミスター・パートナー』No.386/2024年7月10日発売号で、新野緑著『十九世紀小説の誕生―ディケンズ前期小説におけるジャンルの変容』が紹介されました。「英国における出版事情の変遷を解説してくれる、読みやすい研究書」
『日本教育新聞』2024年7月15日号に、高田俊輔著『教育による包摂/排除に抗する児童福祉の理念―児童自立支援施設の就学義務化から』の書評が掲載されました。「就学義務化以降の福祉と教育という異分野での連携・協働の実態と、その可能性を探っている」
▶書評は、下記日本教育新聞ウェブサイト「NIKKYO WEB」よりお読みいただけます。
『図書新聞』3646号(2024年7月6日付)に吉村竜 著『果樹とはぐくむモラル:ブラジル日系果樹園からの農の人類学』の書評が掲載されました。評者は根川幸男先生(国際日本文化研究センター)です。「かつて味わったこの地の柿の甘さを久しぶりに思いだす」
『ローカル・フードシステムと都市農地の保全―庭先直売、移動販売、産消提携の立地と生産緑地』(佐藤忠恭 著)の書評が『農業経済研究』(2024年6月)に掲載されました。評者は高橋克也氏(農林水産政策研究所)です。「今後の経営意向を含めた実際の都市農家の詳細な経営実態など多くの示唆を与えており,都市農業を研究するうえでの必読すべき一冊である」
『週刊読書人』第3543号/2024年6月14日号にオスカー・G・ブロケット、ロバート・J・ボール、ジョン・フレミング、アンドルー・カールソン著、香西史子訳『エッセンシャル・シアター 西洋演劇史入門』の書評が掲載されました。評者は武田寿恵先生(明治大学兼任講師)です。「過去の演劇上演を「生」の演劇へと塗り替える演劇研究の入門書」
『スラブ学論集』第27号に半田幸子(著)『戦間期チェコのモード記者 ミレナ・イェセンスカーの仕事―〈個〉が衣装をつくる』が掲載されました。評者は藤田教子先生(カフカ研究者)です。
「チェコのジャーナリズムに対しては、ペンで闘う人々であるというイメージをいつしか持っていた。しかし、本書と巡り合う幸運を得、チェコのジャーナリズムの明るい側面にも知見を広めることができた」
本文はこちらで公開されています。
原爆文学研究会編『原爆文学研究』第22号(2024年2月)に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学(テクスト)化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は後山剛毅先生(立命館大学)/加島正浩先生(富山高等専門学校)です。
「今ある沖縄の〈声〉を掬いあげるためにこそ、過去から到来する〈声〉に耳を傾ける」/「これまでに「何が」(暴力的に)排除されてきたのかを明らかにし、それを読み取ることのできる身体を構築しなおす」