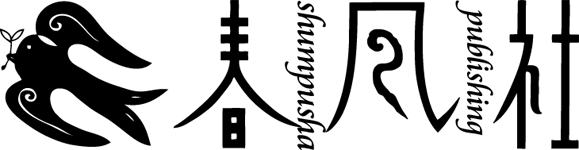【特別寄稿】ルイーズ・グリュックの詩をどう読むか――『アヴェルノ』翻訳を終えて(訳者:江田孝臣)
転機
第四詩集『アキレスの大勝』(The Triumph of Achilles, 1985)で、同一主題のもとに短い抒情詩を連ねて一冊の長篇詩を紡ぎ出す、リリック・シーケンス(lyric sequence)という形式に開眼し(特に、自伝的な第二部の「マラトン」(“Marathon”)にその原型が見い出せる)、これがそののち詩人として大成する契機となった。しかし、第一詩集『長子』(Firstborn, 1968)に明らかだが、若い頃には、読者の理解を拒むような、相当に尖鋭的な詩を書いている。初期のロバート・ロウエル(Robert Lowell, 1917-77)や、コロンビア大学で五年間授業を取ったスタンリー・キューニッツ(Stanley Kunitz, 1905–2006)の影響が感じられる(もっともキューニッツには批判され、それがきっかけで長く師事することになる)。詩人自身、「第一詩集を読んだら、侮蔑されたように感じるだろうから読んでほしくない」と言っている。初めての読者は、近作の『アヴェルノ』か『しとやかで貞淑な夜』(Faithful and Virtuous Night, 2014)から始めるのがよいと勧めている。ところが、読者の中には、第二詩集以降の平易な詩風に飽き足らないマニアックな天邪鬼も少なくないらしく、そういう読者は、人を寄せつけないこの難解な第一詩集を好んで読むらしい。これにはグリュック自身があきれている。
問題含みの一人称
これは第一詩集だけの特徴ではないが、通常の抒情詩なら詩人と同一視して問題ない一人称単数代名詞(“I”)も、グリュックの場合、短絡的に詩人と結びつける読みは危うい。つまり素朴な自伝詩、告白詩ではない。初期作品には、「わたし」が他人の仮面をかぶる趣向の〈ペルソナ詩〉さえ存在する。『アヴェルノ』の表題詩「アヴェルノ」の一人称の話者も、年老いて家族に疎まれるイタリア人の男だ。『しとやかで貞淑な夜』を読んでも、自分の詩が自伝詩として読まれることに激しく反発していることが分かる(「主要詩集紹介」参照)。インタビューでも、グリュックは自分の詩が自伝と見なされることにいら立ちを隠さない。
自伝詩からの脱却
もっとも、現時点から振り返れば、『アキレスの大勝』や最初の成功作『アララト』(Ararat, 1990)が、自伝的要素の色濃い詩集であることは否定できない。『アララト』出版当時に、いわゆる「告白派」第二世代の作品と見なされたとしても不思議はない。しかしながら、グリュックは自伝的な詩の限界に自覚的であり、この成功に甘んじることはなかった。他の新しい告白派詩人たちを批判的に参照しつつ、かつロウエルの高弟フランク・ビダート(Frank Bidart)などの詩業を指針にして、純粋な自伝詩(正確には「読者に自伝と思わせる詩」というべきか)からの脱却を模索していた(評論“The Forbidden” [Proofs & Theories所収]を参照)。その結果が、よりいっそうの成功をもたらした『ワイルド・アイリス』(The Wild Iris, 1992)である(「主要詩集紹介」参照)。
詩の言葉
詩の言葉自体は、第二詩集以降きわめて平明な口語になる。二十世紀初めにエズラ・パウンド(Ezra Pound, 1885-1972)やウィリアム・カーロス・ウィリアムズ(William Carlos Williams, 1883-1963)などモダニズムの詩人たちによって開発され、現在の主流となっている口語自由詩体(フリー・ヴァース free verse)で書かれている。散文を読むのとほぼ変わらない。饒舌を排して、言葉を切り詰めるのもグリュックの大きな特徴だ。これはモダニズムの特徴でもあるが、その先駆となったエミリ・ディキンスン(Emily Dickinson, 1830-86)の詩も思わす。グリュックは幼い頃から愛読していた。詩人としての構え(姿勢)もよく似ている。といっても人嫌いでも隠遁詩人でもなく、コロナ禍までは毎晩のように友人たちと外食していたという。
明らかにディキンスンを意識した詩も見い出せる。たとえば1999年刊の『新生』(Vita Nova)には「着衣」(“The Garment”)と題された詩がある。次節で論じるグリュック詩の主題にもつながるものがある。
着衣
わたしの魂が干乾びた。
火に投げ入れられた魂のように。だが消滅するほど
干乾びたわけではない。パリパリになっても
生き残った。孤独ではなく
不信のために、脆くなった。
暴力の余波だった。
肉体を離れるように誘われた精神よ
あたかも、これから
神に釈明するかのように、震えながら
裸をさらす精神よ
恩寵の約束につられて
孤独から誘い出された精神よ
お前は本当に新しい存在に
たじめるのか。
わたしの魂はしぼみ、ちぢんだ。
肉体は魂には大き過ぎる着衣になった。
そして望みが返還されたとき
それはまったく別の望みだった。
末尾二行が謎めいているが、必ずひとひねり入れるというディキンスンの多くの詩のエンディングの特徴を、心憎いまで巧みに捉えている。
拒食症と精神分析治療、詩の主題
現代アメリカ詩は、経済格差、人種民族差別、性差別、環境、戦争、等々の主題であふれている。グリュックの詩には、ほぼどれも見い出せない。彼女の詩をつらぬく主題は、ひとことで言えば、おのれの魂との対話、内面との対話である。現代では、これまた「古風な」主題である。この主題は、若いグリュックが病んだ拒食症と、その治療のために受けた精神分析療法の経験から産まれた、と言ってよい。高校生のとき発症し治療が長引いたため、コロンビア大学に入学したものの、卒業していない。母親が教育熱心だったことは前述したが、拒食症は母離れに伴なう葛藤が原因だった、とグリュック自身が明言している。七年間に及んだ精神分析療法の中で、おのれの魂と真正面から向き合うことになった。夢分析や神話の解釈など精神分析の技法にも深い関心を持ったと思われる。このことはとりわけ『アヴェルノ』を読めば自明である。ただ彼女自身の生の経験が、そのまま作品に投入されているわけではない。それらの経験が、とくにピュリッツァー賞を受賞した『ワイルド・アイリス』以降は、高度に寓話化され、神話化される。あるいは、寓話や神話と対照される形で提示される。前述したように、自分の作品が自伝として読まれることにグリュックはいら立ちを隠さないが、それは寓話や神話を自伝に「還元」してしまうような読み方に対する憤慨である。彼女の詩を衝き動かしている力が詩人の経験に由来することに変わりはない。
詩に登場する人物は、『アヴェルノ』まではほぼ家族に限られる。詩人とおぼしき話者以外で圧倒的な存在感を持つのは母親である。次いで死んだ姉と夫(ジョン)。妹と父親は不在ではないが、影が薄い。どの詩集にも何らかの形で、苦難(suffering)を克服する(survive)モチーフが見出せる。その苦難の原点にあるのが母親との葛藤である。
ジェンダー規範をめぐる世代格差、グリュックの特異性
戦後の1950年代に思春期を迎え、60年代に成人したグリュックのような女性たちと、その母親たちの世代では、性・恋愛・結婚をめぐる価値観は、言うまでもなく大きく異なる。ある評論では、古いジェンダー規範を「ジェンダーという棺桶」と呼んでいる(“On Stanley Kunitz” [Proofs & Theories所収])。グリュックと母親の葛藤がこのような世代間格差を反映していることは、『アヴェルノ』所収の「プリズム」(“Prism”)や「エコー」(“Echoes”)を見ても歴然としている。しかしながら、母親との葛藤が原因で七年間も拒食症に苦しんだグリュックの例は、やはり特殊というほかない。