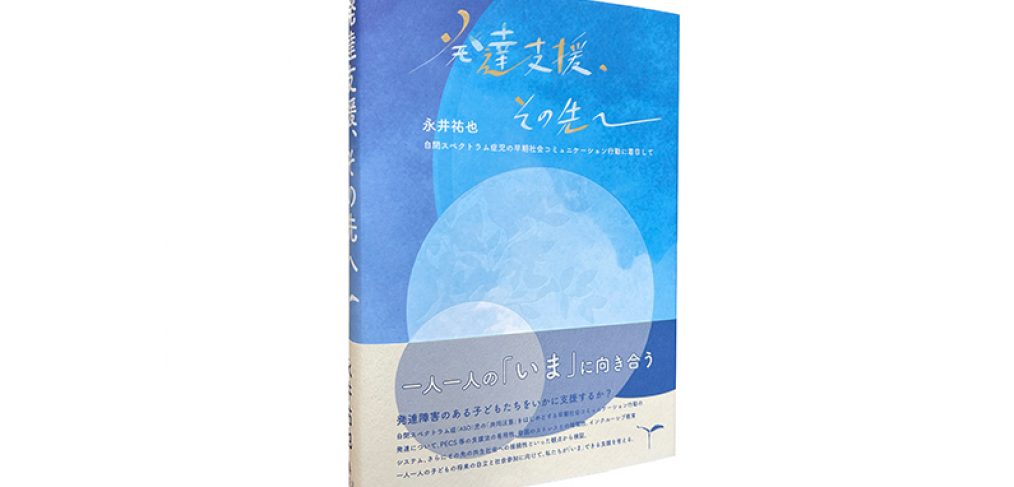イギリス湖水地方
ピーターラビットのガーデンフラワー日記
- 臼井雅美(著)/2024年6月
- 2200円(本体)/四六判並製162頁
- 装丁・レイアウト:矢萩多聞
イギリス湖水地方で出会った、個性豊かな花々の共演――
季節の移ろいにそってトレッキングした際に出会った、カントリー・ハウスやコテージなどのガーデンとそこに植えられた草木をカラー写真とともに紹介するエッセイ。『イギリス湖水地方―ピーターラビットの野の花めぐり』(2023年)の続編。
(ISBN 9784861109485)
目次|contents
プロローグ
Ⅰ 春の囁きに誘われて
春雨のしずくの精たち クロッカス(Crocus)
パレットから飛び出した黄色いブーケ スイセン(Narcissus)
小さな星たちの願い ヒヤシンス(Common Hyacinth)
陽光に向けて、満面の笑顔 パンジー(Pansy)
大切な宝物を守っているよ チューリップ(Tulip)
秘境からやってきた客人 ブルーポピー(Blue Poppy)
にっこり赤ちゃんのほっぺ ナデシコ(Pink)
みんなで集まって大合奏 ベルフラワー(Bell Flower)
黄色のショールがふんわりと レンギョウ(Golden Bells)
ハンカチを振ってごあいさつ モクレン(Mulan Magnolia)
両手からこぼれそうな幸せの束 シャクナゲ(Rhododendron)
秘密の誓いの証 バラ(Rose)
Ⅱ 初夏から夏へ、光との共演
小さな森から顔を出した子供たち ベゴニア(Begonia)
溢れ出る思いを込めて ペチュニア(Petunia)
窓辺のささやき声 ゼラニウム(Garden Geranium)
耳元で揺れるイヤリング フクシヤ(Fuchsia)
小さな蝶たちのピクニック ロベリア(Edging Lobelia)
葉っぱのお皿に添えられて ナスタチウム(Nasturtium)
香りのメッセンジャー ラヴェンダー(Lavender)
虹色のキャンドルが放つ光 アイリス(Iris)
手のひらいっぱいの喜び クレマチス(Clematis)
色と水の魔術師 アジサイ(Japanese Hydrangea)
黄緑のクッションにもたれて ギボウシ(Plaintain Lily)
庭で踊るボールたち アリウム(Allium)
雨上がりに灯った小さな炎 アザレア(Azalea)
天から降り注いだ金の鎖 ラバーナム(Laburnum)
紫のドレスに包まれて フジ(Japanese Wisteria)
揺れる赤いビーズの房 セイヨウスグリ(Gooseberry)
Ⅲ 秋のそよ風に揺れて
星たちの静かな願い アスター(Aster)
宇宙からの使者 コスモス(Common Cosmos)
秋風に向かって、Shall we dance? シュウメイギク(Japanese Anemone)
黄色いコスチュームでイナバウワー イエローコーンフラワー(Yellow Coneflower)
庭を跳ね回る子供たち エキノプス(Echinops)
荒れ地から噴き出した恵み エリカ(Erica)
背伸びをして何を見ているの? ユリ(Lily)
秋を守るガードマン パンパスグラス(Pampas Grass)
恥ずかしがり屋さんのシルエット シクラメン(Cyclamen)
魔女が吹きかけた息の跡 ウィッチヘーゼル(Witch Hazel)
Ⅳ 冬から春に向けて
雪の精からの贈り物 クリスマスローズ(Christmas Rose)
暖かなケープをまとって ツバキ(Camellia Japonica)
寒風からしっかりと身を守って ボケ(Flowering Quince)
お祝いの時がやってきたよ セイヨウヒイラギ(European Holly)
春へのプレリュード セイヨウサンシュユ(Cornelian Cheery Dogwood)
赤と緑のネックレス コトネアスター(Cotoneaster)
ほのかな灯りのシンフォニー ロウバイ(Chimonanthus)
エピローグ
参考文献
著者|author
臼井雅美(うすい・まさみ)
1959年神戸市生まれ。同志社大学文学部・文学研究科教授。神戸女学院大学卒業後、同大学院修士課程修了(文学修士)、1987年ミシガン州立大学修士課程修了(M.A.)、1989年博士課程修了(Ph.D.)。ミシガン州立大学客員研究員を経て、1990年広島大学総合科学部に専任講師として赴任。同大学助教授、同志社大学文学部助教授を経て、2002年より現職。著書に、『記憶と共生するボーダレス文学―9・11プレリュードから3・11プロローグへ』(2018年)、『カズオ・イシグロに恋して』(2019年)、『赤バラの街ランカスター便り』(2019年)、『ビアトリクス・ポターの謎を解く』(2019年)、『不思議の国のロンドン』(2020年)、『ボーダーを超えることばたち―21世紀イギリス詩人の群像』(2020年)、『記憶と対峙する世界文学』(2021年)、『ふだん着のオックスフォード』(2021年)、『イギリス湖水地方アンブルサイドの女神たち』(2021年)、『イギリス湖水地方モアカム湾の光と影』(2022年)、『ブラック・ブリティッシュ・カルチャー―英国に挑んだ黒人表現者たちの声』(2022年)、『イギリス湖水地方におけるアーツ・アンド・クラフツ運動』(2023年)、『イギリス湖水地方―ピーターラビットの野の花めぐり』(2023年)などがある。
この本を注文する
Amazonで注文する e-honで注文する 楽天ブックスで注文する