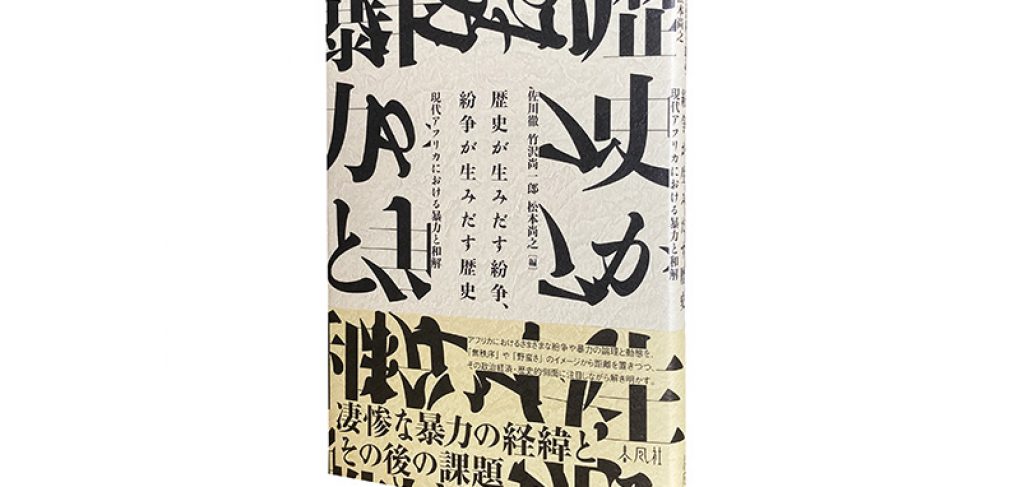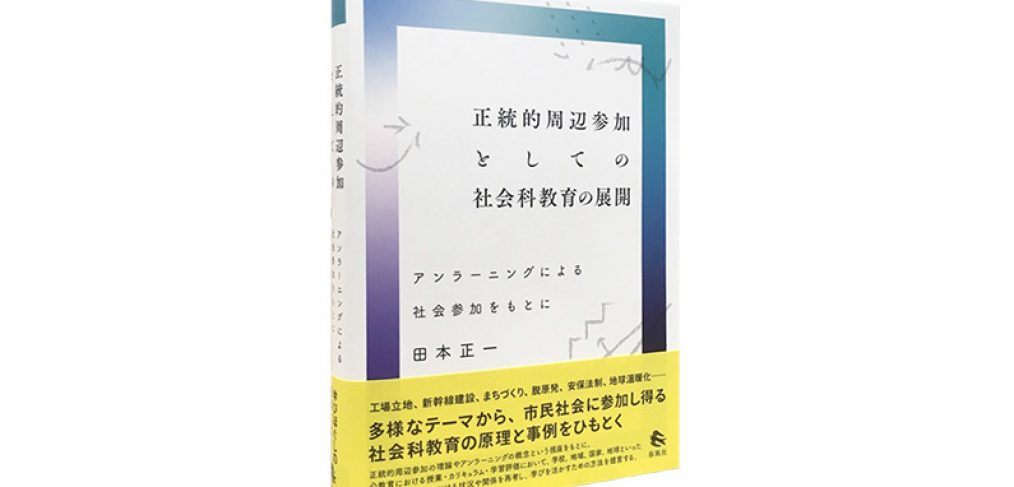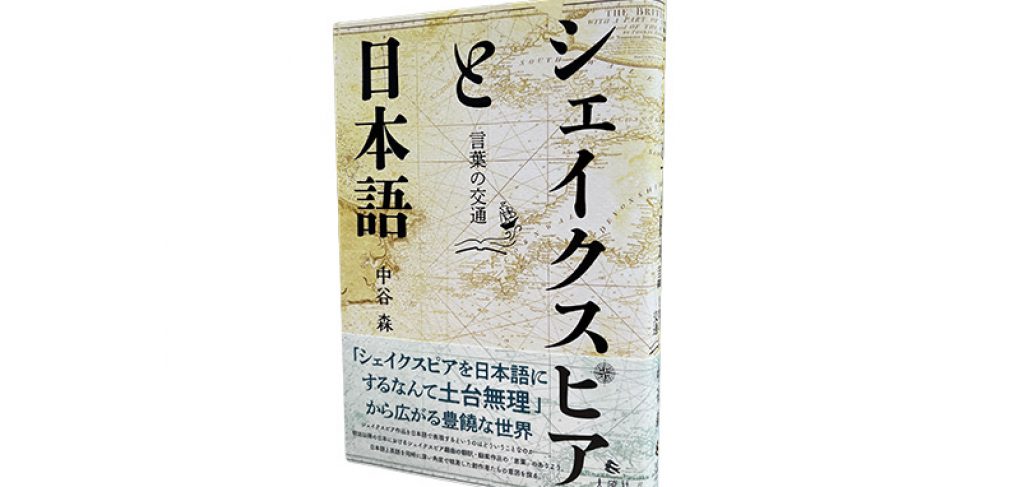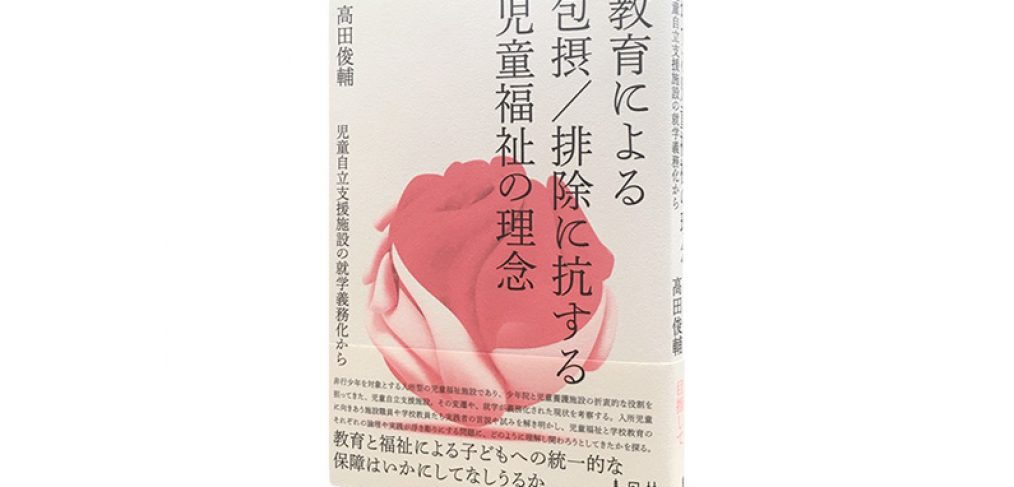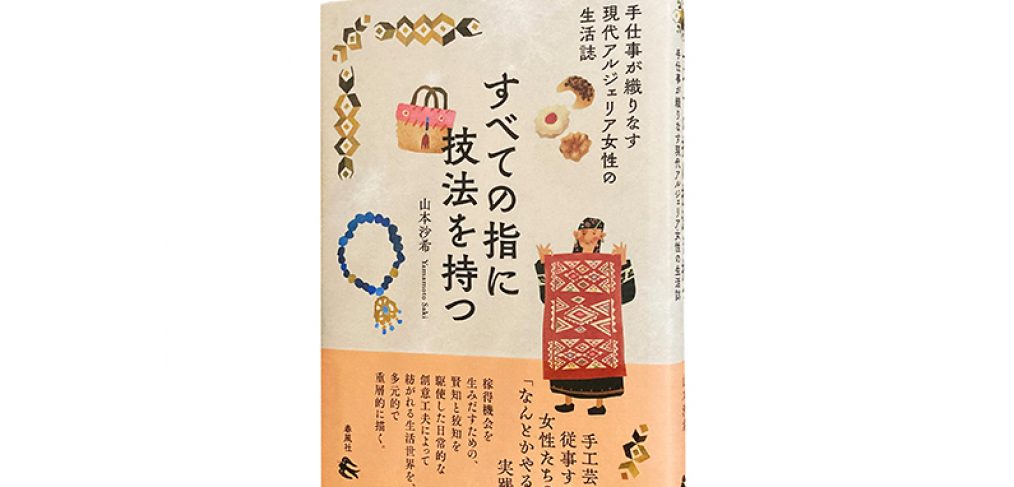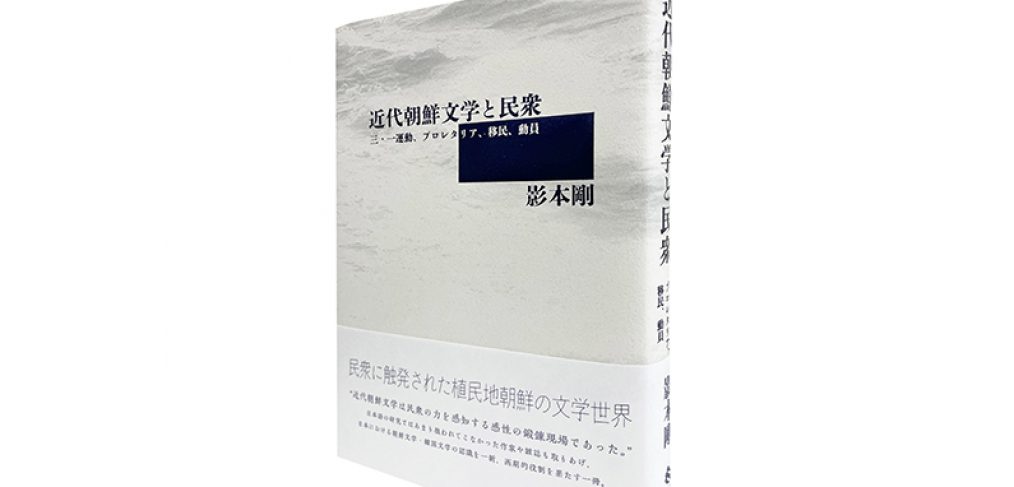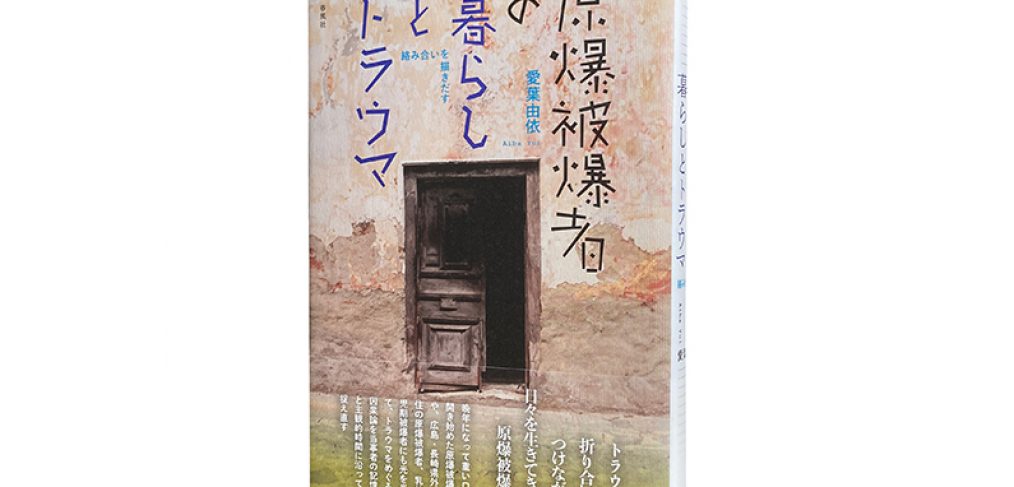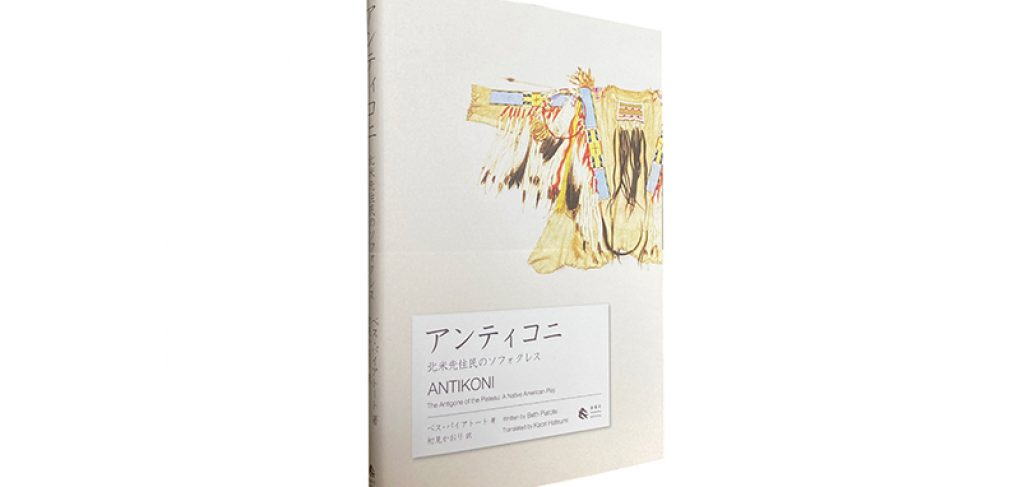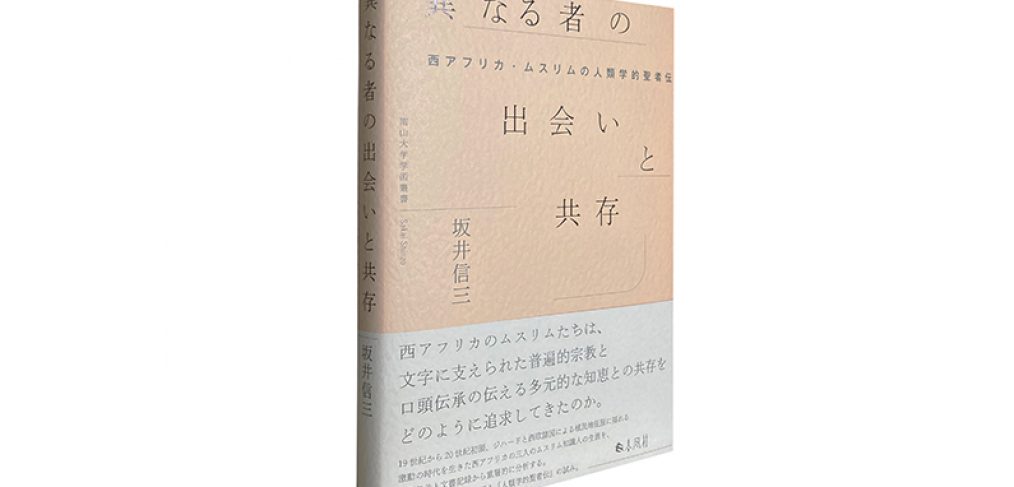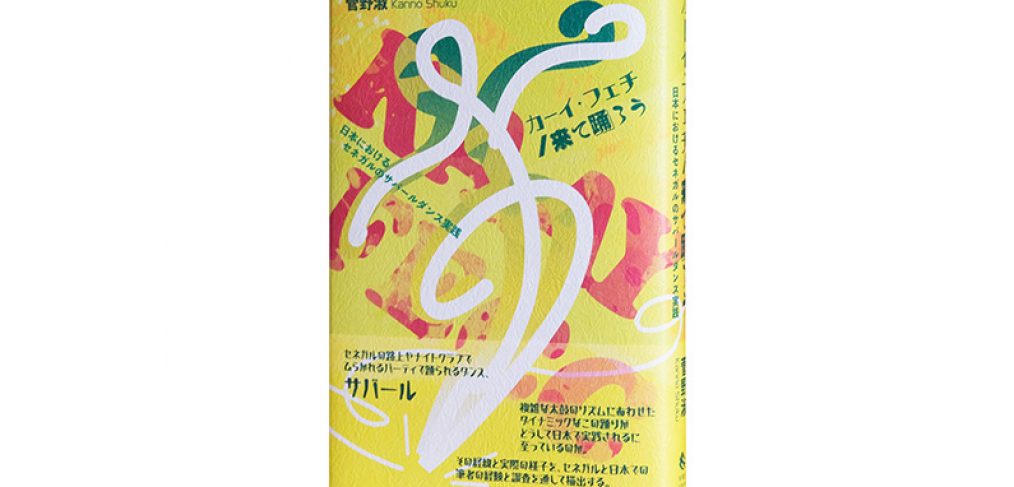歴史が生みだす紛争、紛争が生みだす歴史
現代アフリカにおける暴力と和解
- 佐川徹、竹沢尚一郎、松本尚之(編)/2024年3月
- 3600円(本体)/A5判上製292頁
- 装丁:長田年伸
凄惨な暴力の経緯とその後の課題。
アフリカにおけるさまざまな紛争や暴力の論理と動態を、「無秩序」や「野蛮さ」のイメージから距離を置きつつ、その政治経済・歴史的側面に注目しながら解き明かす。
(ISBN 9784861109539)
目次|contents
序章 歴史が生みだす紛争、紛争が生みだす歴史(竹沢尚一郎、松本尚之、佐川徹)
Ⅰ 国際関係のなかの紛争の機制
第1章 フランスの「かくも惨めな失敗」―マリにおける紛争と混乱の歴史的背景(竹沢尚一郎)
第2章 模倣すべき「過去」―南アフリカ・ナタール植民地における武装蜂起と人種隔離政策の形成(上林朋広)
第3章 誰が好戦的なのか―ウガンダにおける治安部隊編成の歴史と民族をめぐる言説(山崎暢子)
Ⅱ 暴力のモラリティと歴史経験
第4章 いびつなレプリカとしての「報復」―南スーダン、ヌエル社会における紛争と殺人をめぐる概念の歴史的変遷(橋本栄莉)
第5章 内と外の境界を越えて―ウガンダ北部紛争後の和解と加害行為の位置づけ(川口博子)
Ⅲ 紛争をめぐる記憶の配置
第6章 ビアフラ戦争とハム仮説―イボ人たちの「さまよえるユダヤ人」としての運命(松本尚之)
第7章 沈黙の領有、それに抗する慟哭―ルワンダの「歴史」を取り戻す彼女たちの倫理的交渉(近藤有希子)
あとがき
執筆者紹介
編者|editors
佐川徹(さがわ・とおる)
慶應義塾大学文学部准教授
専攻はアフリカ地域研究、文化人類学
主な著作に『負債と信用の人類学:人間経済の現在』(分担執筆、以文社、2023年)、『ようこそアフリカ世界へ』(分担執筆、昭和堂、2022年)、『「戦争と社会」という問い』(分担執筆、岩波書店、2021年)など。
竹沢尚一郎(たけざわ・しょういちろう)
国立民族学博物館・名誉教授
専攻はアフリカ史、宗教人類学
主な著作に『ホモ・サピエンスの宗教史:宗教は人類になにをもたらしたのか』(中央公論新社、2023年)、『原発事故避難者はどう生きてきたか:被傷性の人類学』(東信堂、2022年)、『文化人類学のエッセンス:世界をみる/変える』(共編著、有斐閣、2021年)など。
松本尚之(まつもと・ひさし)
横浜国立大学都市イノベーション研究院教授
専攻は文化人類学、アフリカ地域研究
主な著作に『モビリティの社会学』(分担執筆、有斐閣、近刊)、『アフリカ潜在力のカレイドスコープ』(分担執筆、晃洋書房、2022年)、『アフリカで学ぶ文化人類学:民族誌がひらく世界』(共編著、昭和堂、2019年)など。