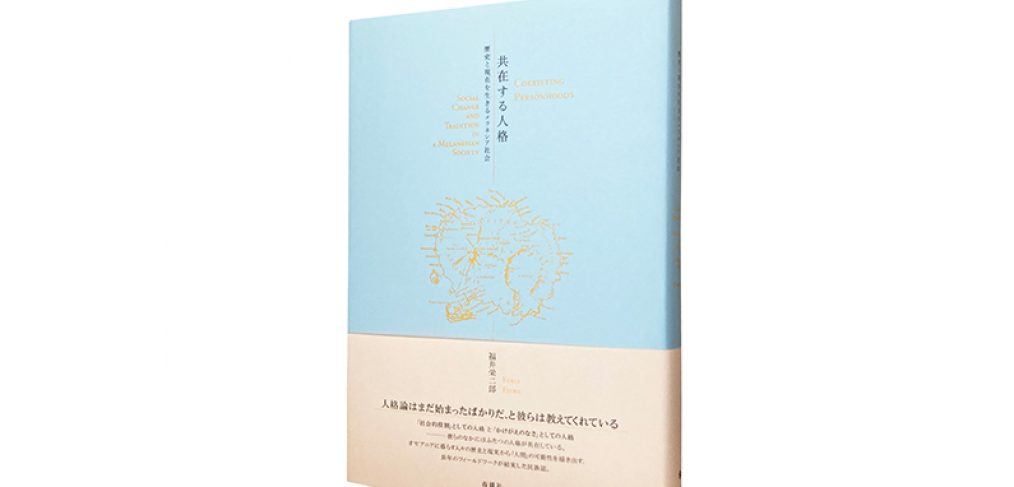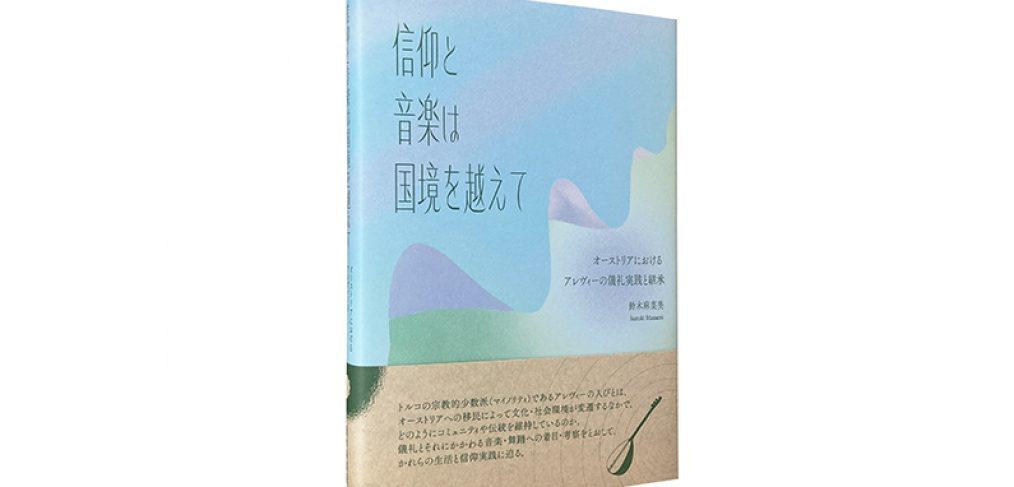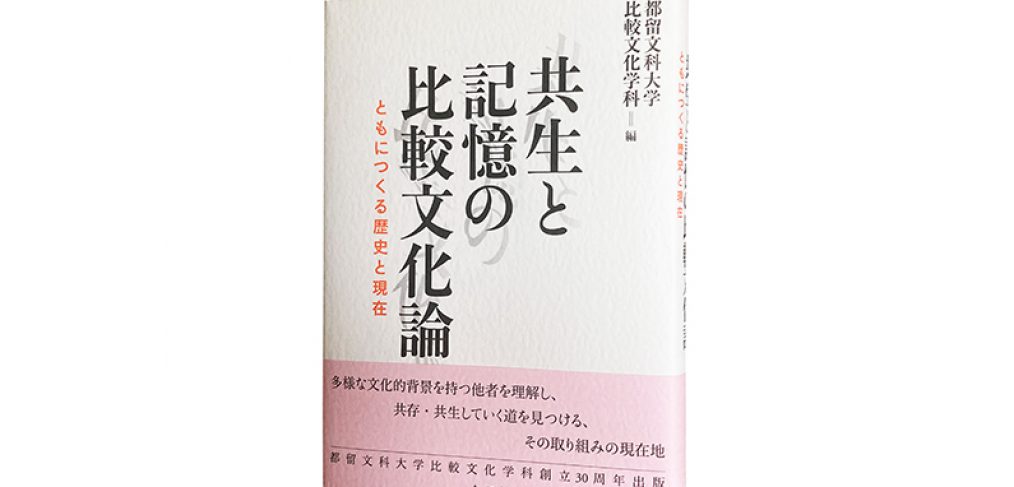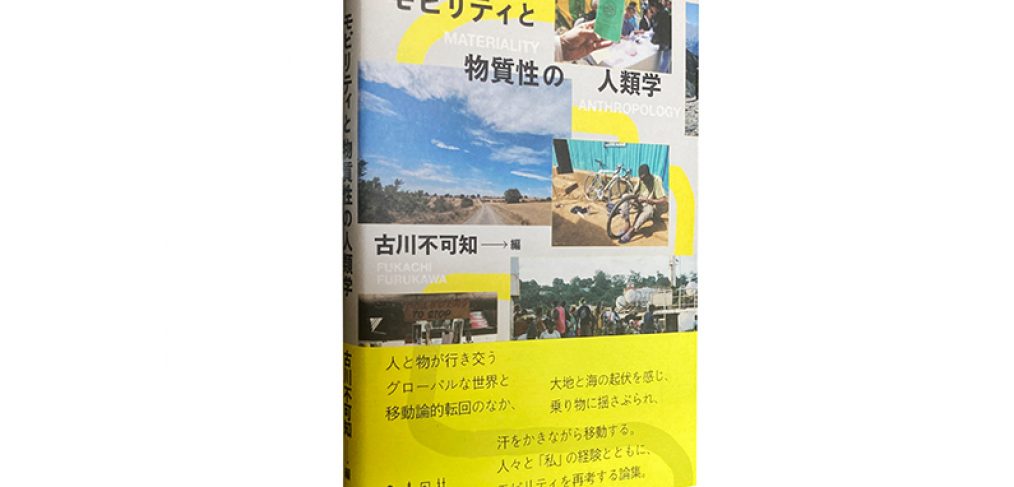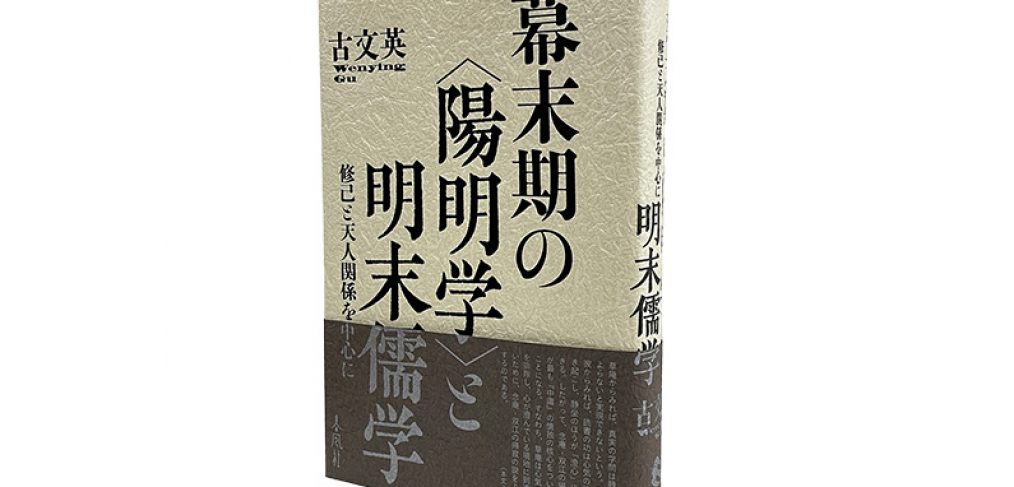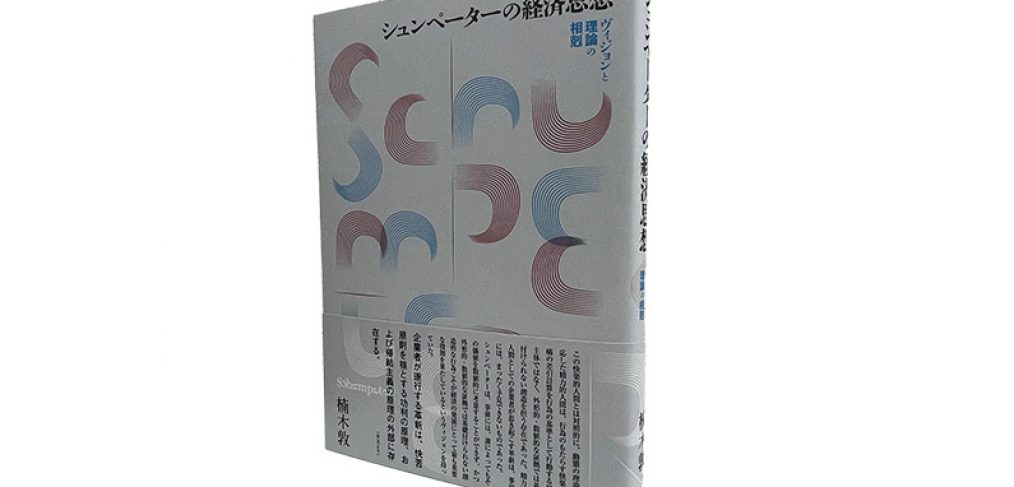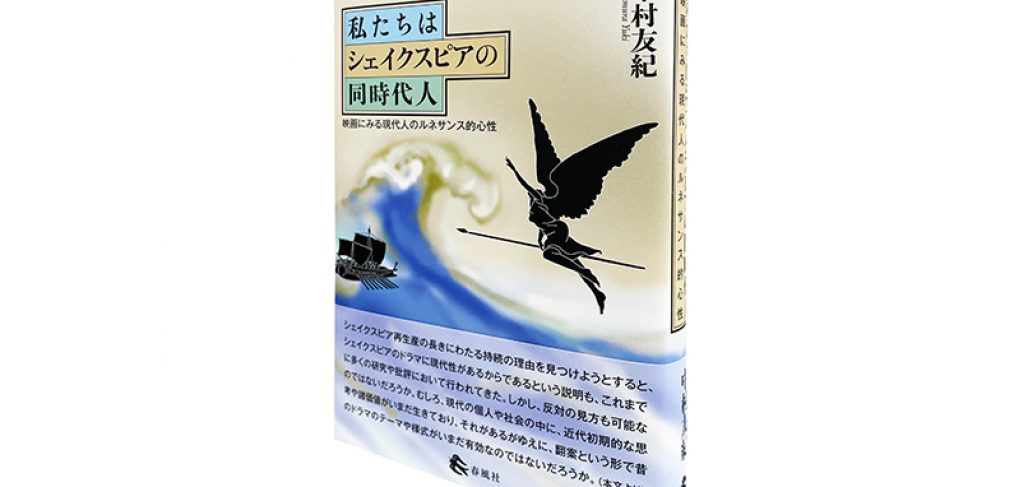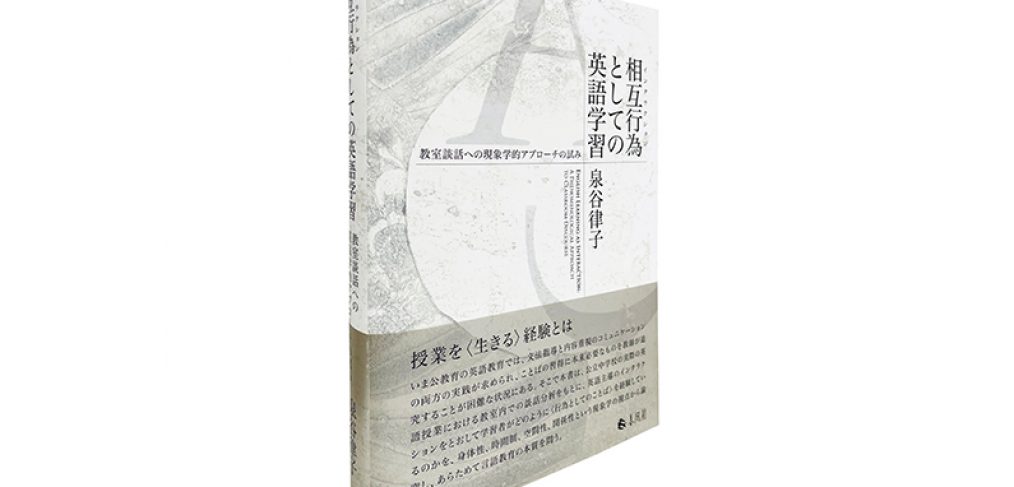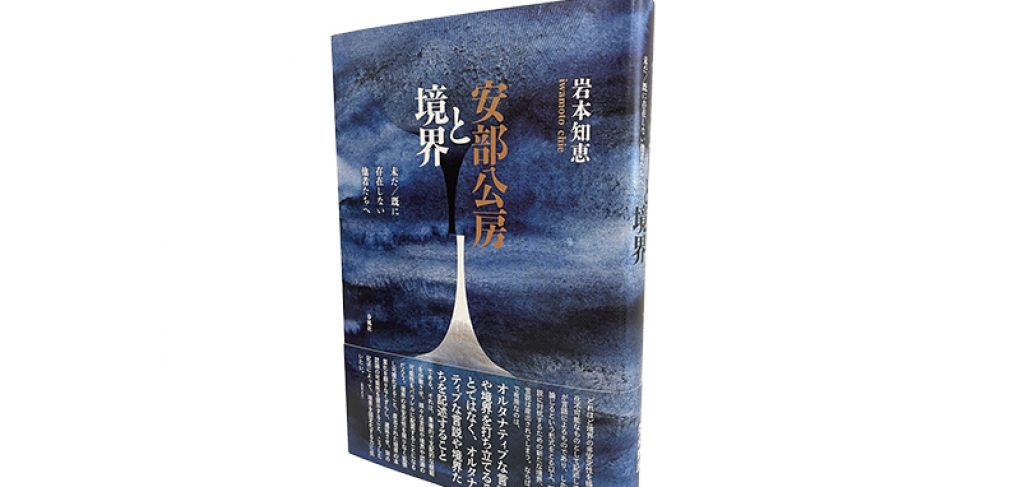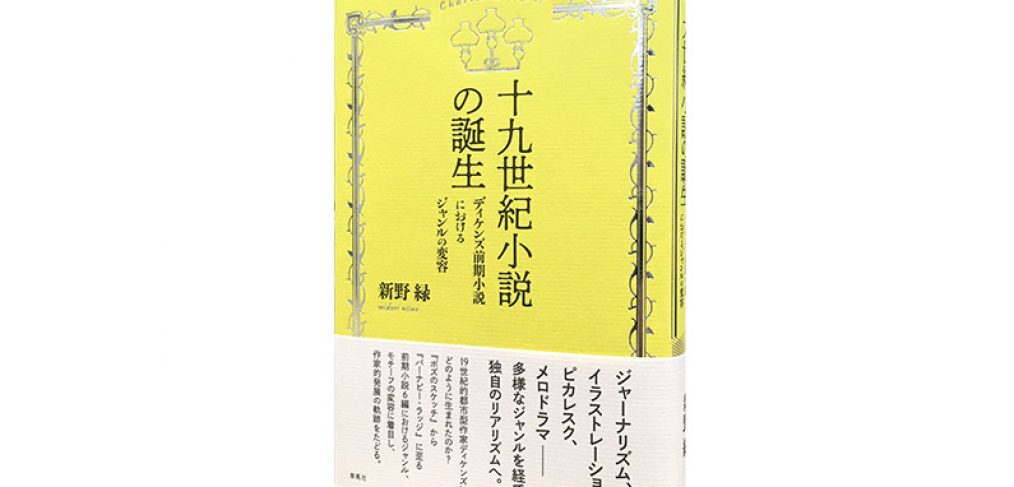共在する人格
歴史と現在を生きるメラネシア社会
- 福井栄二郎(著)/2024年3月
- 5000円(本体)/A5判上製374頁
- 装丁:大田高充
人格論はまだ始まったばかりだ、と彼らは教えてくれている
「社会的役割」としての人格と「かけがえのなさ」としての人格――彼らのなかにはふたつの人格が共在している。オセアニアに暮らす人々の歴史と現実から「人間」の可能性を描き出す、長年のフィールドワークが結実した民族誌。
本書の舞台となるのは太平洋に浮かぶ小島、ヴァヌアツのアネイチュム島である。19世紀以降、西洋からの強大な力がこの島を飲みこむ。伝統は大きく変容し、その傷跡は現在も残されている。そのなかで彼らの「人格」は、いかに変容し、持続したのか。
本書の「はじめに」を公開しています → はじめに(pdfファイル)
(ISBN 9784861109089)
目次|contents
Ⅰ 人格
第1章 文化人類学における「人格」
第2章 ヴァヌアツ・アネイチュム島
Ⅱ 歴史
第3章 一八四八
第4章 村落の誕生
Ⅲ カストム
第5章 持続と断絶―土地と名前の結びつき
第6章 恥辱と歴史認識―カストムの真正性
第7章 譲渡できないものを贈与する―名前の贈与と公共圏
Ⅳ かけがえのなさ
第8章 名の示すもの―ふたつの人格、ふたつの歴史
第9章 人格の手前にあるもの
第10章 死と状況的人格
第11章 共在する人格
あとがき
参照文献
索引
著者|author
福井栄二郎(ふくい・えいじろう)
島根大学法文学部・准教授
社会人類学・オセアニア研究
主な著作に、『交錯と共生の人類学:オセアニアにおけるマイノリティと主流社会』(共著、風間計博編、ナカニシヤ出版、2017年)、『多配列思考の人類学:差異と類似を読み解く』(共著、白川千尋・石森大知・久保忠行編、風響社、2016年)、「From Kastom to Developing Livelihood: Cruise Tourism and Social Change in Aneityum, Southern Vanuatu」(『People and Culture in Oceania』35、2020年)などがある。
この本を注文する
Amazonで注文する Hontoで注文する 楽天ブックスで注文する