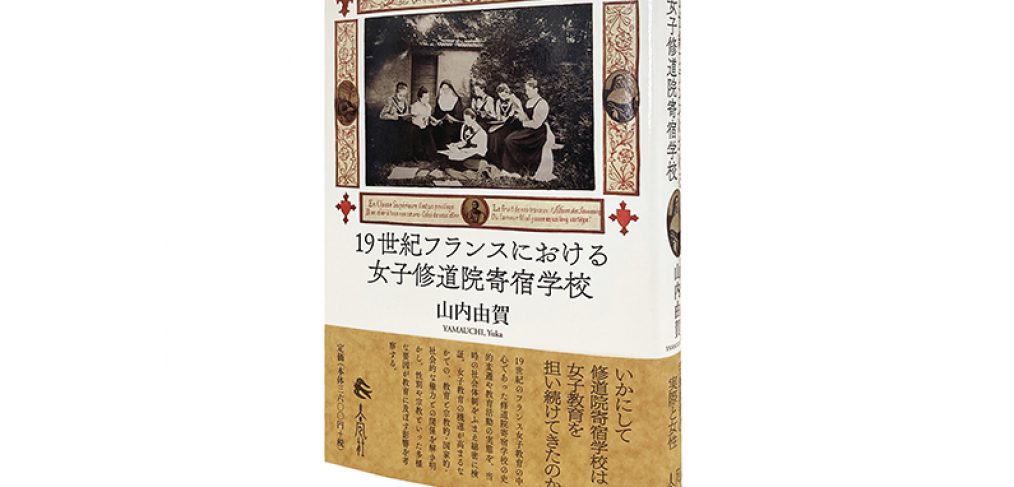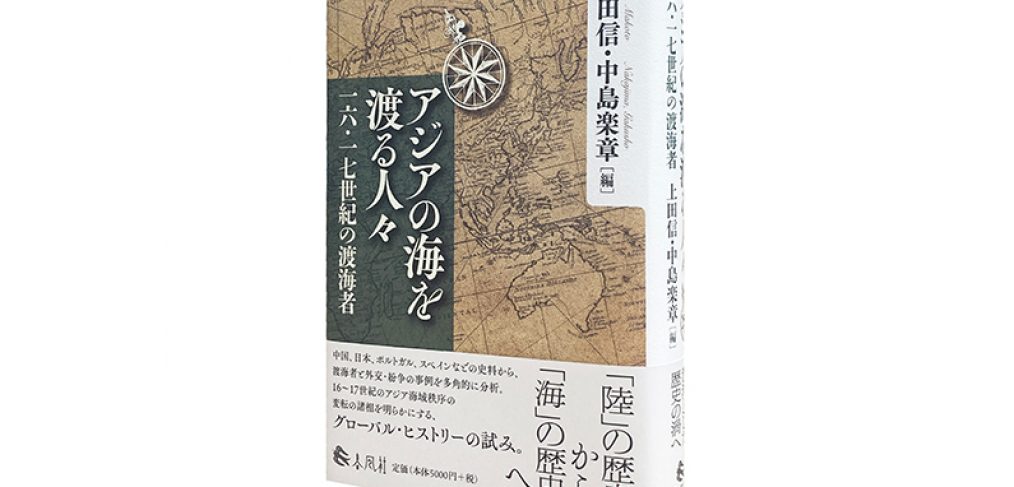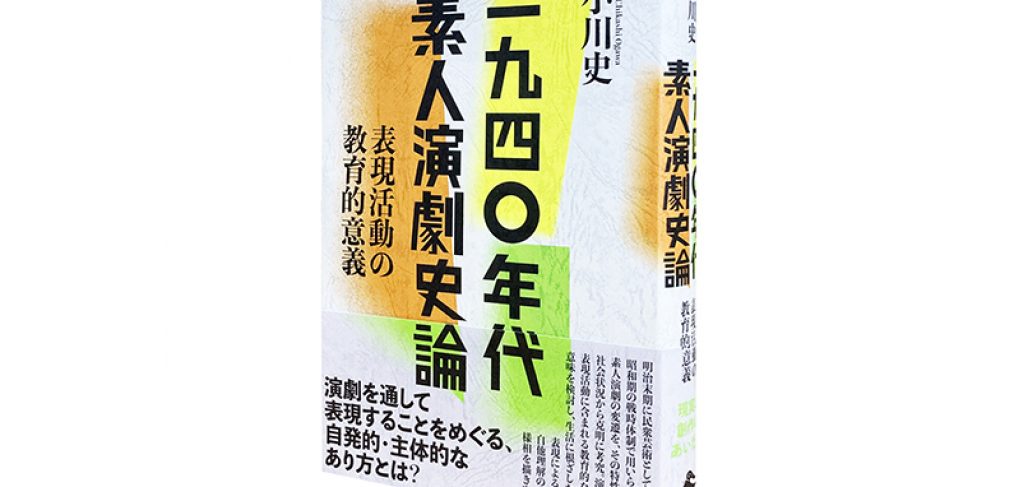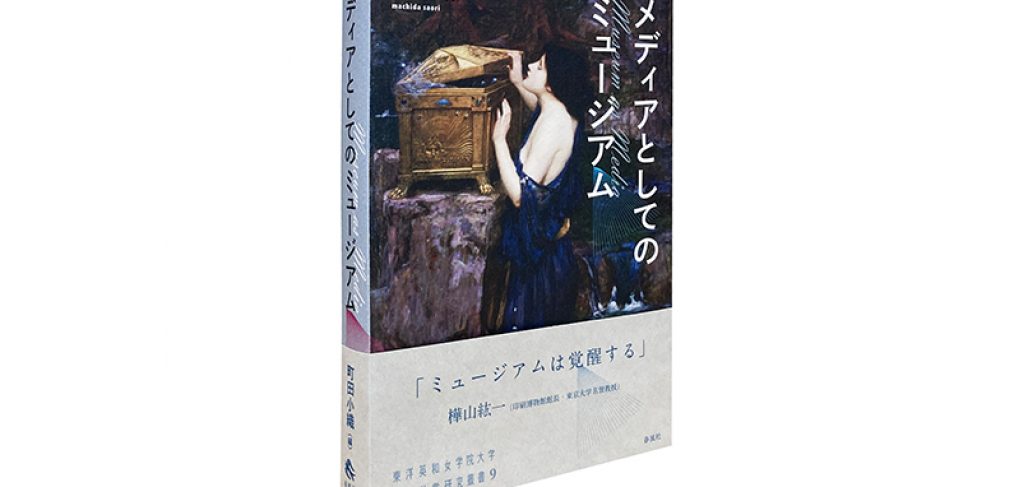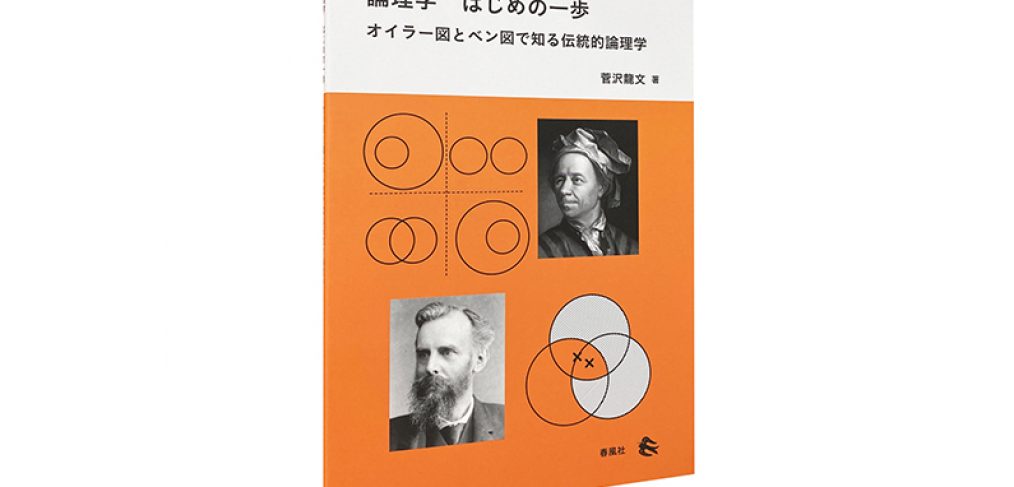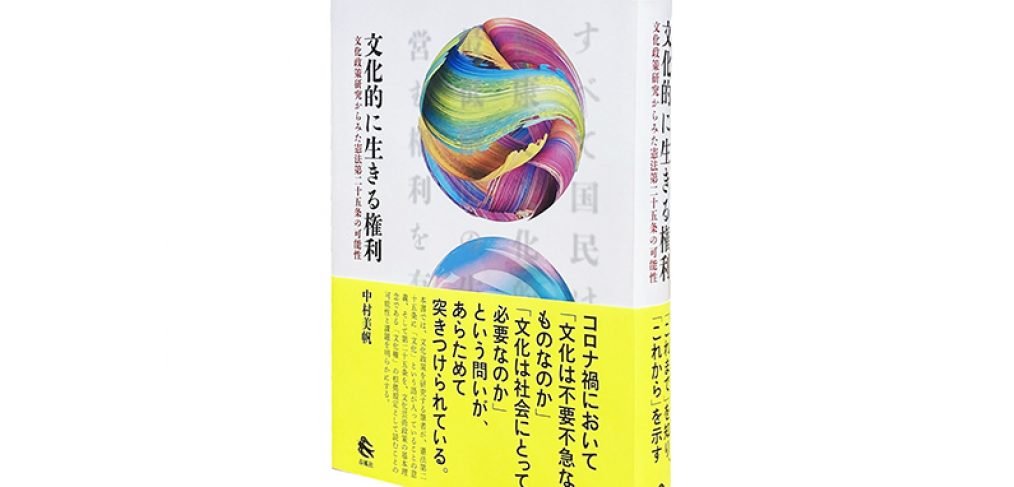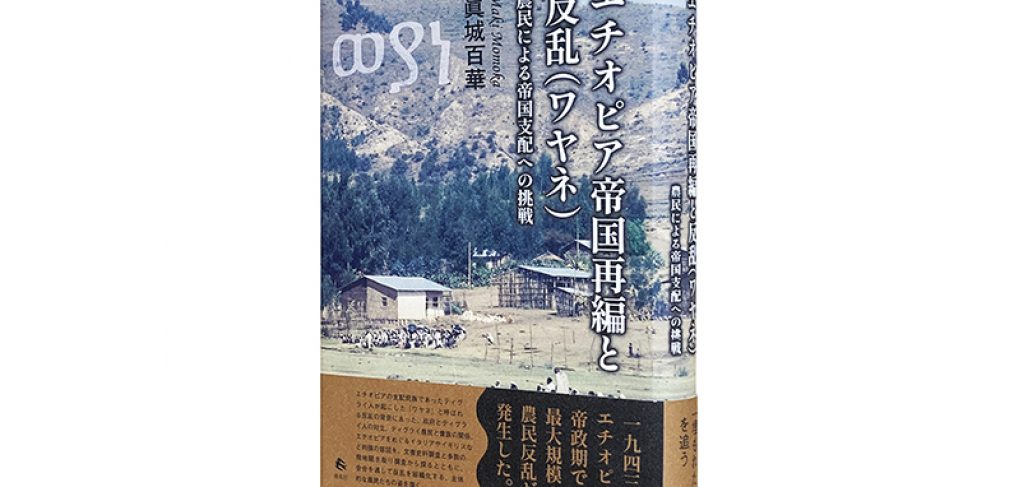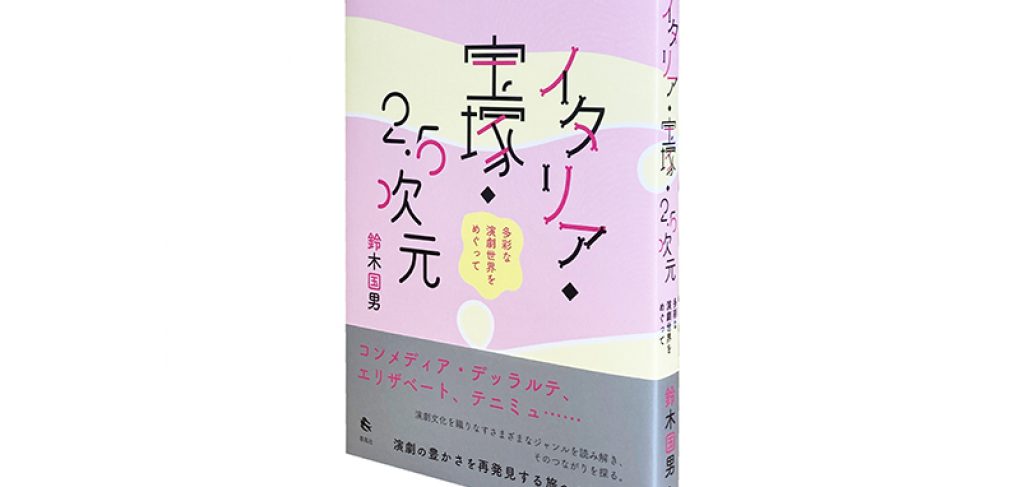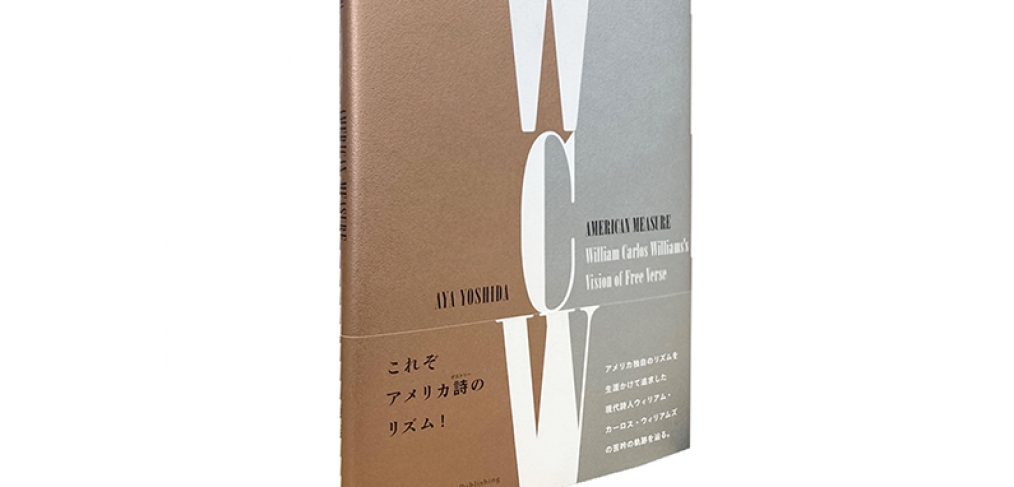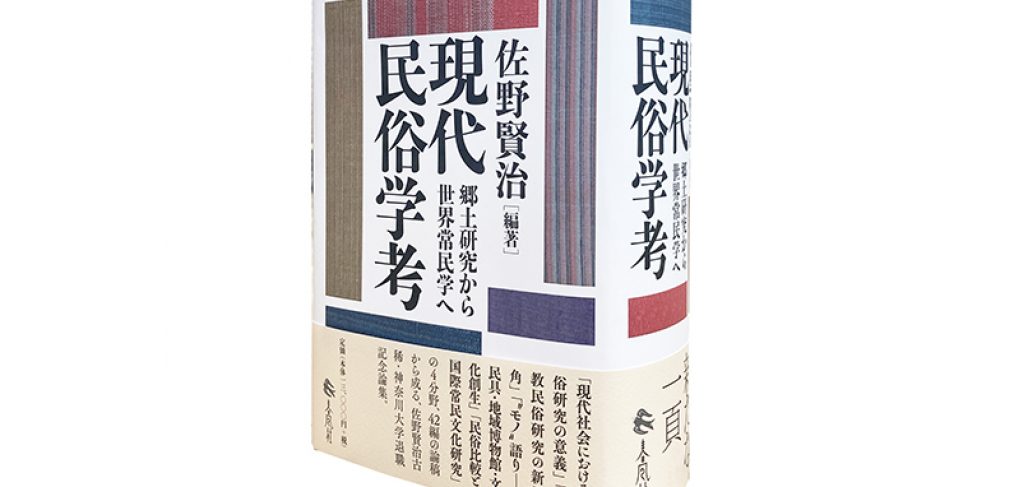19世紀フランスにおける女子修道院寄宿学校
- 山内由賀(著)/2021年3月
- 3600円(本体)/四六判上製256頁
- 装丁:桂川潤
いかにして修道院寄宿学校は女子教育を担い続けてきたのか――
19世紀のフランス女子教育の中心であった修道院寄宿学校の史的変遷や教育活動の実態を、当時の社会体制をふまえ綿密に検証。女子教育の機運が高まるなかでの、教育と宗教的・国家的・社会的な権力との関係を解き明かし、性別や宗教といった多様な要因が教育に及ぼす影響を考察する。
(ISBN 9784861107351)
目次|contents
はしがき
序章 女子修道院寄宿学校を問うということ
第1節 問題の所在
第2節 研究の手法と構成
第1章 修道院寄宿学校の始まりから隆盛まで
第1節 修道院寄宿学校の始まり
第2節 フランス革命による修道院寄宿学校の閉鎖
第3節 世俗寄宿学校の登場と女子教育論
第4節 修道院寄宿学校に対する社会的認識
第2章 修道院寄宿学校の教育
第1節 寄宿生活
第2節 修道院寄宿学校における授業
第3節 「競争」と「褒賞」の活用
第4節 「針仕事」の二つの側面
第3章 女性と宗教教育
第1節 修道院寄宿学校における宗教教育
第2節 修道院寄宿学校で学んだ娘たち
第3節 女子教育における宗教教育の役割
第4節 カトリック教会にとっての女子教育
第4章 非宗教の女子教育をめざして
第1節 皇后ウジェニーと教育への関心
第2節 公教育大臣による修道院寄宿学校調査
第3節 女子中等教育講座の開講
第4節 女子医学校設立計画
第5章 修道院寄宿学校と女子リセ・コレージュ
第1節 第三共和政の成立と反教権主義政策
第2節 女子中等教育法の成立
第3節 女子リセ・コレージュの設立
第4節 対抗する修道院寄宿学校
終章 女子修道院寄宿学校とは何であったのか
第1節 一九世紀フランスにおける修道院寄宿学校の盛衰
第2節 宗教的な女子教育から非宗教的な女子教育へ
第3節 二〇世紀以降の修道院寄宿学校と男女教育の同格化
あとがき
引用文献および主要参考文献
索引
著者|author
山内由賀(やまうち・ゆか)
1986年兵庫県生まれ。聖心女子大学卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程研究指導認定退学、博士(人間・環境学)。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、現在は立命館大学、神戸女子大学非常勤講師。専門はフランス女子教育史、ジェンダーと教育。主な業績に「フランス第二帝政期における修道院寄宿学校の復興」『比較文化研究』No.110(2012年)、「19世紀フランスの女子教育における「針仕事」の変遷」『比較文化のまなざし』(2014年)、「フランス第二帝政期の修道院寄宿学校における「競争」と「褒賞」そして「罰則」――男子教育との比較を通して」『女性学年報』第38号(2017年)など。