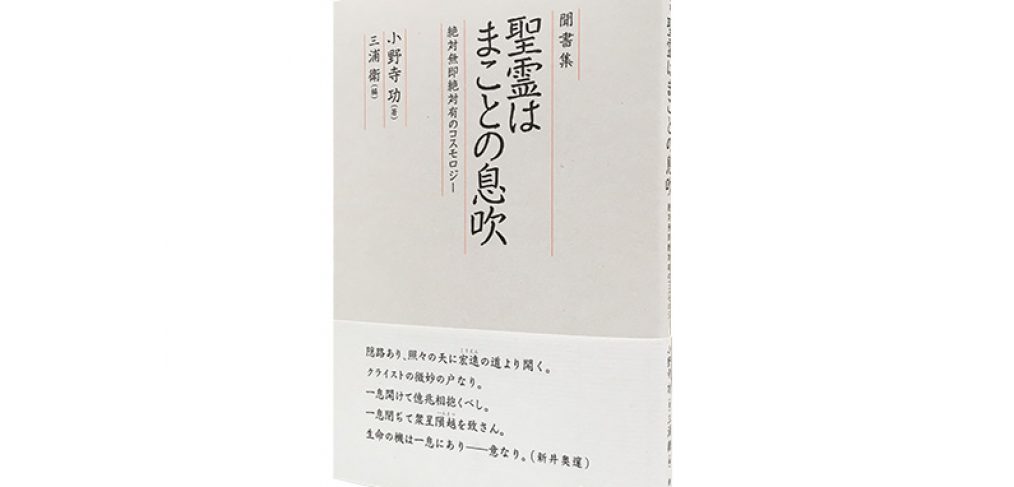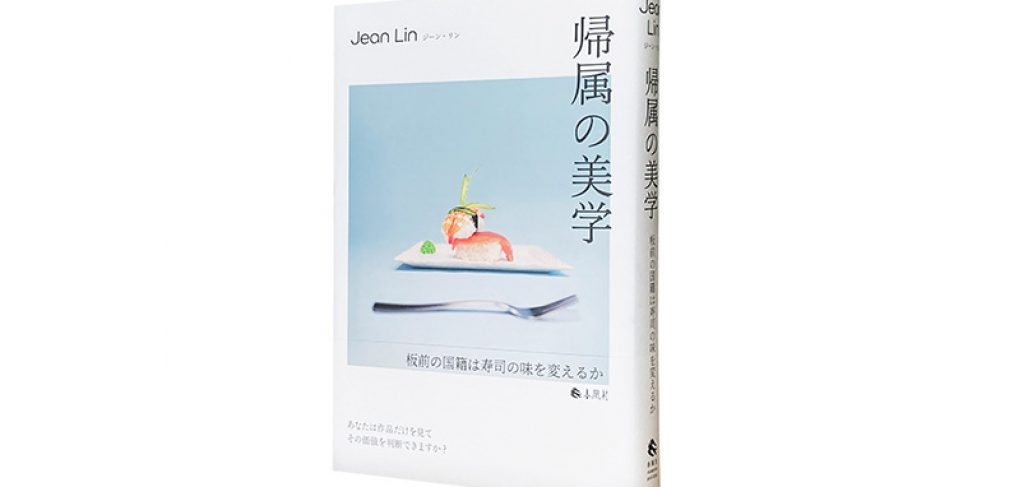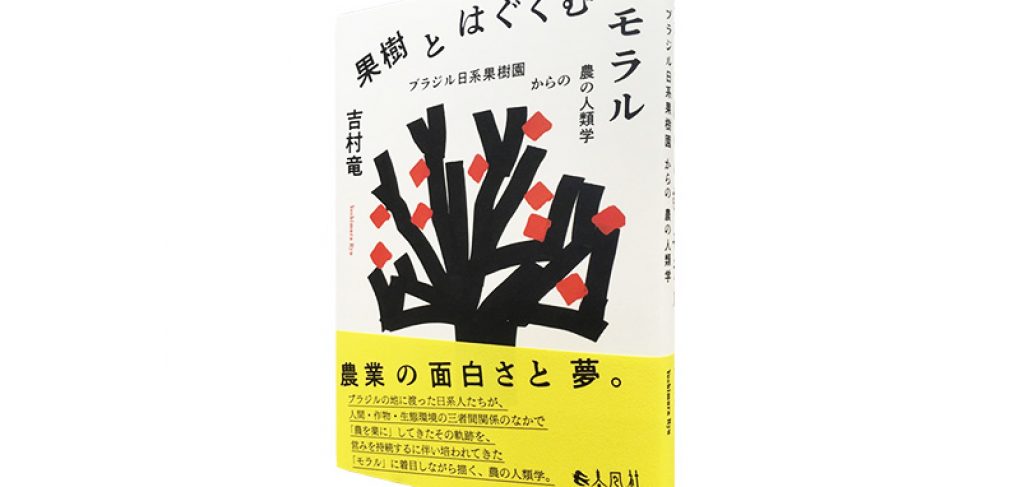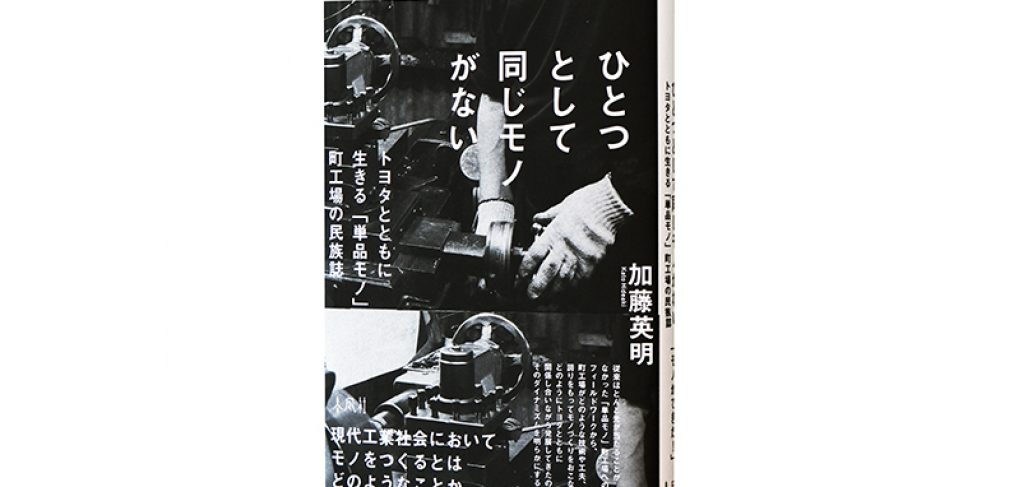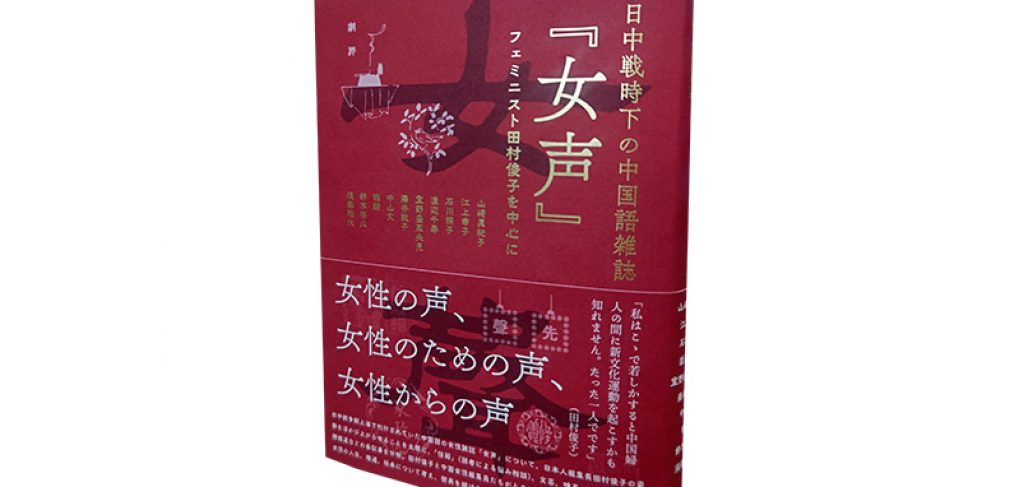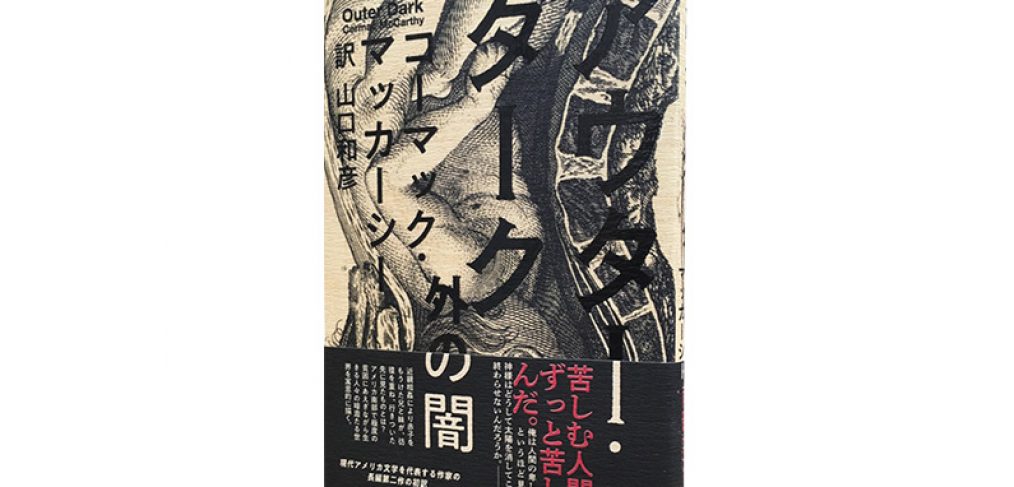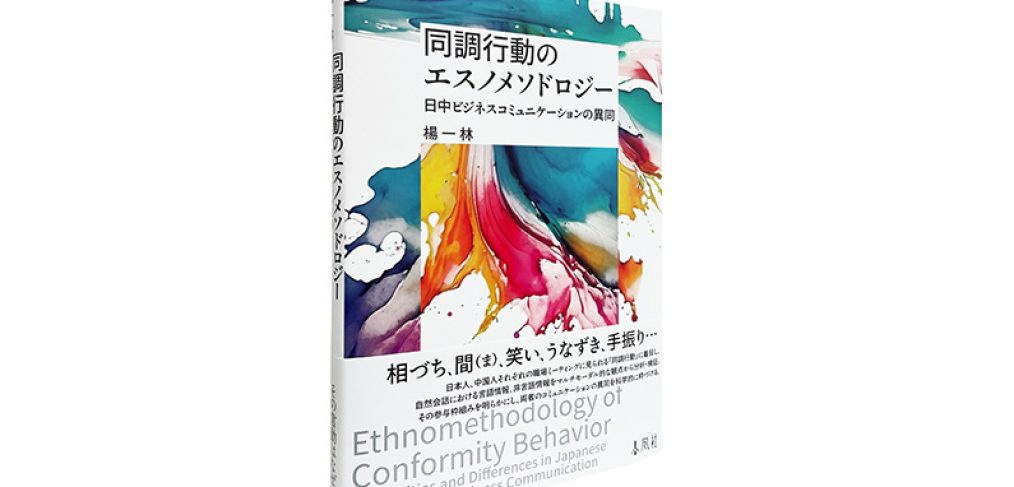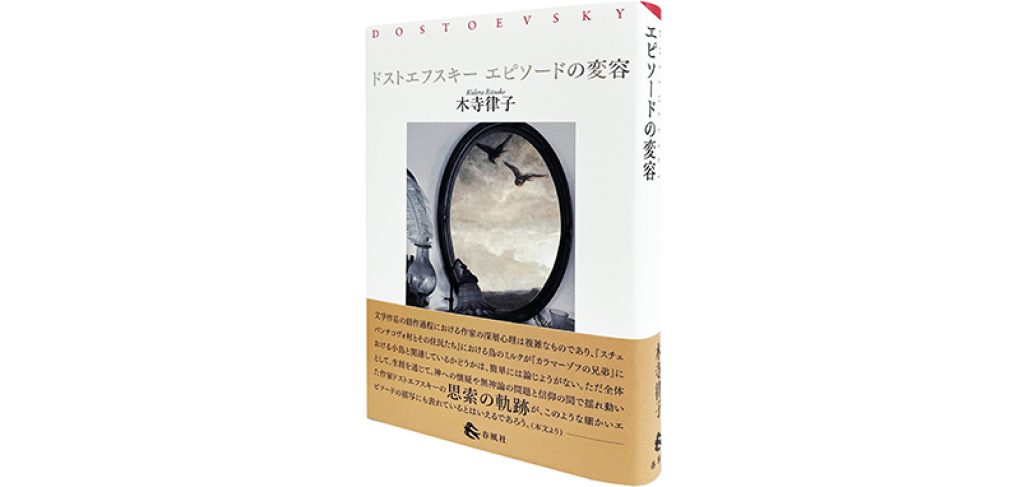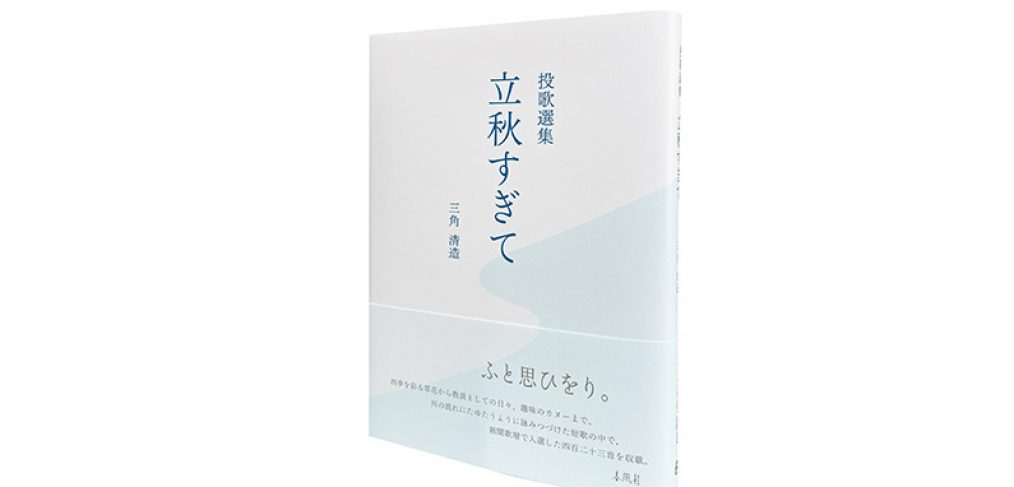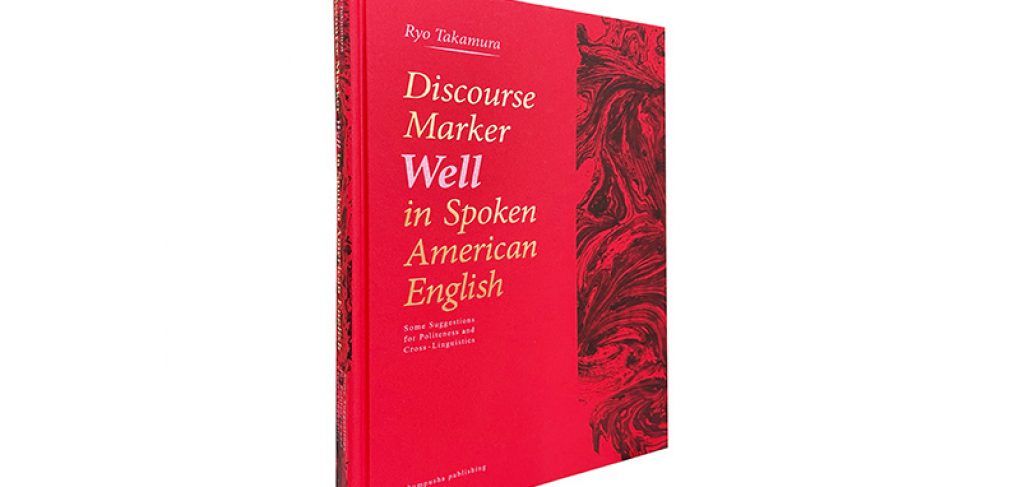日中戦時下の中国語雑誌『女声』
フェミニスト田村俊子を中心に
- 山﨑眞紀子、江上幸子、石川照子、渡辺千尋、宜野座菜央見、藤井敦子、中山文、姚毅、鈴木将久、須藤瑞代(著)/2023年12月
- 4500円(本体)/A5判上製408頁
- 装丁:中本那由子
日中戦争期上海で刊行されていた中国語の女性雑誌『女声』について、日本人編集長田村俊子の姿勢を浮かび上がらせることを主眼に、「信箱」(読者による悩み相談)、文芸、映画、演劇、児童、国際報道などの各記事を分析。田村俊子と中国女性編集員たちがときに価値観の相違を見せながらも、女性の人生、境遇、将来について考え、発表を続けた諸相を多角的に考察する。
(ISBN 9784861109164)
目次|contents
はじめに
Ⅰ 総論
第1章 田村俊子と『女声』 山﨑眞紀子
第2章 関露の『女声』への参加とその後 江上幸子
「東京寄語」「東京憶語(精神病状態の日々)」関露(須藤瑞代訳)
第3章 アジア・太平洋戦争期の上海政治空間と国際関係―『女声』の性格を探る手がかりとして 石川照子
Ⅱ 『女声』の戦略性
第4章 プロパガンダの「責任者」としての編集長・田村俊子―時事評論欄「国際新聞」「新聞網」「瞭望台」の検討から 渡辺千尋
第5章 『女声』の映画スペース―日本に対する同調・忌避・〝好意〟 宜野座菜央見
第6章 『女声』における「先声」と「余声」の意義 藤井敦子
Ⅲ 関露と『女声』
第7章 『女声』誌上のジェンダー論―関露を中心に 江上幸子
長編小説『黎明』第三章 関露(石井洋美訳 江上幸子解説)
第8章 『女声』劇評にみるジェンダー観―関露の見た海派話劇 中山文
Ⅳ 田村俊子と『女声』
第9章 『女声』における「児童」ならびに豊島与志雄の童話 姚毅
第10章 陶晶孫と田村俊子、そして『女声』 鈴木将久
「日本からアメリカ、そして中国へ―追悼・佐藤女史」陶晶孫(藤井敦子訳)
第11章 『女声』における日本女性の存在と不在 須藤瑞代
第12章 田村俊子主宰「信箱」―戦時下における私的言語の空間 山﨑眞紀子
おわりに
参考文献一覧
『女声』総目録
主要執筆者のペンネームと執筆記事一覧
索引
著者|author
山﨑眞紀子(やまさき・まきこ)
日本大学スポーツ科学部教授、日本大学大学院総合社会情報研究科教授。日本近現代文学。
主な著作に、『田村俊子の世界―作品と言説空間の変容』(彩流社、2005年)、「青島―翻訳都市、須賀敦子の青島」『中国の都市の歴史的記憶』(共著、勉誠出版、2022年)など。
江上幸子(えがみ・さちこ)
フェリス女学院大学名誉教授。中国近現代文学・女性史。
主な著作に『探索丁玲』(共著、台湾:人間出版社、2017年)、『中国の娯楽とジェンダー―女が変える/女が変わる』(共著、勉誠出版、2022年)など。
須藤瑞代(すどう・みずよ)
京都産業大学准教授。近代中国ジェンダー史研究。
主な著作に、『中国「女権」概念の変容―清末民初の人権とジェンダー』(研文出版、2007年)、『女性記者・竹中繁のつないだ近代中国と日本―一九二六〜二七年の中国旅行日記を中心に』(共著、研文出版、2018年)など。
石川照子(いしかわ・てるこ)
大妻女子大学比較文化学部教授。中国近現代史(女性史、ジェンダー、キリスト教)。
主な著作に、『戦時上海のメディア―文化的ポリティクスの視座から』(共編著、研文出版、2016年)、『女性記者・竹中繁のつないだ近代中国と日本― 一九二六~二七年の中国旅行日記を中心に』(共著、研文出版、2018年)など。
渡辺千尋(わたなべ・ちひろ)
東洋大学経済学部講師。日本近代史、近代日中関係史。
主な著作に、「治外法権撤廃・内地開放論の経済的背景―中国「本部」を中心に」(『東アジア近代史』第24号、2020年6月)、「日清戦争後の対清経済政策と居留地経営」(『交通史研究』第94号、2019年3月)など。
宜野座菜央見(ぎのざ・なおみ)
明治大学文学部兼任講師。日本史・映像文化史。
主な著作に、宜野座菜央見『モダン・ライフと戦争―スクリーンのなかの女性たち』(吉川弘文館、2013年)など。
藤井敦子(ふじい・あつこ)
立命館大学客員協力研究員・立命館大学非常勤講師・関西外国語大学非常勤講師。中国近現代史・中国女性史・中国近現代文学。
主な著作に、『女性記者・竹中繁のつないだ近代中国と日本―一九二六~二七年の中国旅行日記を中心に』(共著、研文出版、2018年)、『わたしの青春、台湾』(共訳、五月書房新社、2020年)など。
石井洋美(いしい・ひろみ)
横浜国立大学等非常勤講師。中国現代文学。
主な著作に、「葉霊鳳が描いた男女に見られる「椿姫」の影響―1932年以降の作品を中心に」『文学の力、語りの挑戦』(共著、東方書店、2021年)、「葉霊鳳の短編小説「麗麗斯」解釈の可能性―アナトール・フランス「リリトの娘」との類似性と相違点について」(『人間文化創成科学論叢』第22巻、2020年)など。
中山文(なかやま・ふみ)
神戸学院大学人文学部教授。中国演劇、ジェンダー学。
主な著作に、『新版 越劇の世界―中国の女性演劇』(共編著、エヌ・ケー・ステーション、2019年)、「姉妹の越劇―姚水娟・袁雪芬・尹桂芳の時代」『中国の娯楽とジェンダー―女が変える/女が変わる』(共著、勉誠出版、2022年)など。
姚毅(よう・き)
大阪公立大学客員研究員。中国女性史。
主な著作に、『近代中国の出産と国家・社会―医師・助産士・接生婆』(研文出版、2011年)など。
鈴木将久(すずき・まさひさ)
東京大学大学院人文社会系研究科教授。中国近現代文学。
主な著作に、『上海モダニズム』(中国文庫、2012年)、『思想史の中の日本と中国』(翻訳、孫歌著、東京大学出版会、2020年)など。
この本を注文する
Amazonで注文する e-honで注文する 楽天ブックスで注文する