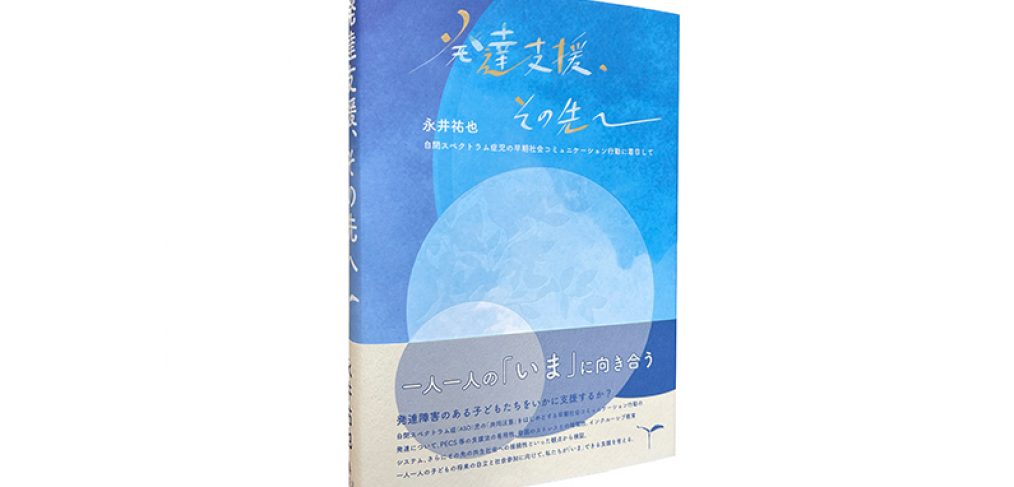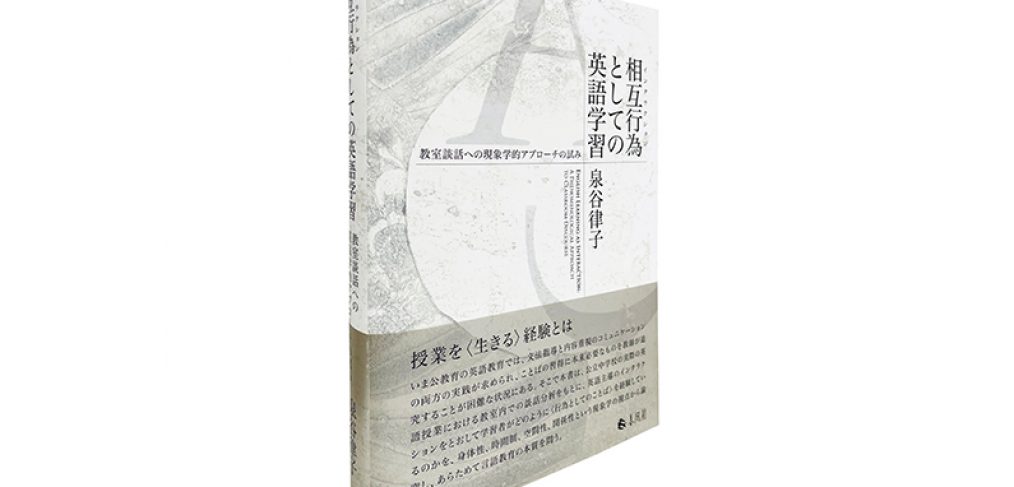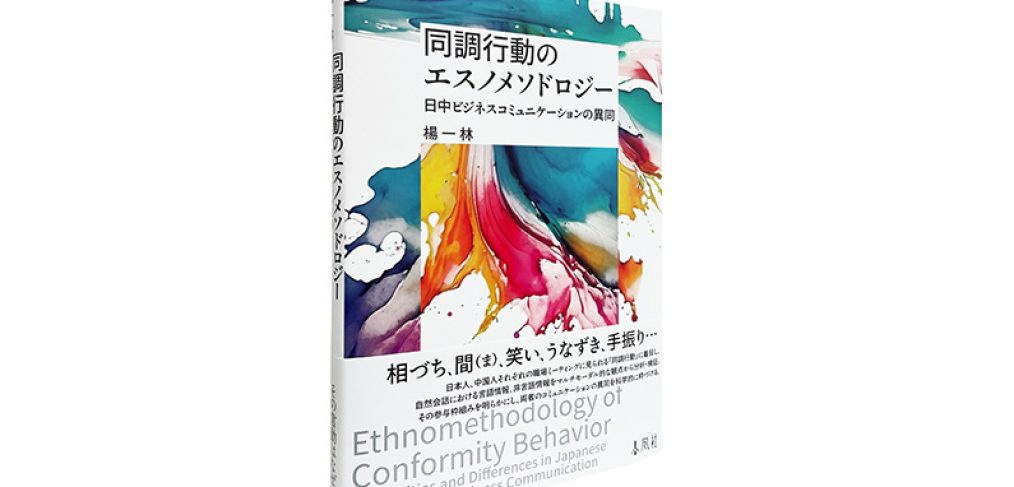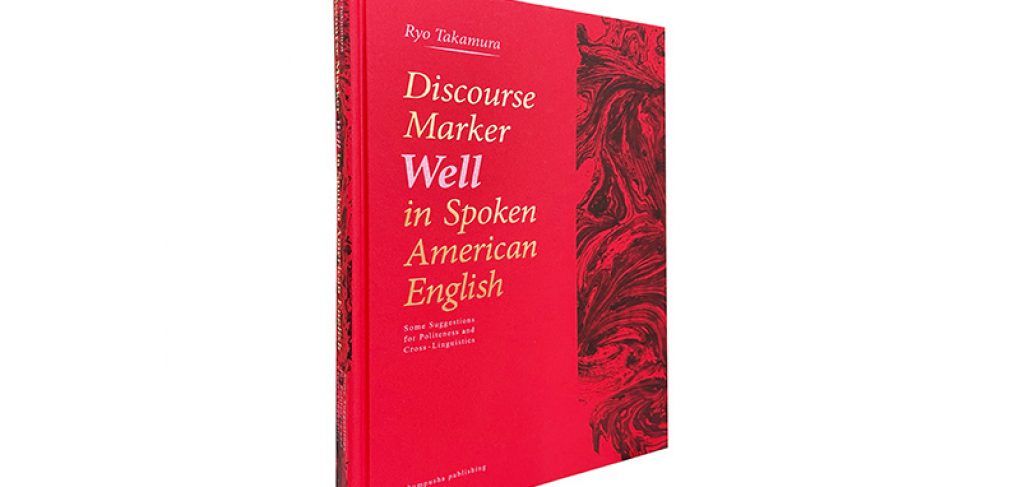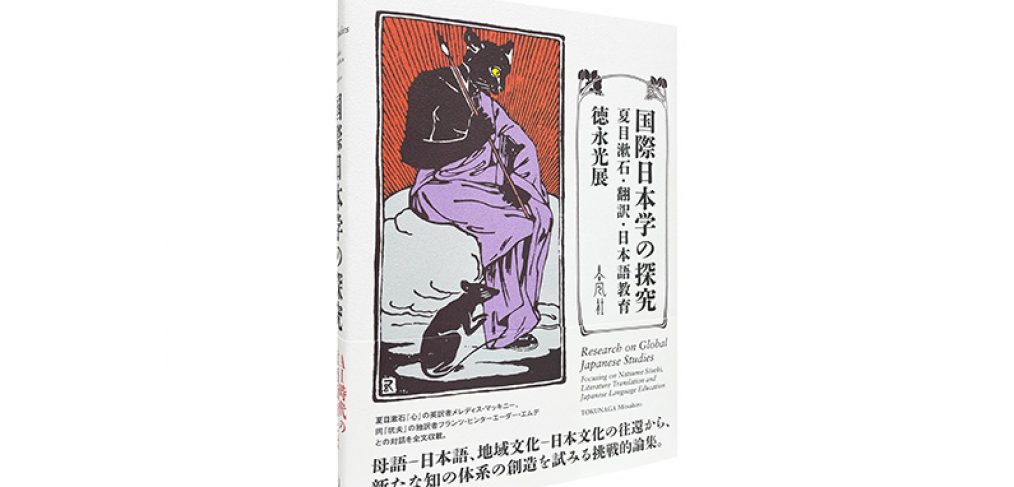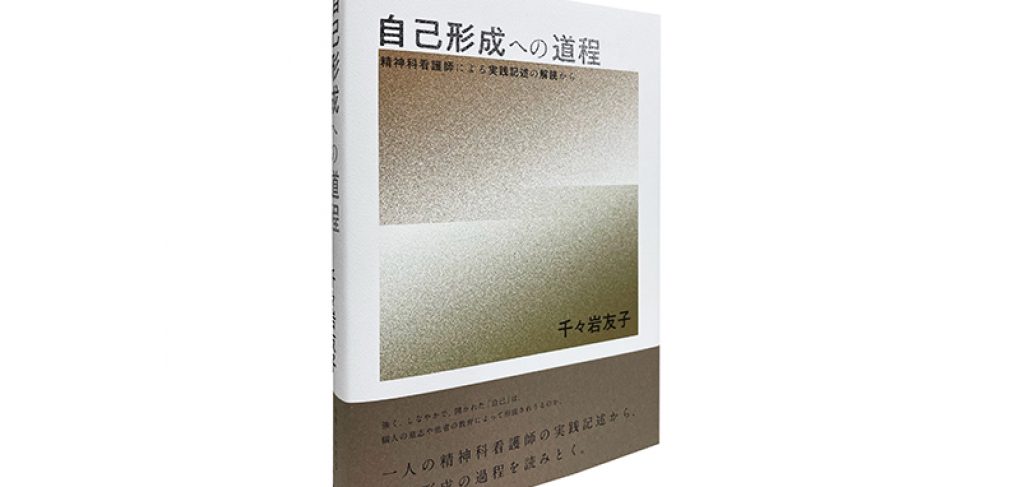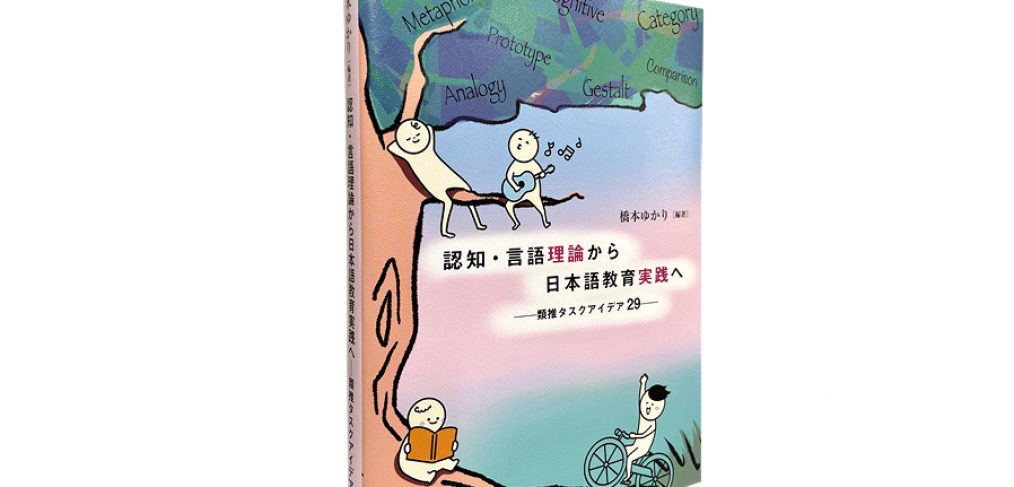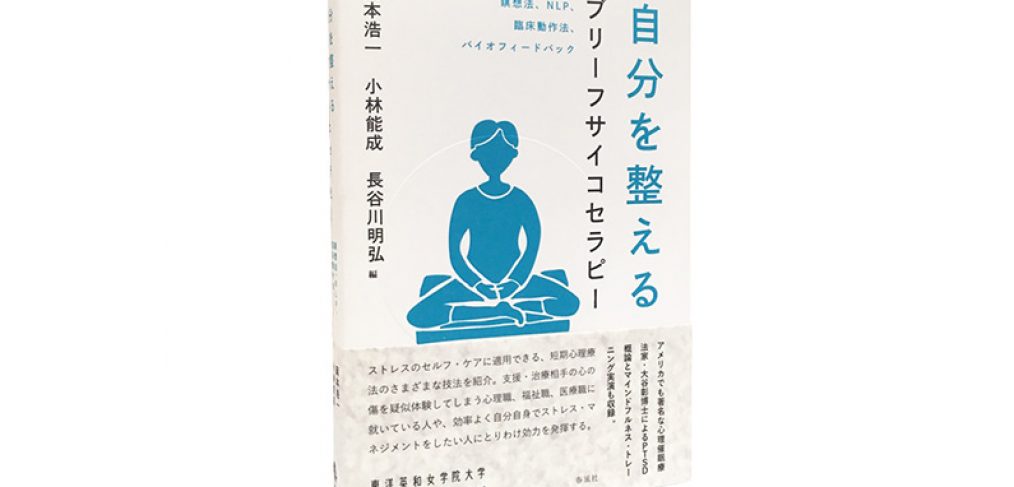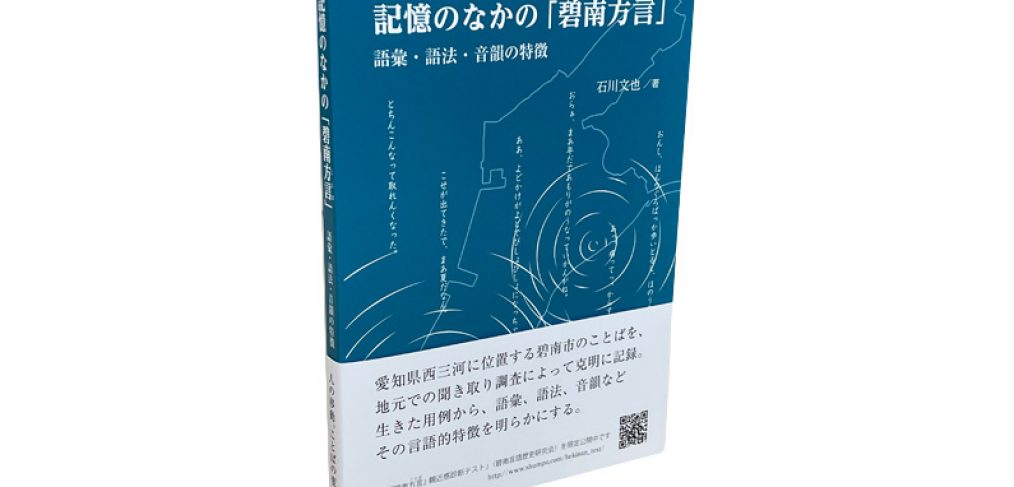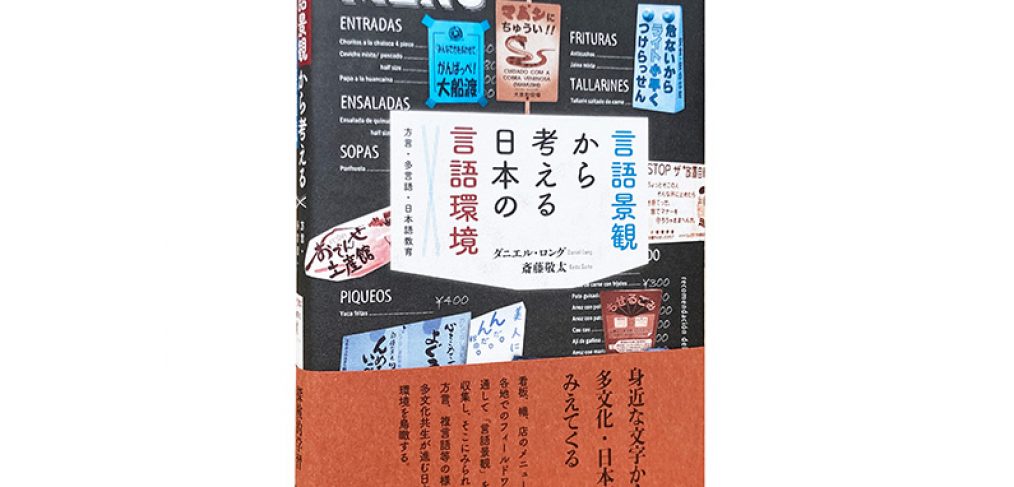発達支援、その先へ
自閉スペクトラム症児の早期社会コミュニケーション行動に着目して
- 永井祐也(著)/2024年4月
- 3900円(本体)/A5判上製276頁
- 装丁:中本那由子
発達障害のある子どもたちをいかに支援するか?
近年、発達障害のある児童生徒にとって、より早い段階における適切な支援が、社会適応や二次障害予防に有効であることが分かってきた。本書ではその一例として、自閉スペクトラム症(ASD)児の「共同注意」をはじめとする早期社会コミュニケーション行動の発達に着目。PECS等の支援法の有用性、母親のストレスとの相関性、インクルーシブ教育システム、さらにその先の共生社会への接続性などの観点から検証し、児の将来の自立と社会参加に向けて、「いま」できる発達支援を考える。
(ISBN 9784861109508)
目次|contents
はじめに
第0章 序論
第1章 日本の特別支援教育・インクルーシブ教育システムの動向
第2章 自閉スペクトラム症(ASD)の理解と発達支援
第3章 アイトラッカーによるASD児の共同注意の測定とその臨床的有用性
第4章 ASD児の早期社会コミュニケーション行動が不適応行動に及ぼす影響
第5章 PECSがASD児の早期社会コミュニケーション行動に及ぼす効果
第6章 母親の育児ストレス軽減に果たすASD児の共同注意の役割
第7章 個別発達支援におけるASD児の母親の育児ストレス軽減効果
第8章 総合考察
あとがき
図表一覧
初出一覧
文献一覧
索引
著者|author
永井祐也(ながい・ゆうや)
岐阜聖徳学園大学教育学部 専任講師
1988年 大阪府生まれ
大阪大学大学院人間科学研究科 修了 (博士(人間科学))
日本学術振興会特別研究員 (DC2)、くらしき作陽大学子ども教育学部専任講師、大阪大学大学院人間科学研究科助教を経て、2022年4月より現職。
主要論文
・標準「病弱児の教育」テキスト【改訂版】(ジアース教育新社, 分担執筆, 2022)
・母親の育児ストレス軽減に果たす自閉スペクトラム症児の共同注意の役割(発達心理学研究, 34(1), 11-18, 2023)
・Effects of the Picture Exchange Communication System on early social-communication behaviors in children with autism spectrum disorders.(Journal of Special Education Research, 10(2), 69-81, 2022)
・小児がん啓発人形劇が小学校教員に復学支援を想像させる効果(小児保健研究, 80(6), 782-787, 2021)
・ムコ多糖症のある幼児児童生徒への教育的支援に関する保護者の認識(特殊教育学研究, 53(3), 175-183, 2015)