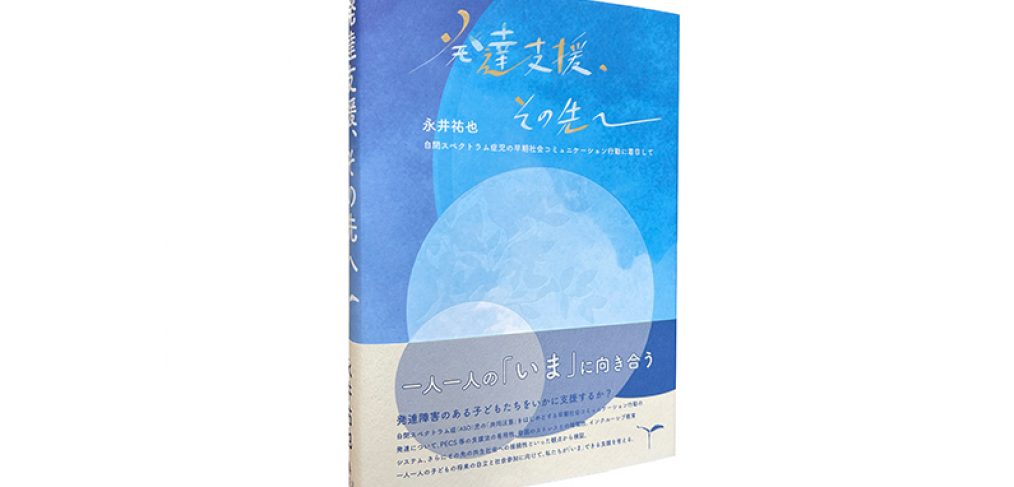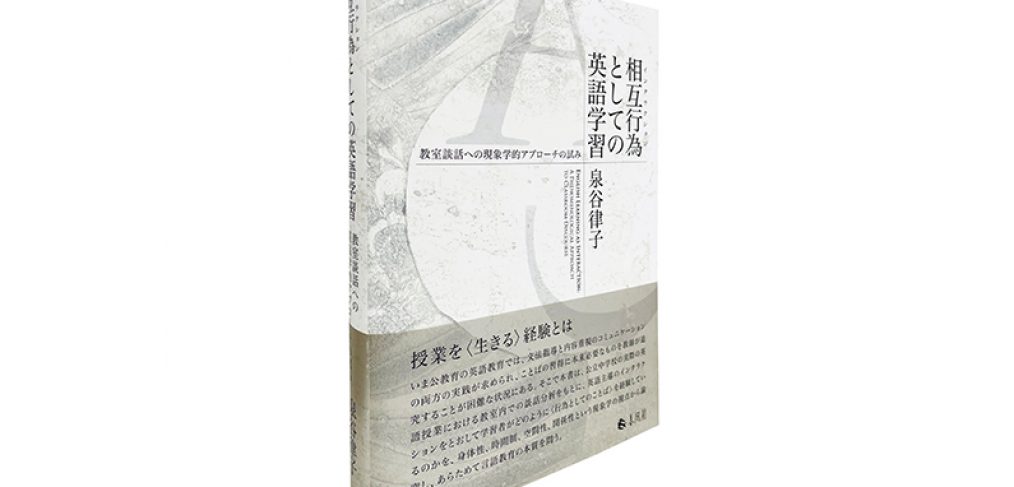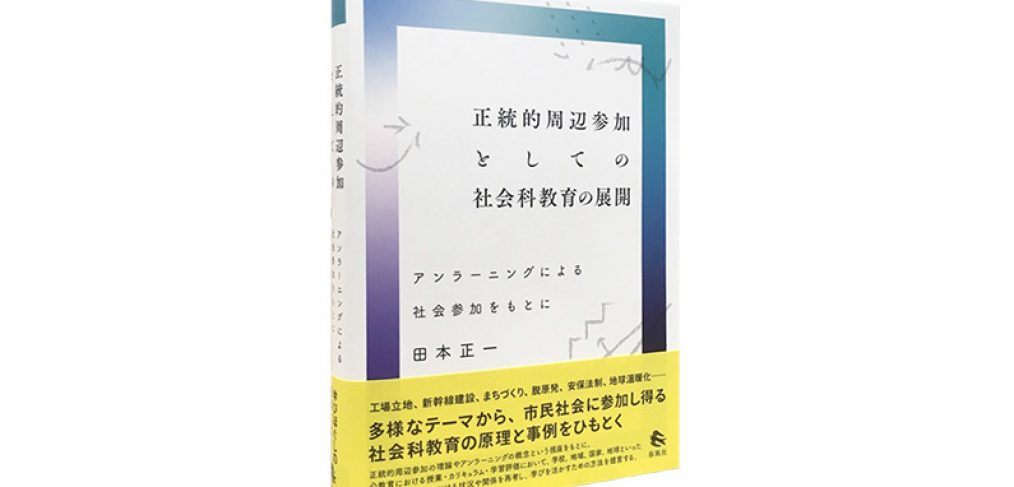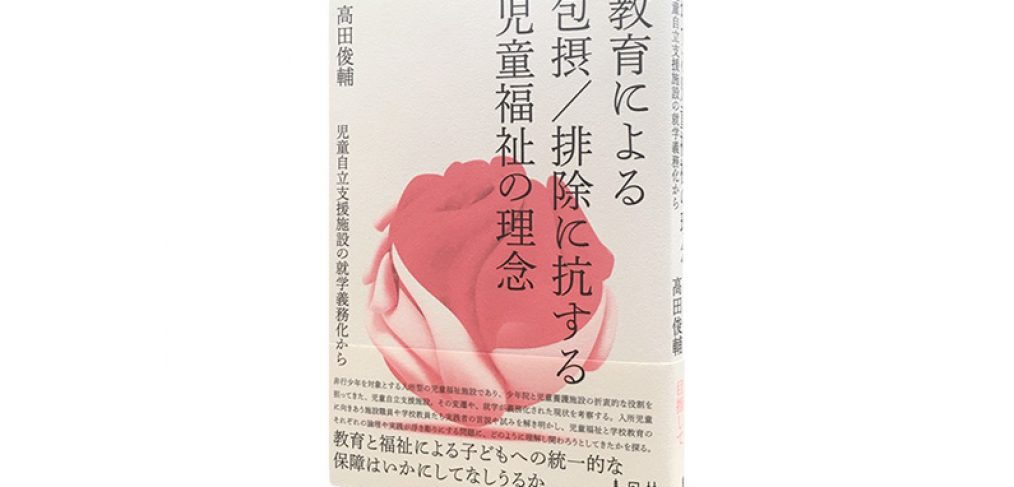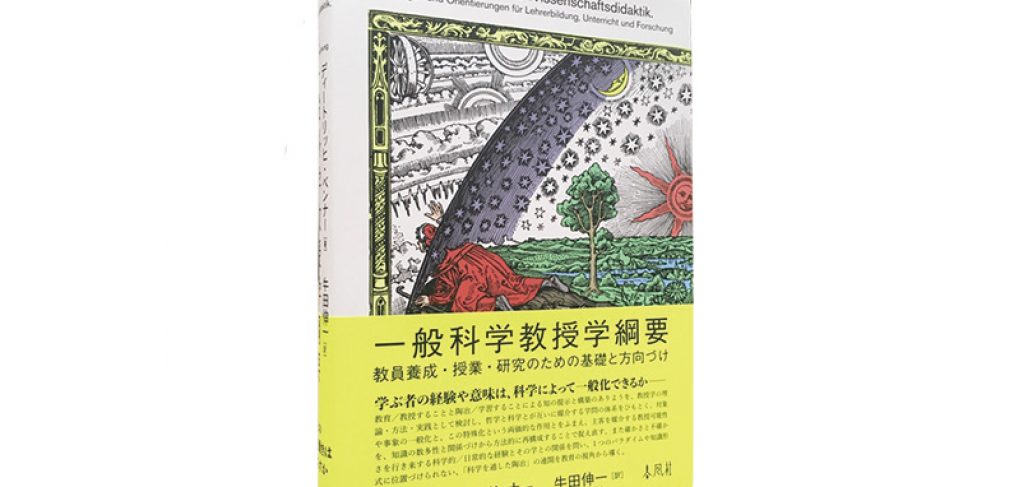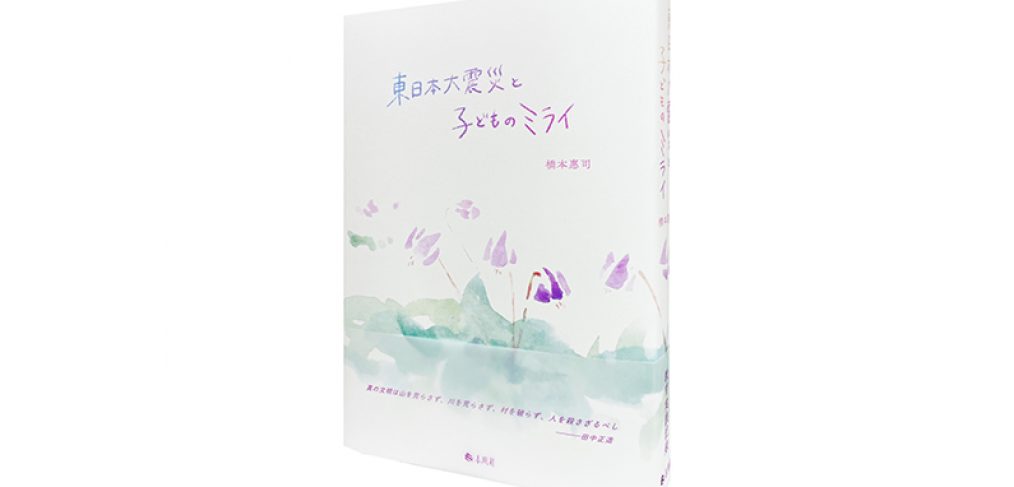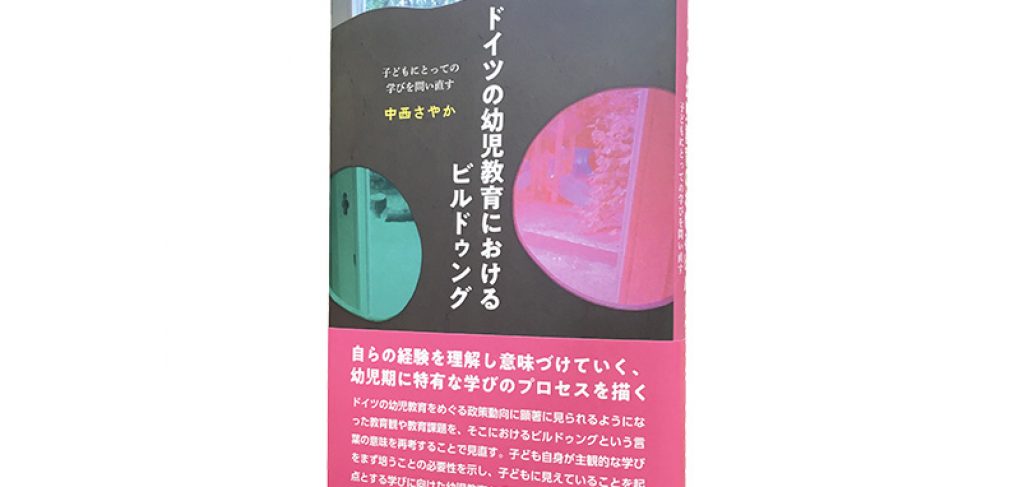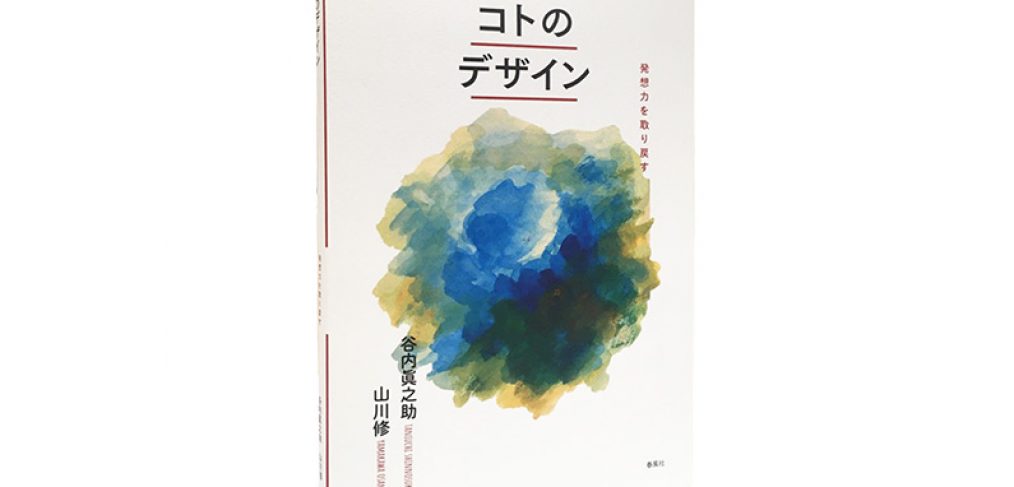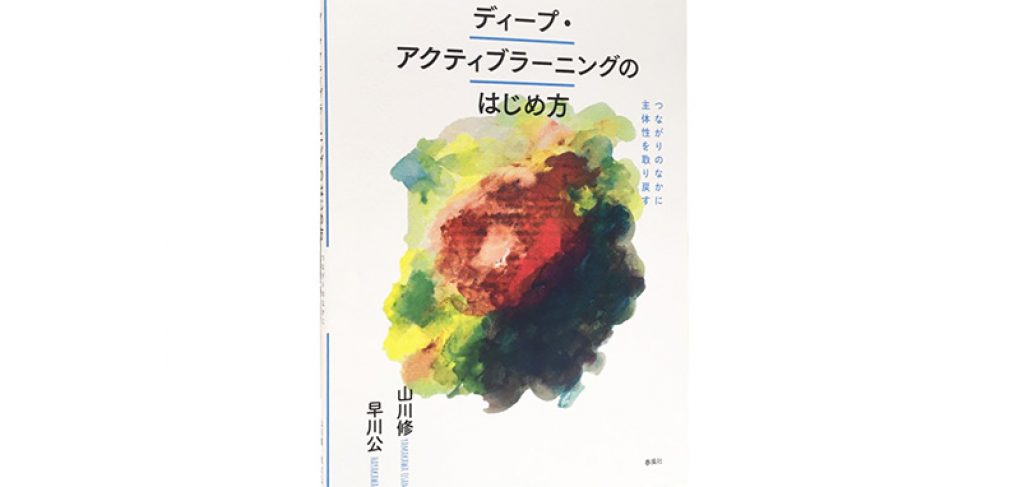アンリ・ワロンの精神発生学と人間発達研究
その思想と理論の現代的意義を探って
- 亀谷和史(著)/2024年3月
- 4200円(本体)/四六判上製304頁
- 装丁:長田年伸
20世紀初頭から半ばにかけて心理学研究に携わったアンリ・ワロンの人間発達思想を、〈精神発生学〉の構想という観点からひもとく。現代の発達心理学の領域に収まらないその哲学的・ 発達思想的な理論の到達点や展望、意義を検討し、〈精神〉の発生・発達過程の本質と、これまで見逃されてきた心身の相互関係を探る。
(ISBN 9784861109331)
目次|Contents
凡例
はじめに
序章 アンリ・ワロンが生きた時代と今日のワロン研究の到達点
第1章 アンリ・ワロンの〈精神発生学〉の構想と人間発達研究
第2章 アンリ・ワロンの発達研究の先駆性と〈意識〉の発生的研究
第3章 アンリ・ワロンの発達理論における〈姿勢機能(システム)〉概念と模倣発達論
第4章 アンリ・ワロンの発達理論と乳児保育――〈こころ〉と〈からだ〉の発達の統一的理解をめざして
第5章 アンリ・ワロンの発達理論における〈機能〉把握と機能連関
第6章 アンリ・ワロンの精神病理学研究と『病理心理学』――その認識論的立場をめぐって
第7章 アンリ・ワロンの人格発達研究における〈指向性〉の機能
補章 アンリ・ワロン著『行為から思考へ――比較心理学試論』序論
あとがき
主な参考文献
著者|Author
亀谷和史(かめたに・かずふみ)
日本福祉大学教育・心理学部教授。専門は、発達思想、教育哲学、保育学。主要著書に『ピアジェ×ワロン論争――発達するとはどういうことか』(編訳著、ミネルヴァ書房、一九九六年)、『現代保育と子育て支援――保育学入門』(編著、八千代出版、二〇〇六年)、『「知的な育ち」を形成する保育実践Ⅰ・Ⅱ』(編著、新読書社、二〇一三年、二〇一六年)ほか。