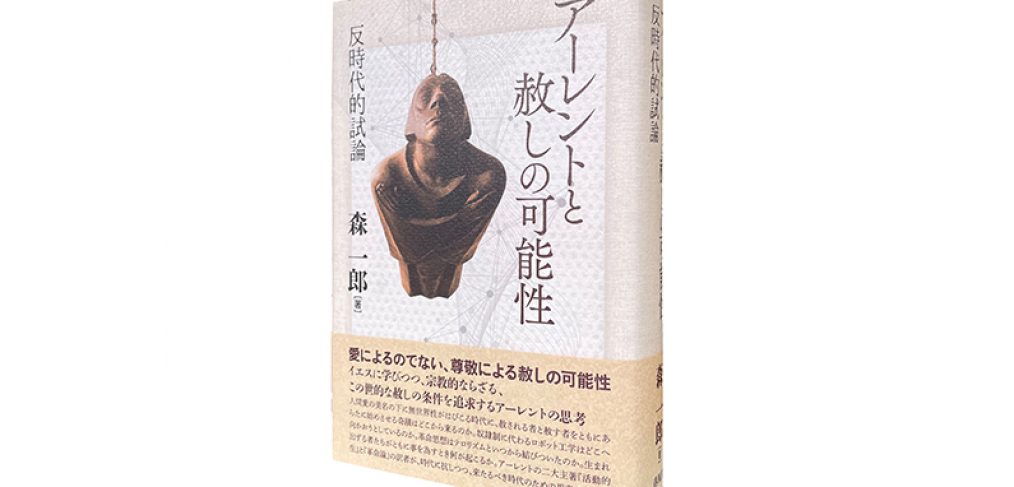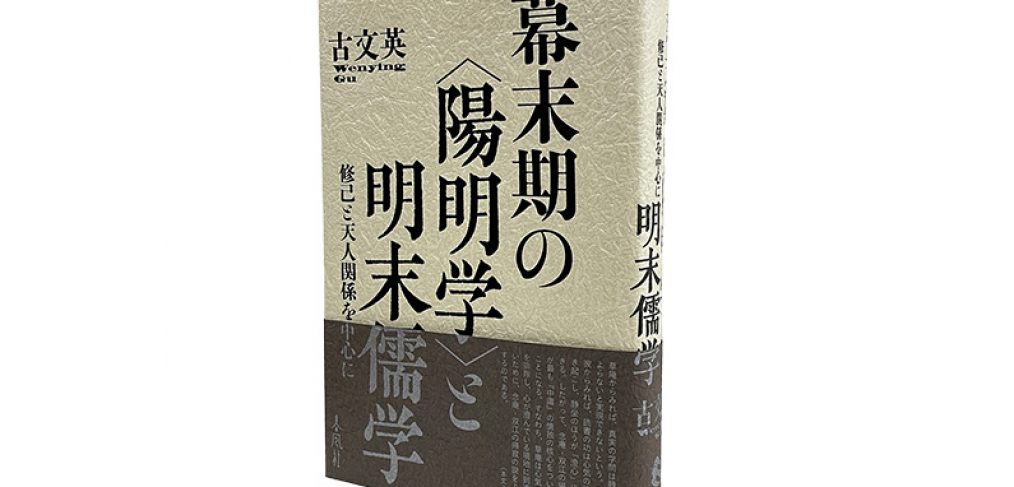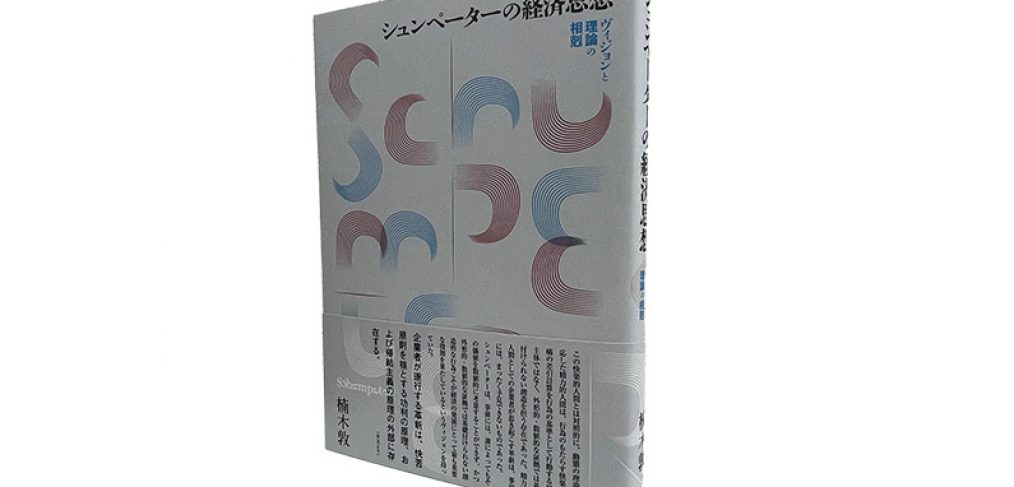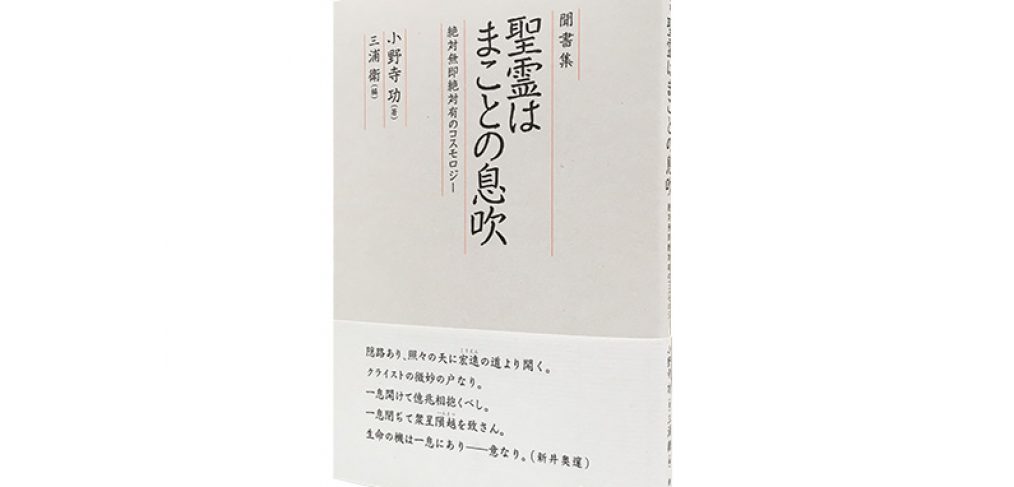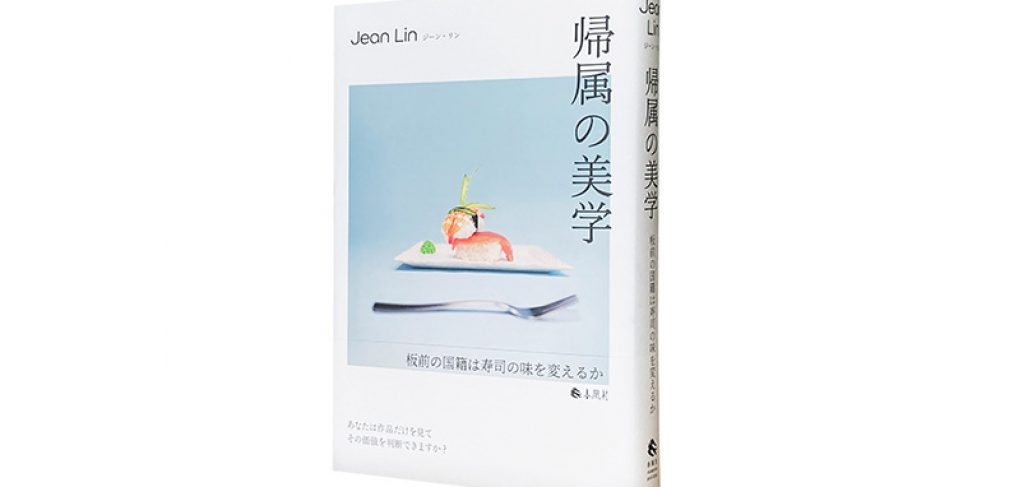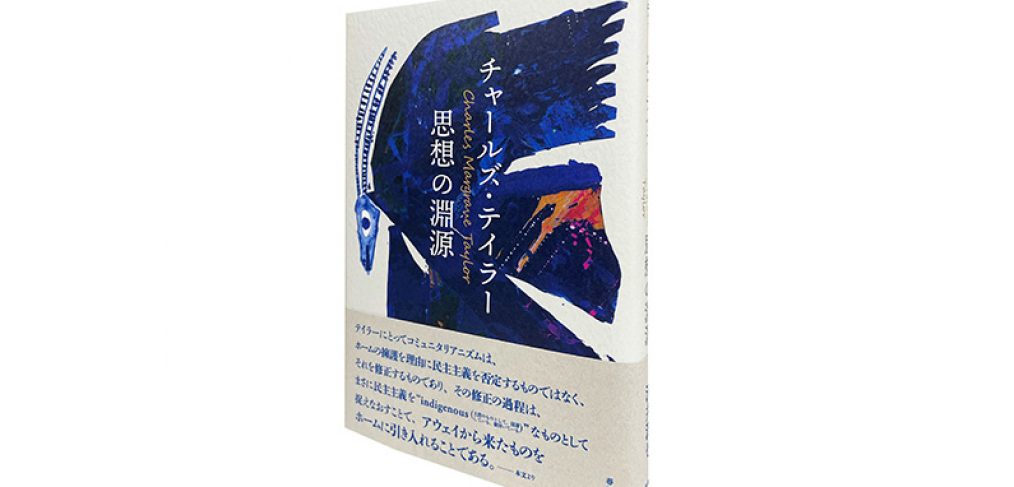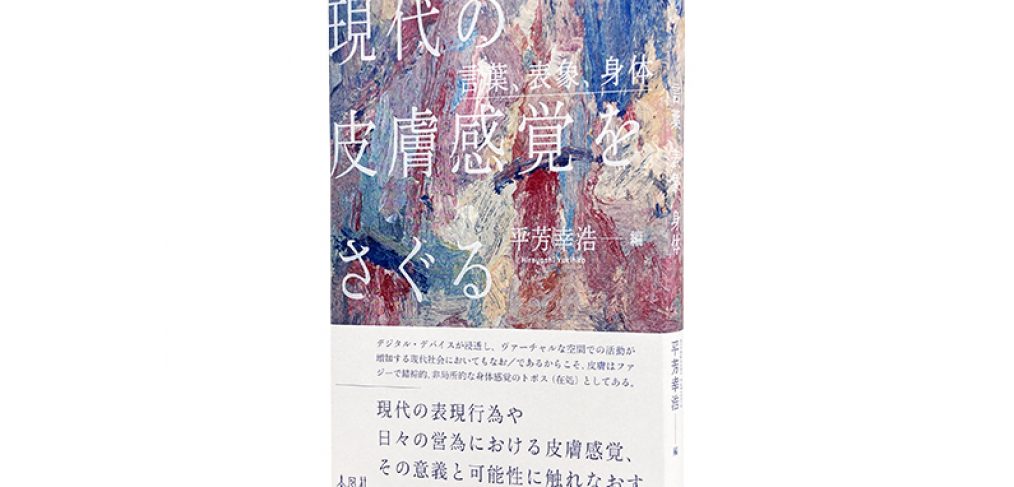挨拶の哲学
- 鳥越覚生(著)/2024年5月
- 3500円(本体)/四六判上製240頁
- 装丁:矢萩多聞
挨拶に関し様々な角度から思索を重ね、挨拶という現象の意義を解明する。
「挨拶は大文字の理念ではない。挨拶は頭や理性からの指令ではなくて、我が身からあふれてくる幽かな宇宙ことばである。これはまた、人間に残された最後の小さな「やさしさ」と言ってもよい。と言うのも、真正の挨拶はわが身、それもその底辺である足裏から湧き上がってくるものだからである。」(本文より)
(ISBN 9784861109270)
目次|contents
はじめの挨拶
第一部 思想史篇 ショーペンハウアーからレヴィナスへ
佇む傍観者からの挨拶
第一章 無責任の散歩
第二章 暗がりの色彩論
第三章 色彩の挨拶
第四章 世界を映す一つの眼と巨人
第五章 立ち上がって、祈っていなさい
第二部 教示篇 挨拶の哲学 よく生きるために
はじめの挨拶
第一章 人間の無関心
第二章 共生共苦の宇宙ことば
第三章 挨拶と祈り
おわりの挨拶 人間のやさしさに賭ける
あとがき
初出一覧
索引
著者|author
鳥越覚生 (とりごえ・かくせい)
1984年石川県金沢市生まれ
博士(文学・京都大学)
主要著作
『佇む傍観者の哲学 ショーペンハウアー救済論における無関心の研究』晃洋書房、2022年