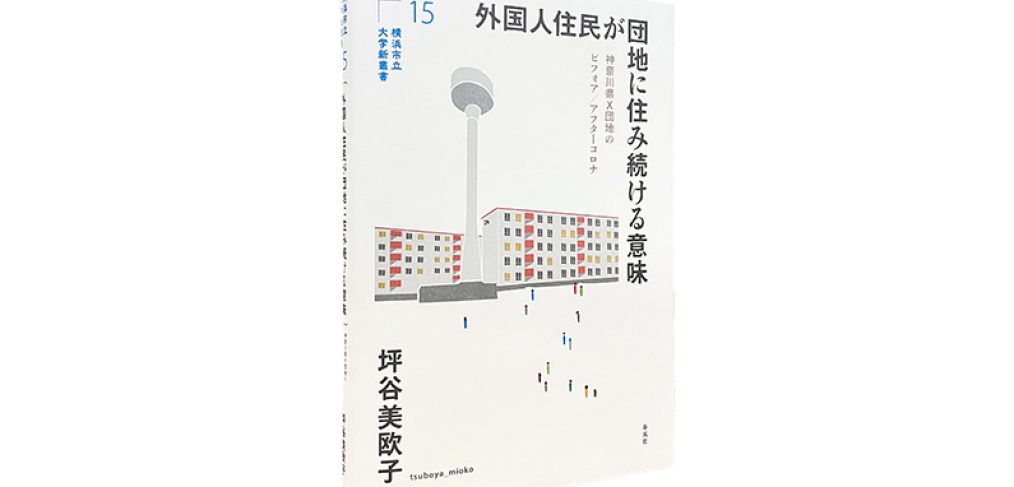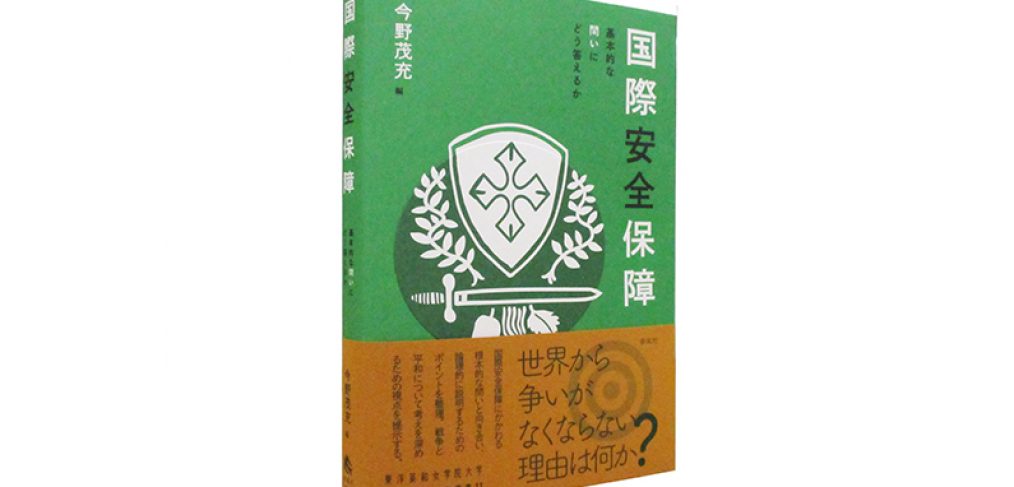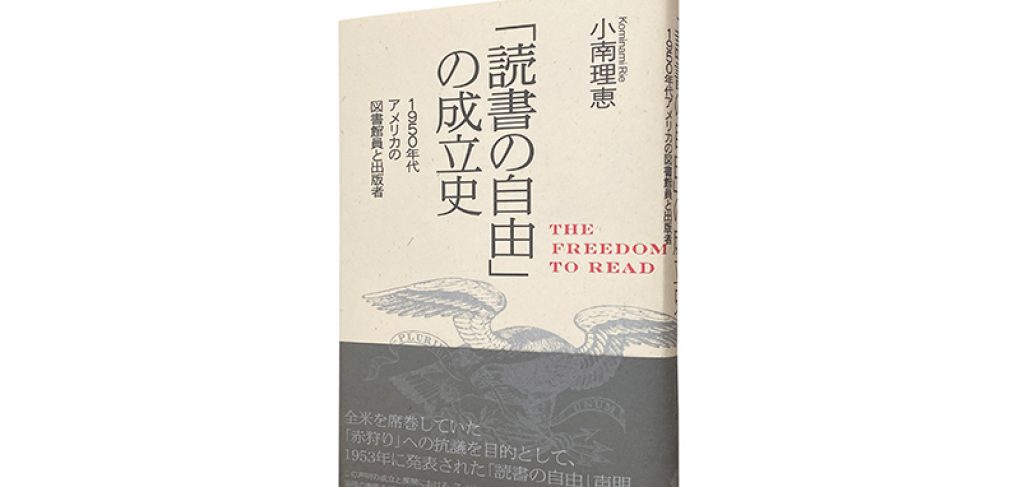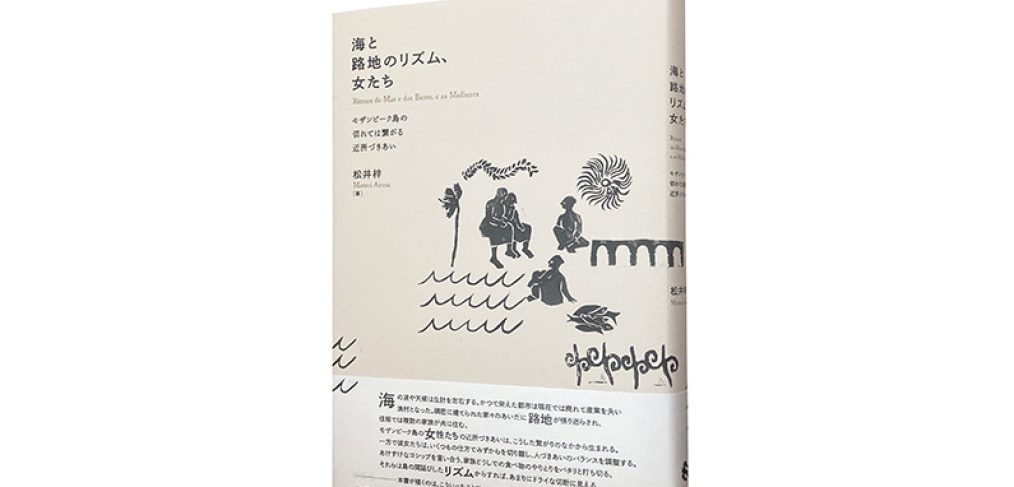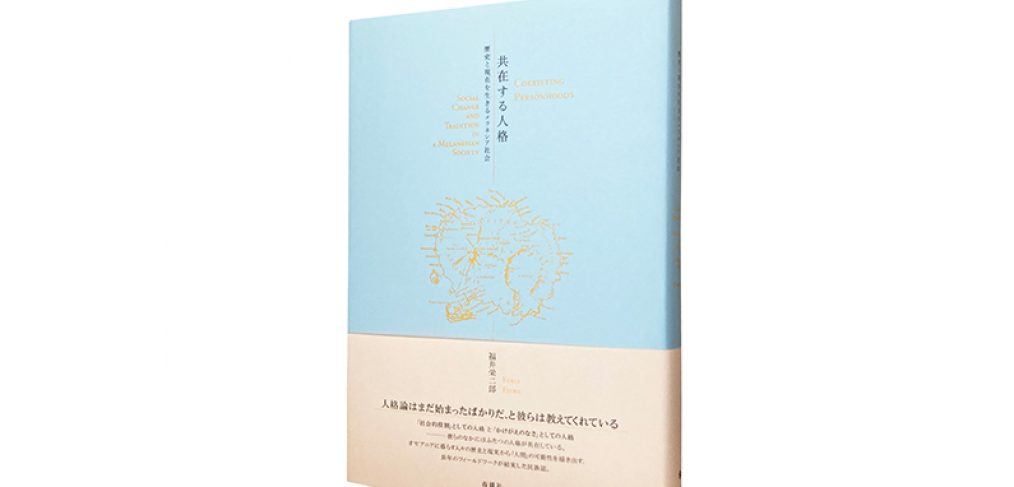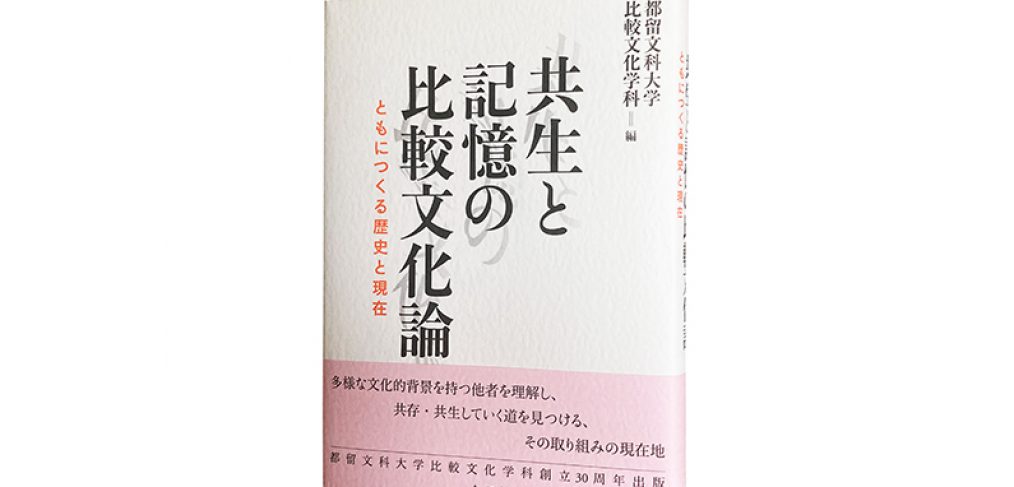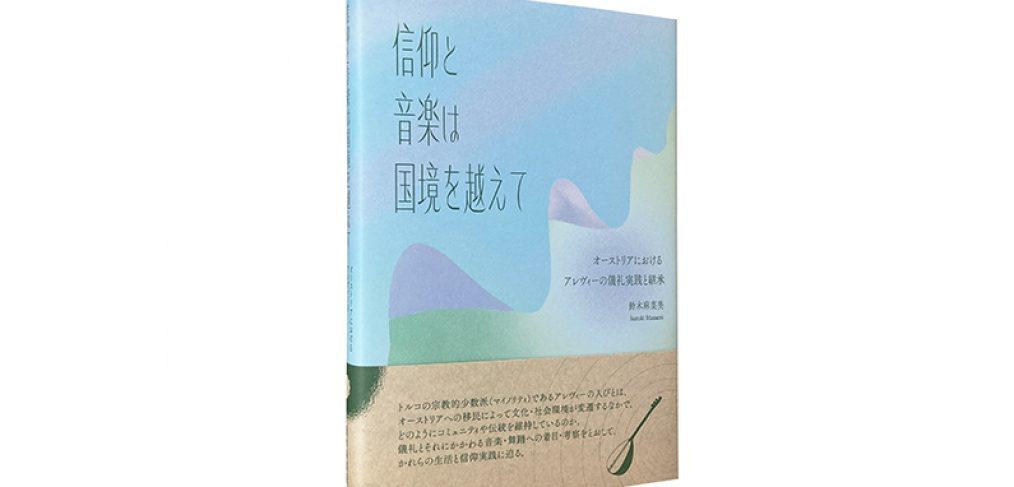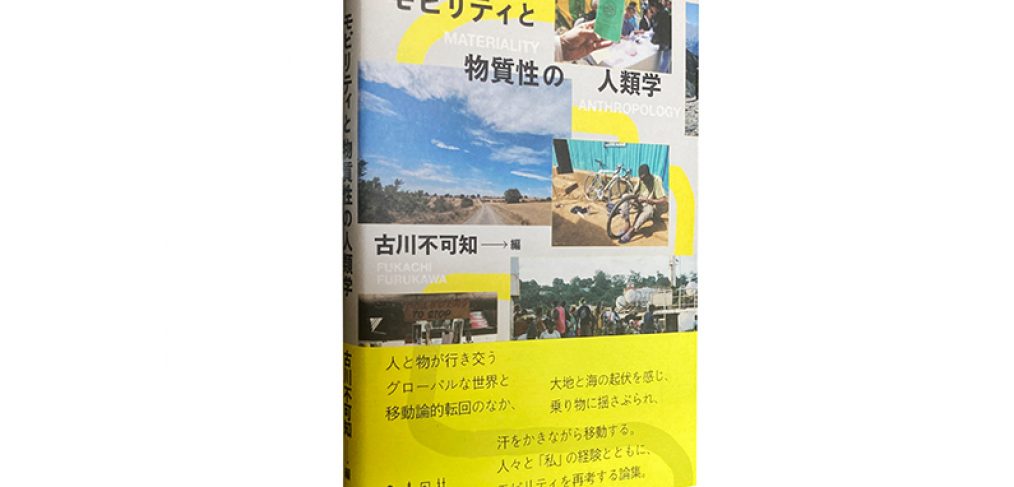ベルブアルブアルの世界
マレーシアの柔構造時間と柔構造社会
- 板垣明美(著)/2024年6月
- 3000円(本体)/四六判並製340頁
- 装丁:矢萩多聞
- 挿画:越野世帆里
「お金の理論」と「人の理論」のバランスをとるメカニズムとは?
カギとなるゼロ時間(無の時間)をマレーシアの農村で徹底調査し、その役割と重要性を明らかにする。
(ISBN 9784861109201)
目次|Contents
はしがき
序 章 文化人類学が捉えた「時間」と「環境問題=持続可能性」の関連
第1章 マレー人農村の柔構造時間と柔構造社会
――新しい技術も自分たち流に
第2章 ベルブアルブアルの世界
――マレー人農村におけるおしゃべり活動とその成員
第3章 マレー人農村は変わったか
――マレーシア・ケダ州の大規模灌漑プロジェクトと農民の対応
第4章 マレーシアにおける農薬使用の抑制のフィードバック
――ケダ州ムダ地域G村の「漁労稲作果樹菜園文化生態系」の事例
あとがき
アペンディックス
著者|Author
板垣明美 (いたがき・あけみ)
1985年筑波大学環境科学研究科修士課程修了、1993年筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。
横浜市立大学都市社会文化研究科准教授。
主要著書に『癒しと呪いの人類学』(2003年、春風社)、『ヴェトナム―変化する医療と儀礼』(編著、2008年、春風社)ほか。
この本を注文する
Amazonで注文する e-honで注文する 楽天ブックスで注文する