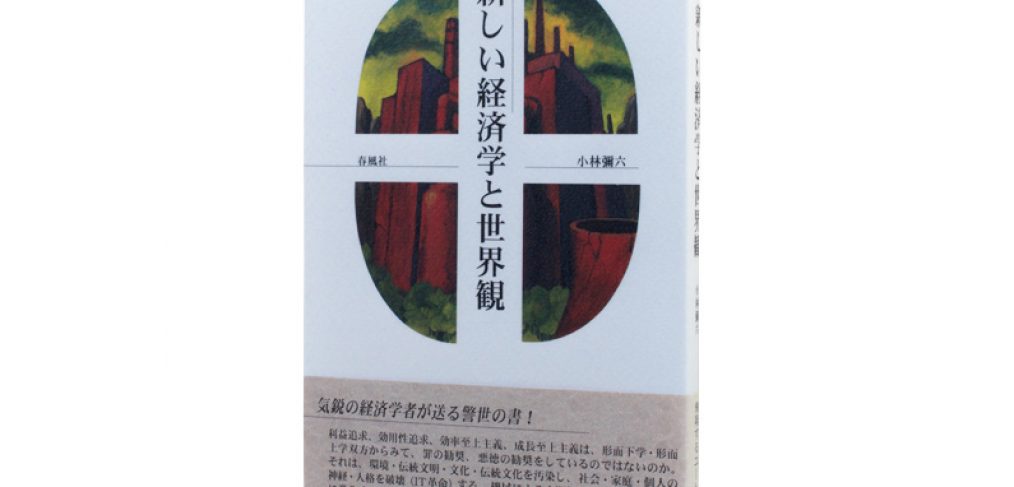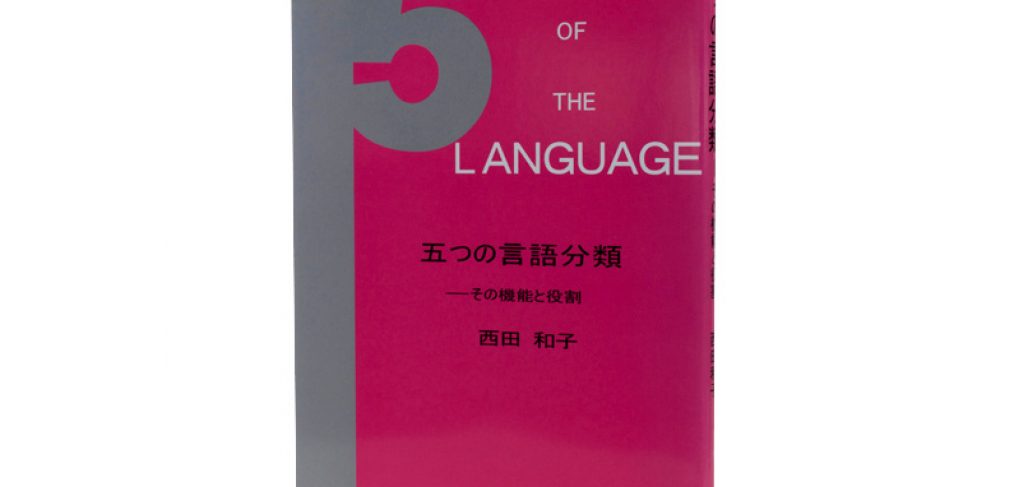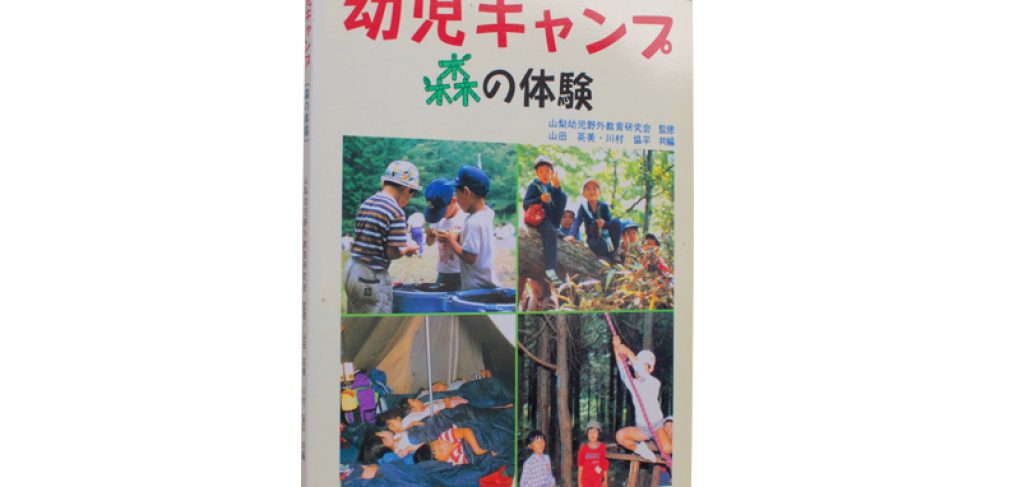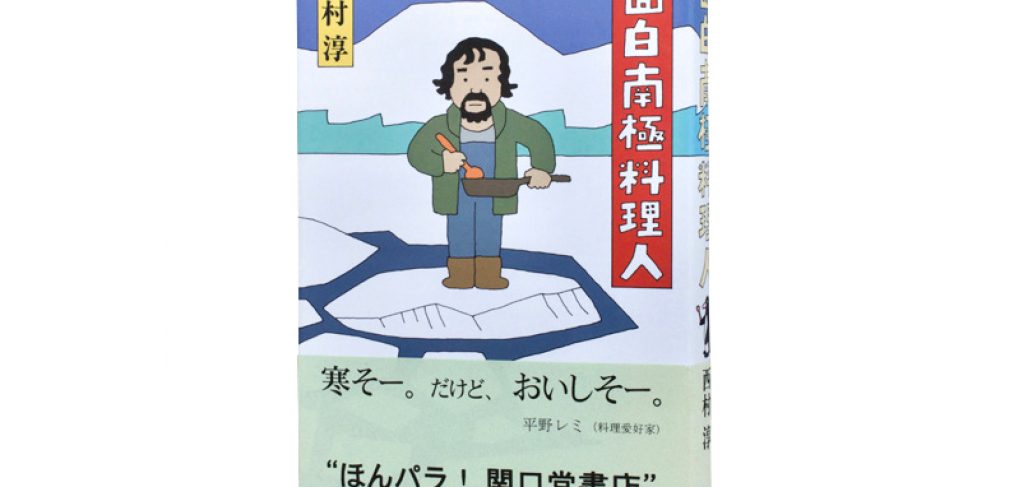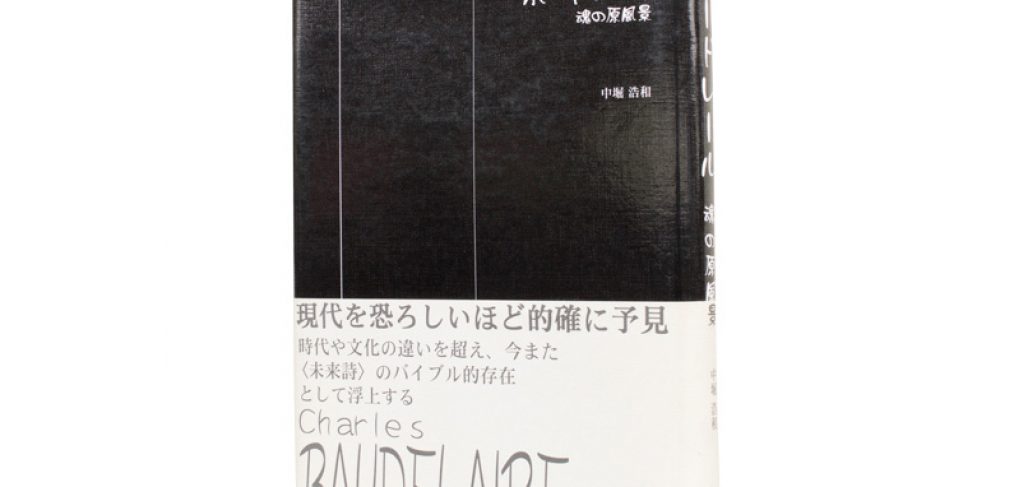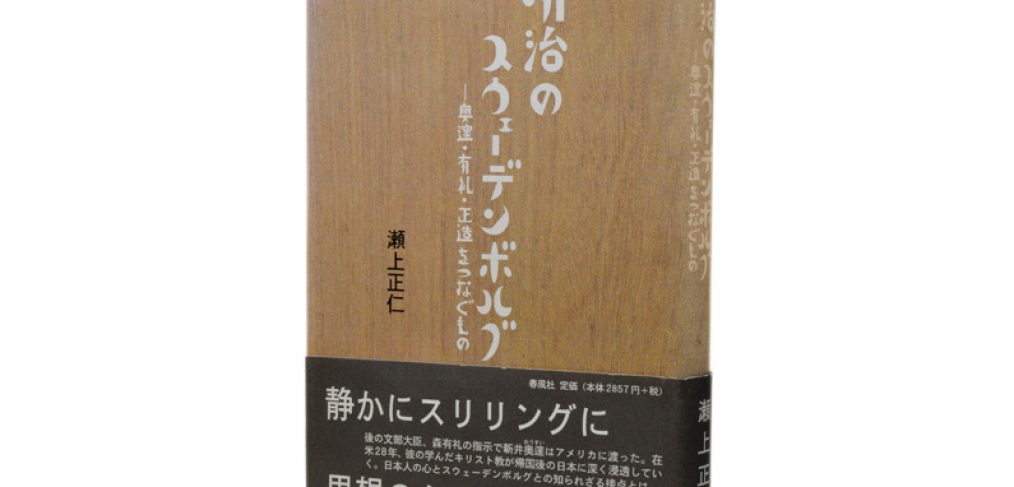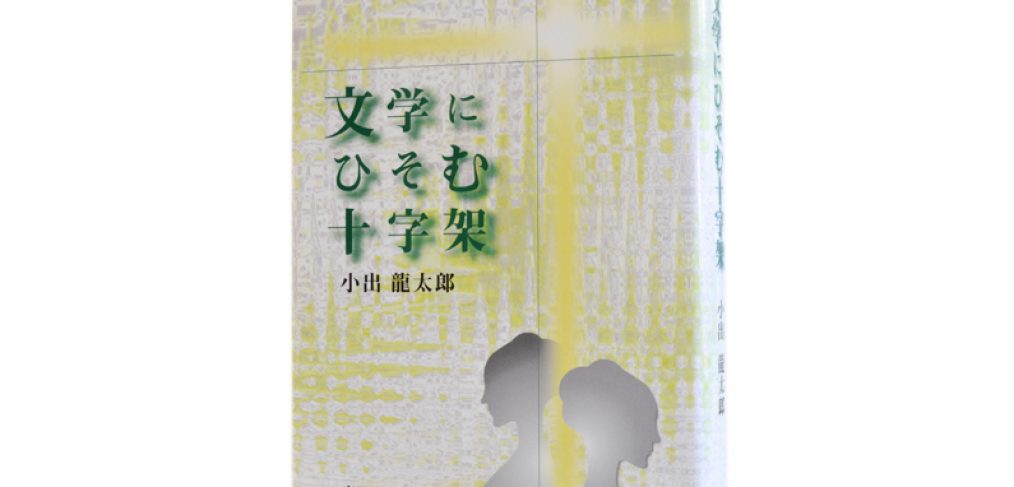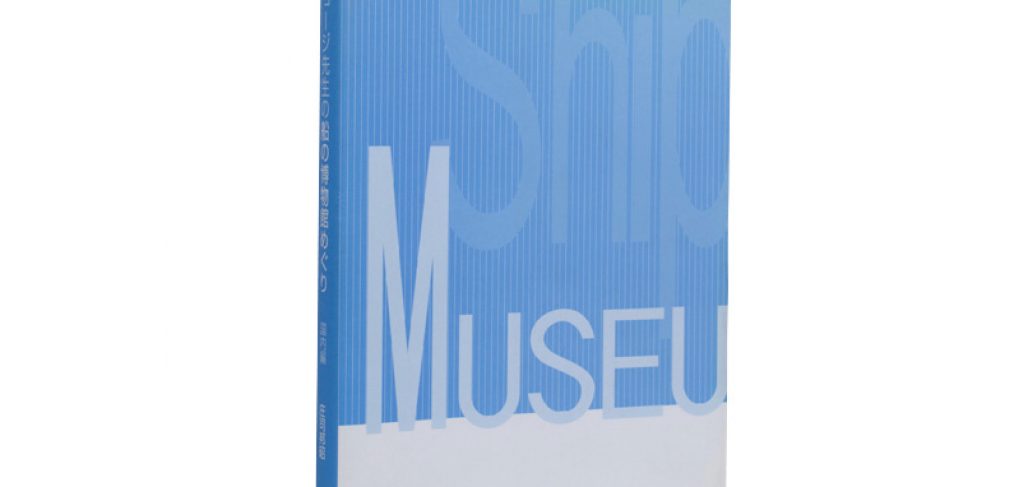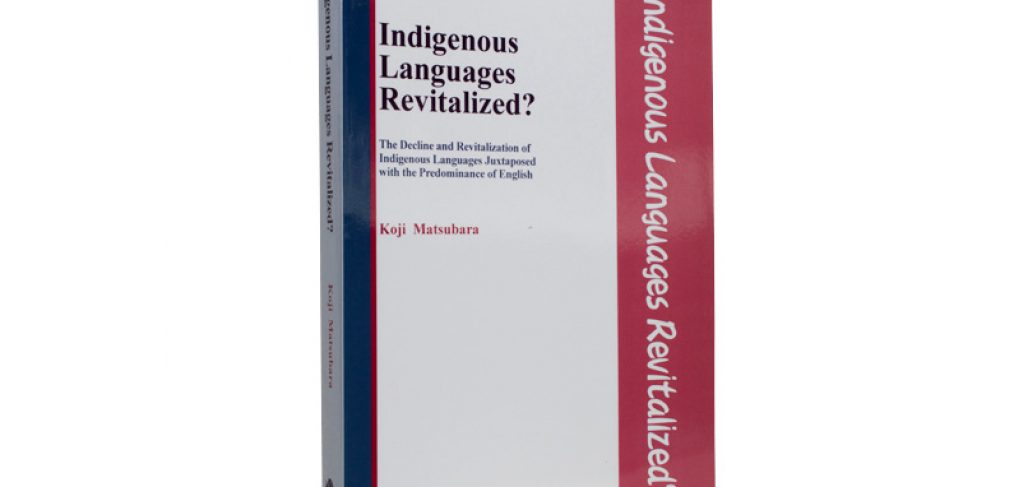新しい経済学と世界観
- 小林彌六/2001年6月
- 2381円(本体)/四六判・256頁
気鋭の経済学者が送る警世の書! 利益追求、効用性追求、効率至上主義、成長至上主義は、形而下学・形而上学双方からみて、罪の勧奨、悪徳の勧奨をしているのではないか―利他即利自のパラダイムと「友愛主義」に基づく新しい経済学の必要性を説く!
(ISBN 4921146306)
目次|indexs
第一章 二一世紀の新文明
ニュートン型社会科学・人間学からの離脱とポスト・アインシュタイン型へのパラダイム転換/21世紀の新文明/21世紀の経済・企業・技術と地球環境・資源・生命の「共生」/東洋文明と西洋文明の統一・止揚によってポスト・モダンの新社会学と新文明の展開を/聖徳太子に学べ
第二章 社会科学のパラダイム転換―疎外された社会科学よりポスト・モダンのホーリスティックな社会科学へ
社会科学のパラダイム転換の必要性/現代社会科学と現代世界/ニュートン型社会科学よりポスト・アインシュタイン、ポスト・ホーキング型社会科学への転換/ポスト・モダンの社会科学は東洋の知恵に学ぶべし―西洋式社会科学と東洋の社会思想の統合による新社会科学の建設を
第三章 21世紀の新しい社会思想
経済学のパラダイム転換/第三の経済学と第三の経済システム―友愛経済学と友愛主義の社会思想
第四章 グローバル化世界の実相・一仮説としての問いかけ
世界政経寡占体制(グローバル化世界の構図)その一/第一節 大国同盟―世界オルゴポリー・オリガーキー寡占制・奉仕か支配か/超国家的な経済システム/世界システムとしての資本主義/世界政経寡占体制(グローバル化世界の構図)その二/グローバル化世界・世界資本主義/グローバル超帝国主義
著者|author
小林 彌六 (こばやし・やろく)
筑波大学名誉教授。現在、明海大学経済学部教授。経済学博士。近代経済学とマルクス経済学研究の経歴を持つ立場から、その垣根を越えた視点で独自の現代資本主義論、現代社会主義論、新従属理論などの展開を行う。著書『友愛主義宣言』『新ユートピア経済学』『資本主義と社会主義―停滞と苦悩』など。
担当編集者から
著者はもともとちゃきちゃきのマルクス経済学者。この本には著者・小林彌六が真剣に学問と苦闘する姿が垣間見える。[-三浦-]