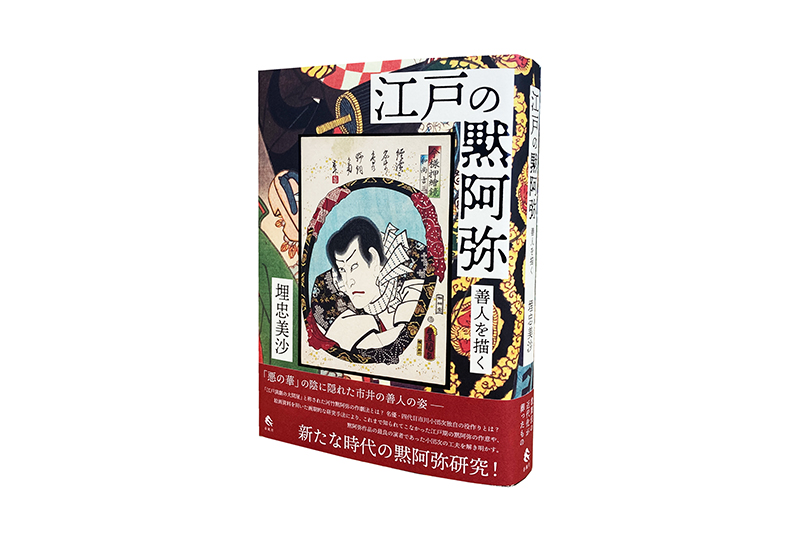「秋田魁新報」2021年4月9日号に、弊社代表・三浦衛のコラム「歩くリズムで書いた人 武塙三山の文章に触れて」が掲載されました。
詳細は以下リンクよりご覧になれます。
◆秋田魁新報ウェブサイト「武塙三山を知っていますか? 井川出身文人の副読本制作」https://www.sakigake.jp/news/article/20210306AK0028/
「秋田魁新報」2021年4月9日号に、弊社代表・三浦衛のコラム「歩くリズムで書いた人 武塙三山の文章に触れて」が掲載されました。
詳細は以下リンクよりご覧になれます。
◆秋田魁新報ウェブサイト「武塙三山を知っていますか? 井川出身文人の副読本制作」https://www.sakigake.jp/news/article/20210306AK0028/
兵庫教育大学ウェブサイトで、坂口真康著『「共生社会」と教育―南アフリカ共和国の学校における取り組みが示す可能性』が紹介されました。
詳細は以下リンクよりご覧になれます。
◆兵庫教育大学「教員の著書」https://hyogo-u.ac.jp/about/public_relations/book/5275685.php
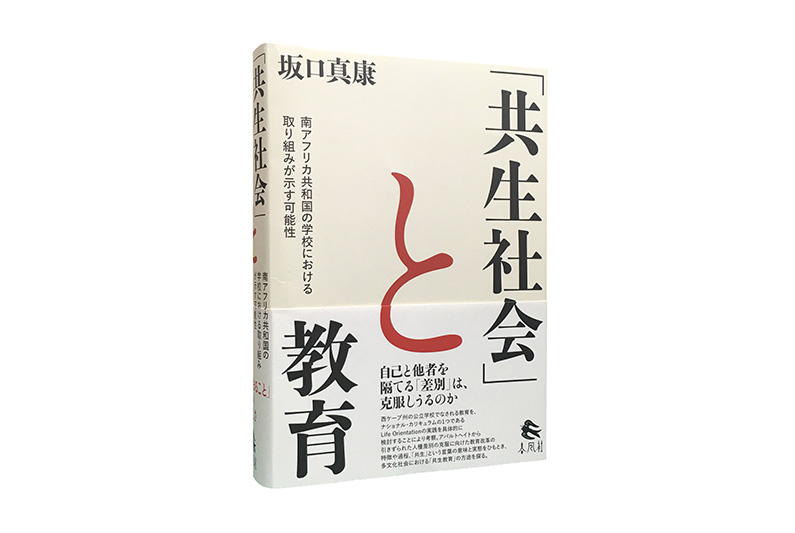
「図書新聞」第3492号(2021年4月17日号)に、ヘレン・M・ガンター著/末松裕基、生澤繁樹、橋本憲幸訳『教育のリーダーシップとハンナ・アーレント』座談会が掲載されました。「「悪の凡庸さ」とリーダーシップ――専門にとらわれず自由に発言することの大切さ」。
詳細は以下リンクよりご覧になれます。
◆図書新聞ウェブサイト http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/
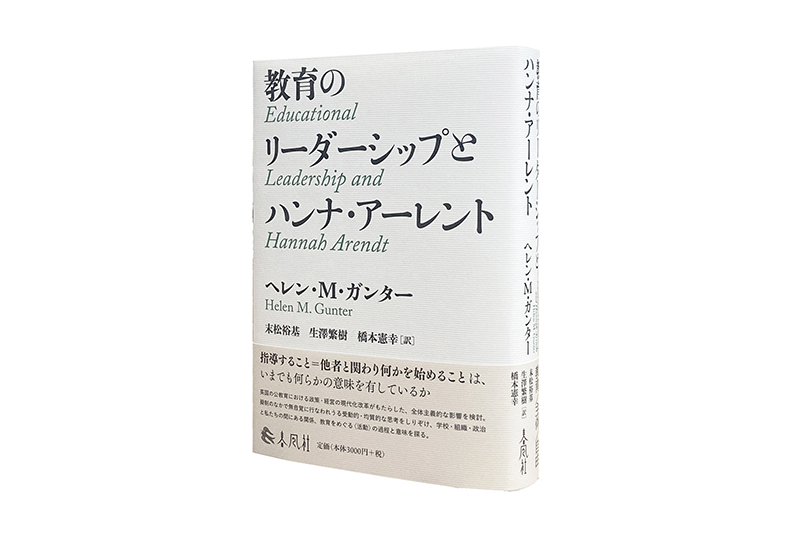
Webマガジン[Edit-us]2021年4月号に、坂口真康著『「共生社会」と教育――南アフリカ共和国の学校における取り組みが示す可能性』図書紹介と、著者によるコラム「和解のための道程 歴史をふり返ることの意味」が掲載されました。
コラムは、以下リンクからご覧になれます。
◆Webマガジン[Edit-us]「他人と生きるための社会学キーワード」
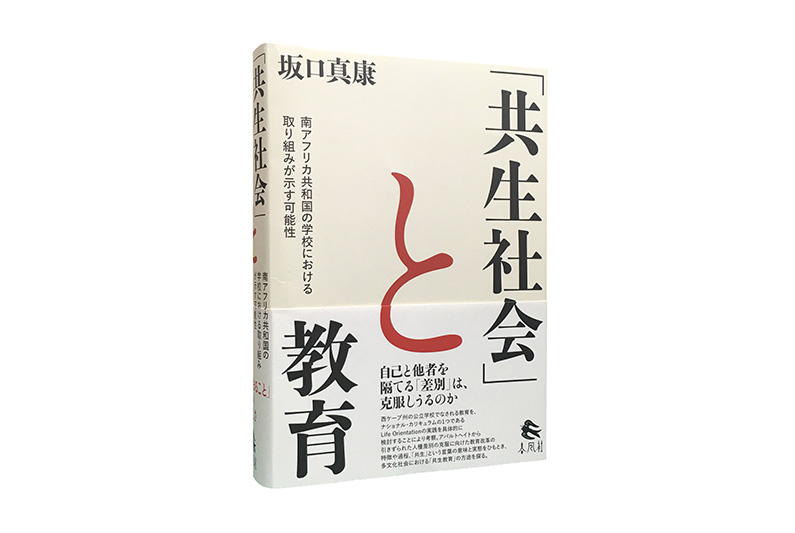
日本アメリカ文学会『アメリカ文学研究』第57号(2021年3月)に、『『パターソン』を読む――ウィリアムズの長篇詩』(江田孝臣 著)の書評が掲載されました。評者は三宅昭良先生(東京都立大学)です。「『パターソン』はその内部構造もさることながら、細部の意味も理解しやすいとはいえない。他の諸作品との関係もひとりでつかむのは容易でない。本書はそうした困難を解消してくれるすぐれた指南書である」
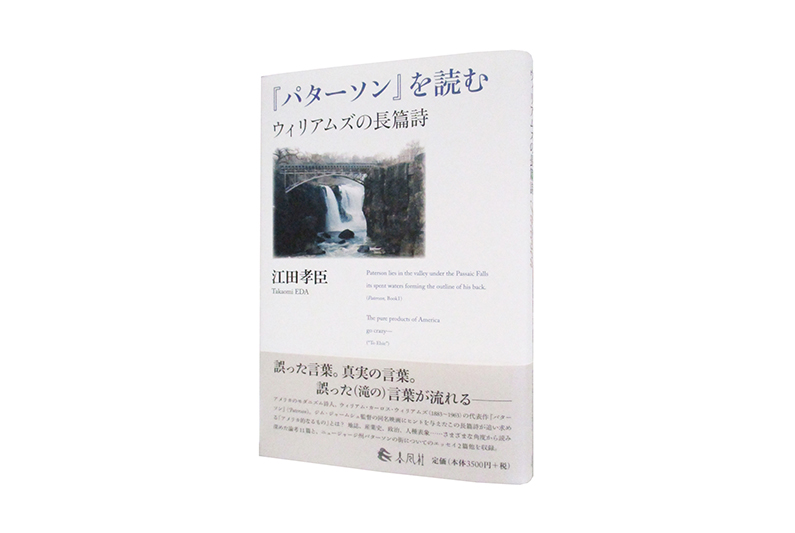
歌舞伎専門月刊誌『演劇界』2021年5月号「家で楽しむ歌舞伎 今月のおすすめ」欄にて、『江戸の黙阿弥――善人を描く』(埋忠美沙著)が紹介されました。「カラー図版も豊富で、作品が〝現代劇〟だった頃の上演に思いを馳せ、楽しめる一冊」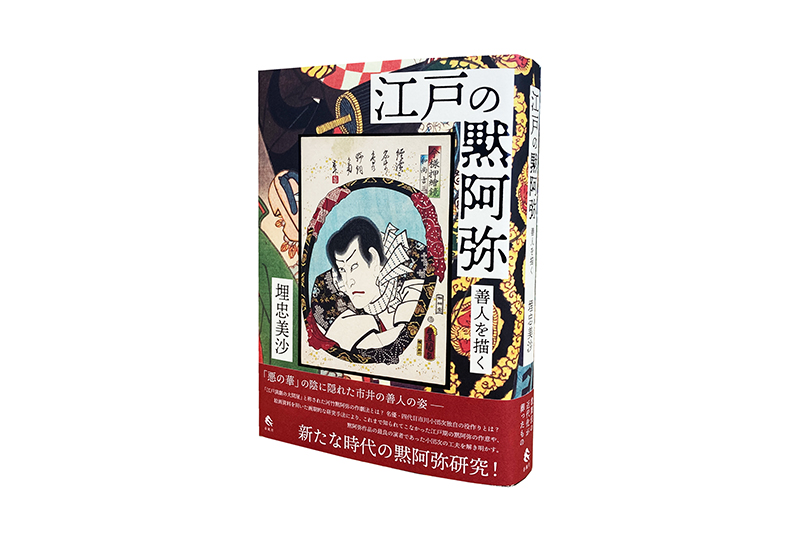
ウェブサイト「日本遺産 地下迷宮の秘密を守る旅 大谷石文化が息づくまち宇都宮」(宇都宮市大谷石文化推進協議会)に、髙山慶子著『江戸の名主 馬込勘解由』図書紹介が掲載されました。「馬込家の当主は代々「勘解由」と名乗り、江戸の中心部である日本橋地域の町人地の名主を世襲で務めた。……宇都宮藩戸田家との関係が縁となり、十一代当主は明治時代に栃木県内で養蚕業(蚕種製造)を行い、綿糸や麻糸の製造も模索するなど、さまざまな殖産興業の事業に挑戦した」
本文は、以下リンクからご覧になれます。
◆「大谷石文化学」
8.明治前期における大谷石の東京市場開拓(1)
9.明治前期における大谷石の東京市場開拓(2)
10.明治前期における大谷石の東京市場開拓(3)
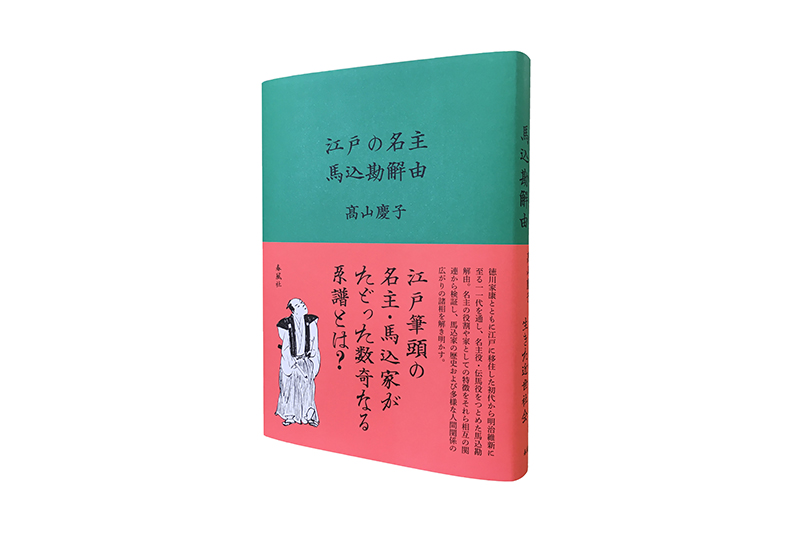
全国大学国語教育学会『国語科教育』第89巻(2021年)に、山田直之著『芦田恵之助の教育思想――とらわれからの解放をめざして』の書評が掲載されました。評者は村井万里子先生(鳴門教育大学)です。「「硬直化」は、山田氏のいう「とらわれ」から起こる。もちろん「とらわれからの解放」への「とらわれ」も避けねばならない。……「生活即ち伝統」に足を着けて歩むことが、これからも大切なことで有り続けるだろう」
書評全文は、下記URLよりご覧になれます。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/kokugoka/-char/ja
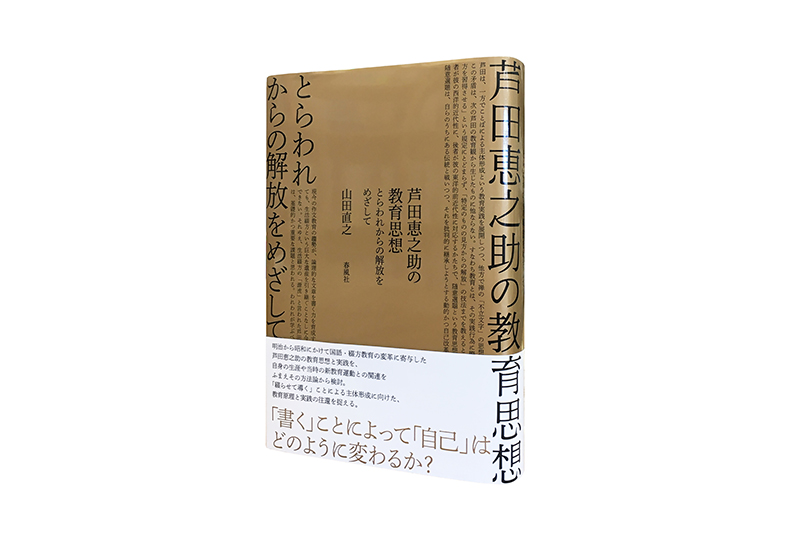
『死ぬ権利はあるか―安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非と命の価値』(有馬斉 著)、『居場所―生の回復と充溢のトポス』(萩原建次郎 著)の電子書籍を配信開始しました。電子書籍は Amazon Kindle、紀伊國屋書店Kinoppy、楽天Kobo、Google Play などの各書店でお求めになれます。
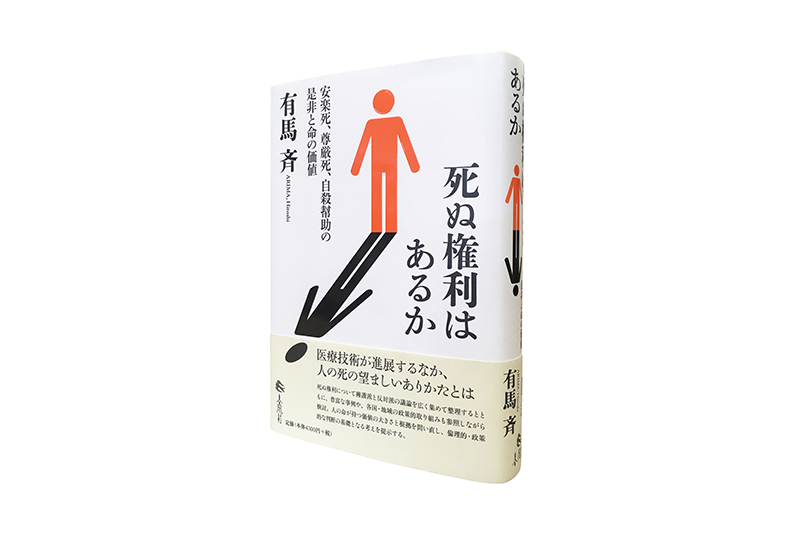
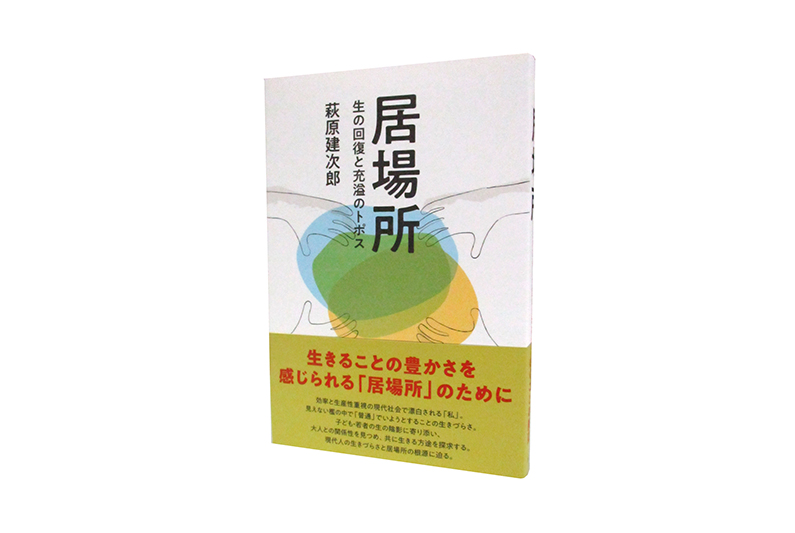
『図書新聞』第3490号/2021年4月3日号に『江戸の黙阿弥――善人を描く』(埋忠美沙 著)の書評が掲載されました。評者は日置貴之先生(明治大学)です。「文学研究でも美術史研究でもなく、紛うことなき「演劇学」の手法によって黙阿弥という重要な作者に迫った本書の意義は大きい」