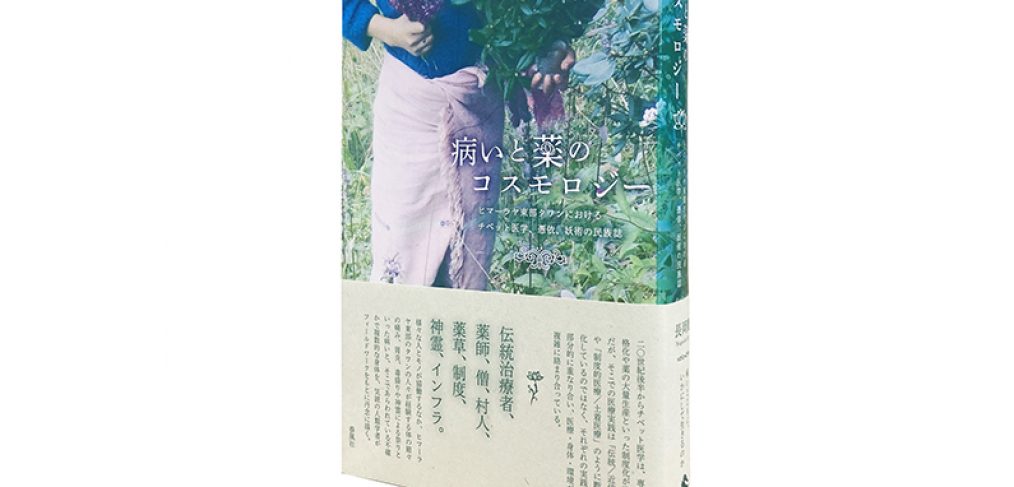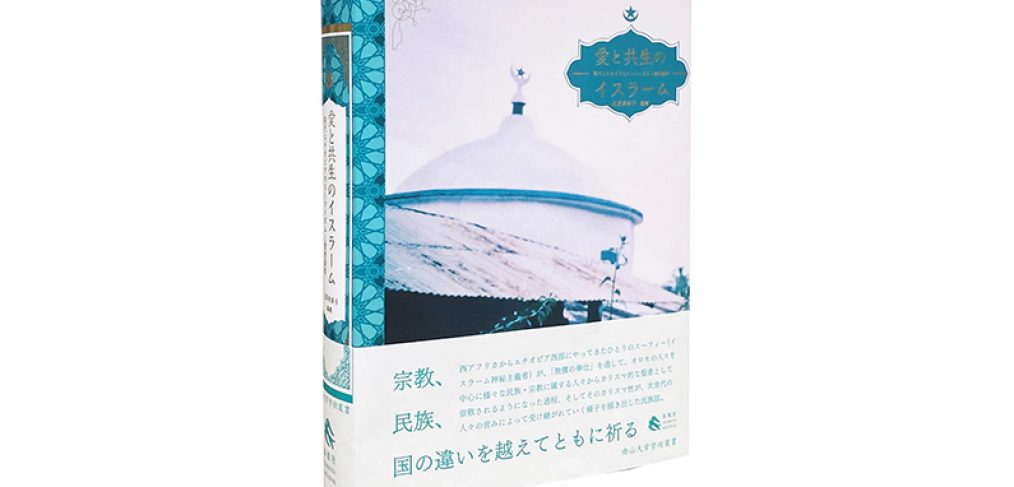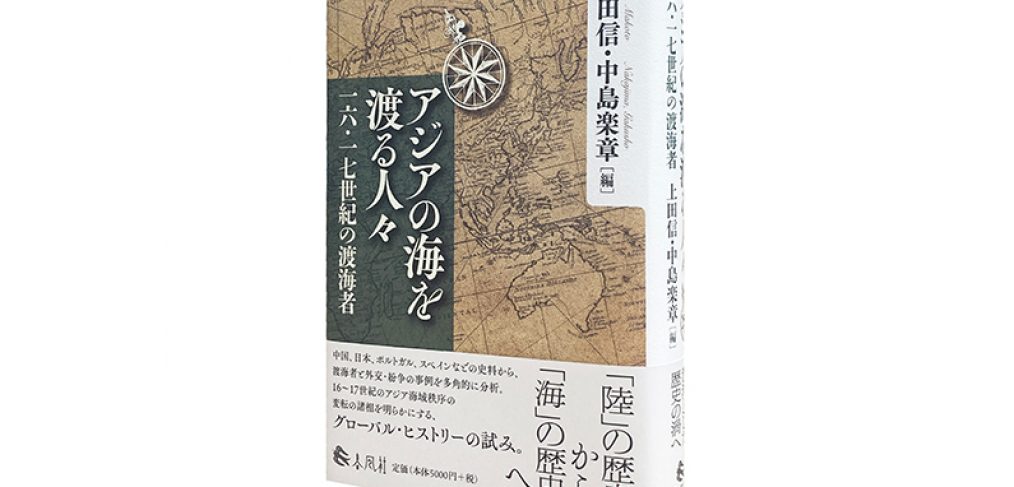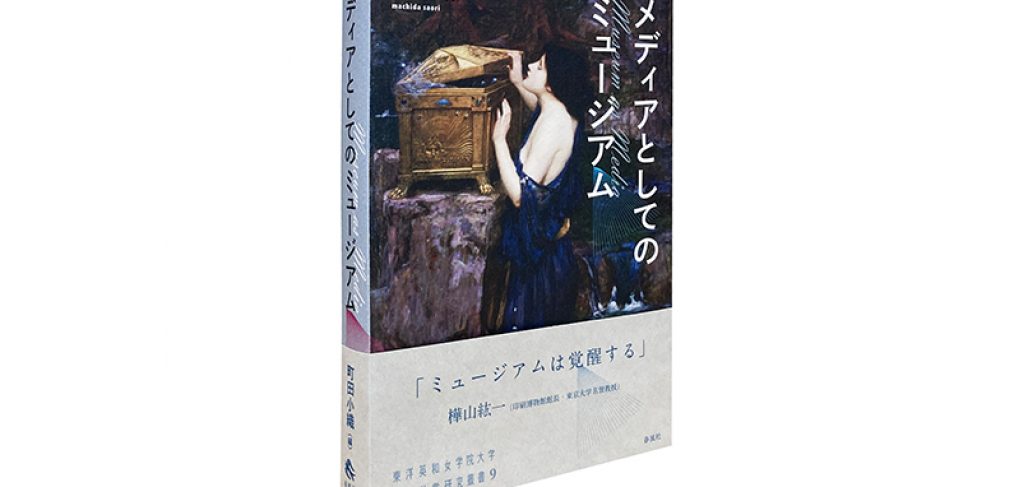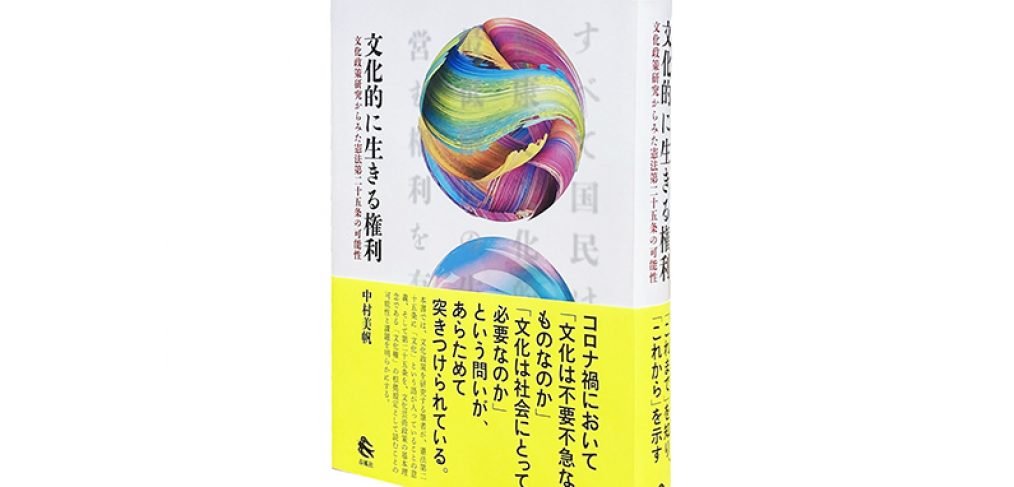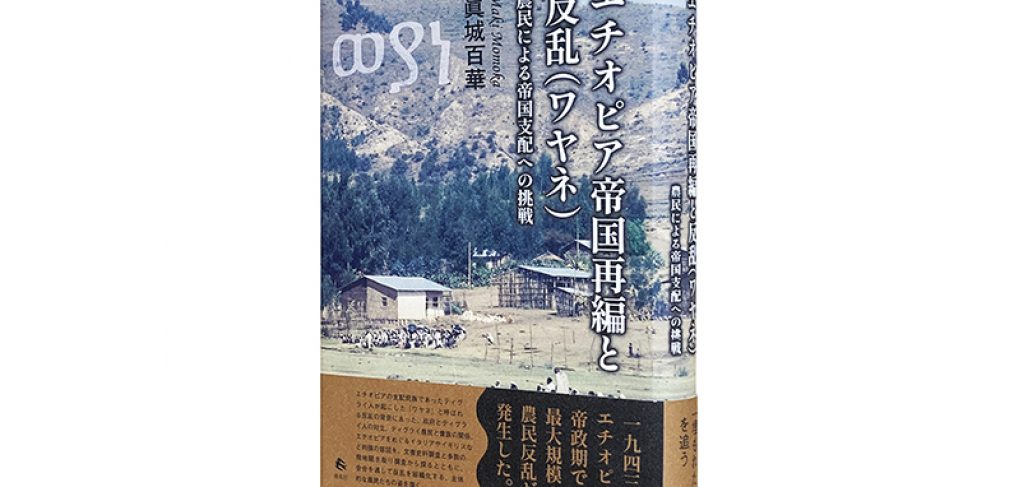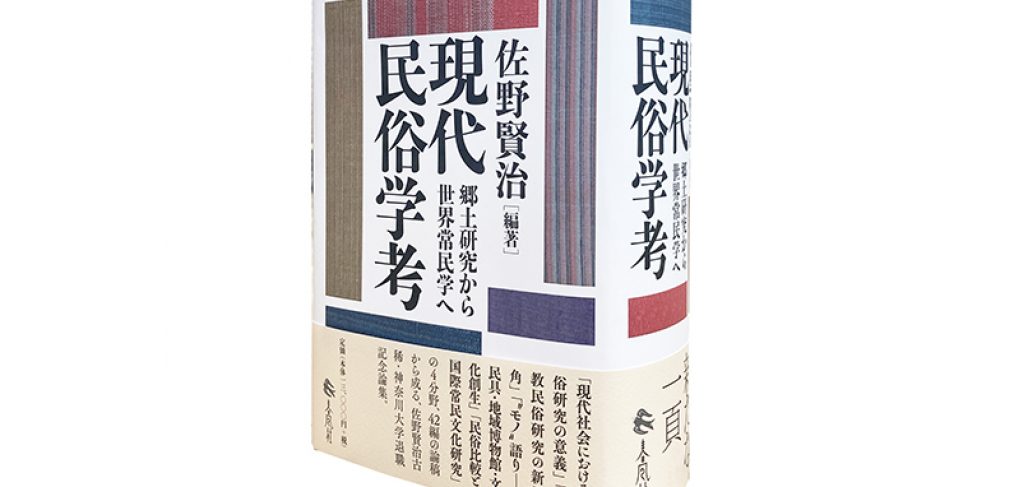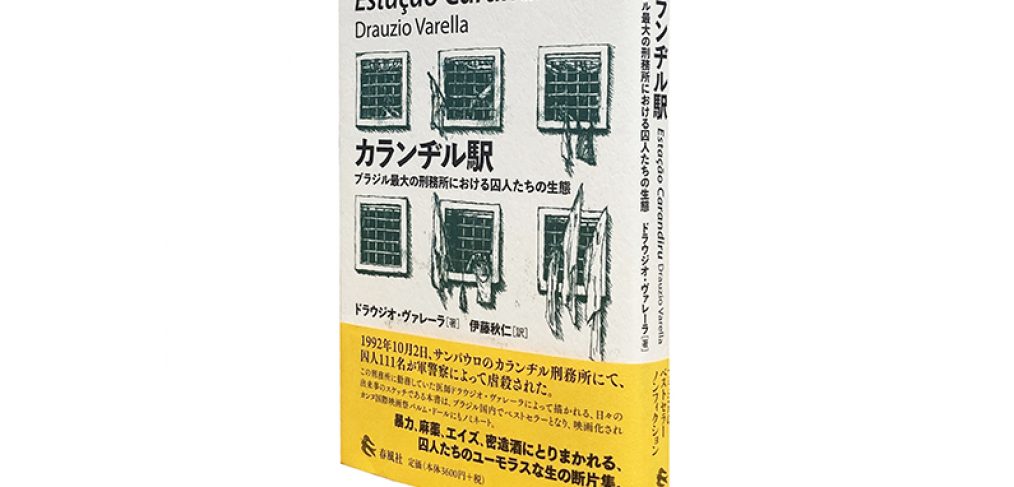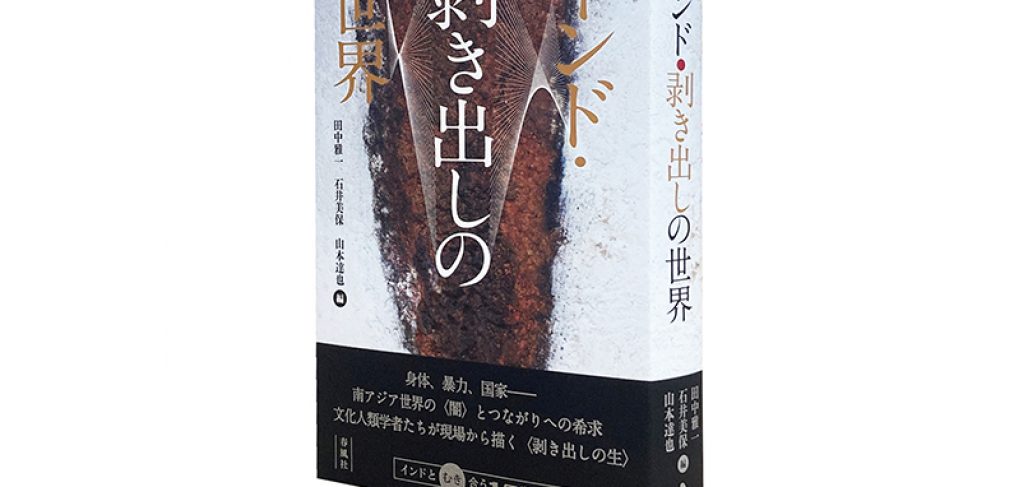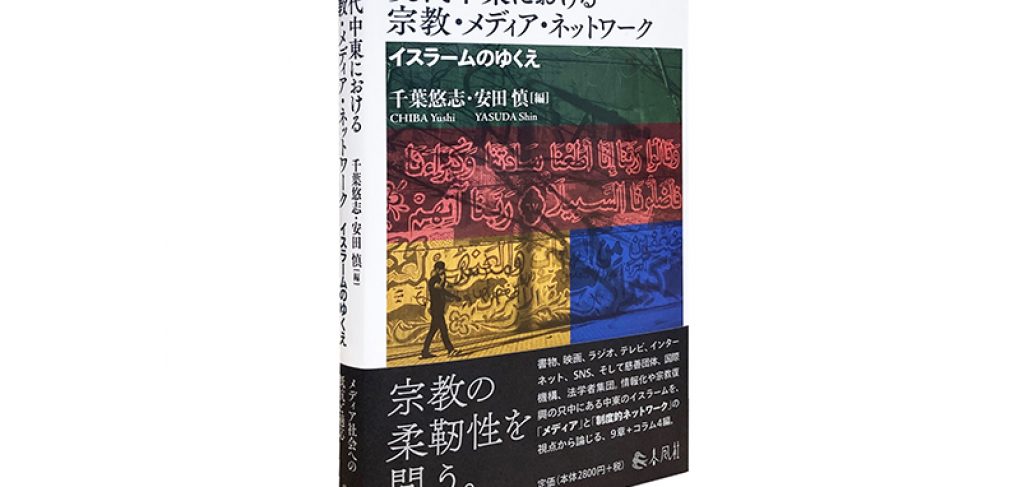病いと薬のコスモロジー
ヒマーラヤ東部タワンにおけるチベット医学、憑依、妖術の民族誌
- 長岡慶(著)/2021年3月
- 4000円(本体)/四六判上製416頁
- 装丁:中本那由子
病いとともに、いかにして生きるのか
二〇世紀後半からチベット医学は、専門資格化や薬の大量生産といった制度化が進んだが、そこでの医療実践は「伝統/近代」や「制度的医療/土着医療」のように断片化しているのではなく、それぞれの実践が部分的に重なり合い、医療・身体・環境が複雑に絡まり合っている。
伝統治療者、薬師、僧、村人、薬草、制度、神霊、インフラ。様々な人とモノが協働するなか、ヒマーラヤ東部のタワンの人々が経験する体の節々の痛み、胃炎、毒盛りや神霊による祟りといった病いと、そこであらわれている不確かで複数的な身体を、気鋭の人類学者がフィールドワークをもとに丹念に描く。
(ISBN 9784861107108)
本書が『フレグランスジャーナル』で紹介されました。
本書の書評が『アジア・アフリカ地域研究』に掲載されました
本書の書評が『宗教研究』に掲載されました
目次|contents
まえがき
凡例
序章
第Ⅰ部 チベット医学の開発
第1章 チベット医学の制度化とアムチ
第2章 チベット薬の標準化とタワンの人々
第Ⅱ部 ナツァの病いとチベット医学の実践
第3章 タワンの暮らしとナツァ治療
第4章 チベット医学の診療実践
第Ⅲ部 神霊と妖術における病いと薬
第5章 神霊ルーによる病いと開発
第6章 憑依と宗教薬
第7章 毒盛りと妖術と民間薬
終章
あとがき
参考文献
索引
お詫びと訂正
本文中に編集上の不手際で以下のような誤りが生じました。謹んでお詫びして訂正いたします。
『病いと薬のコスモロジー』正誤表
著者|author
長岡慶(ながおか・けい)
日本学術振興会特別研究員(CPD、関西大学)。専門は医療人類学、環境人類学、南アジア研究。主な著作に、Repairing Everyday Ruptures: Tibetan Medicine in Tawang, India. (Yogesh Raj ed. Ruptures and Repairs in South Asia Historical Perspectives. Martin Chautari、2013年)、「チベット医学の歴史的展開と東ヒマーラヤにおける実践」(小杉泰編『環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理』京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター:京都大学現代インド研究センター、2013年)、「神霊ルーをめぐるローカリティの再編――インド北東部モンパ社会の事例から」(岩尾一史・池田巧編『チベット・ヒマラヤ文明の歴史的展開』臨川書店、2018年)など。