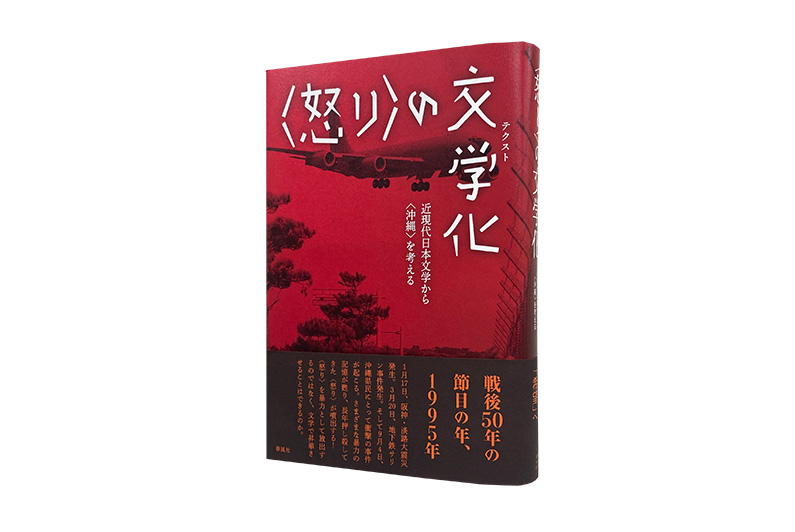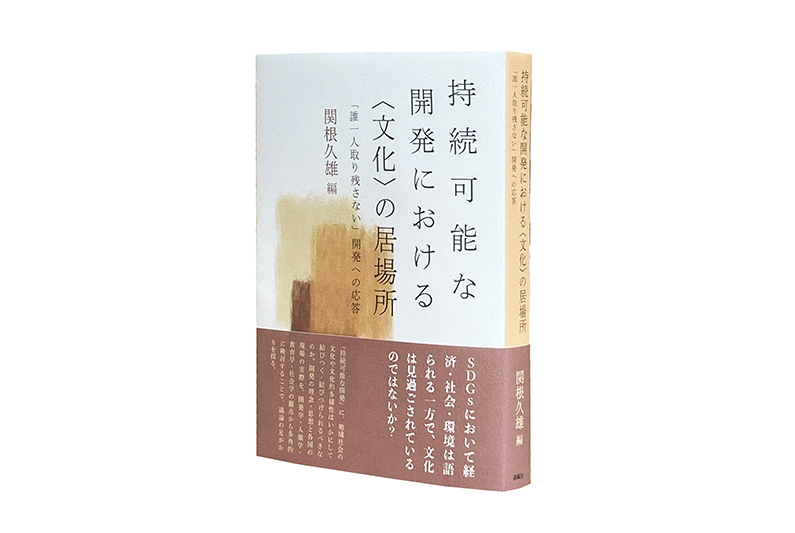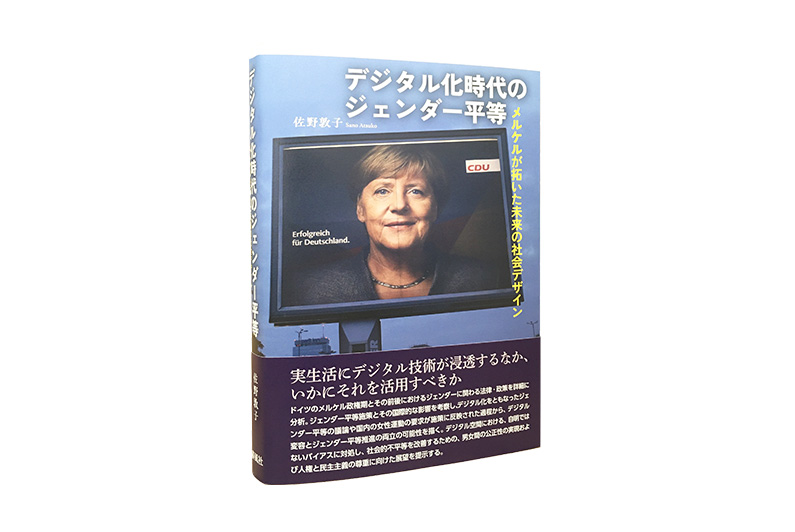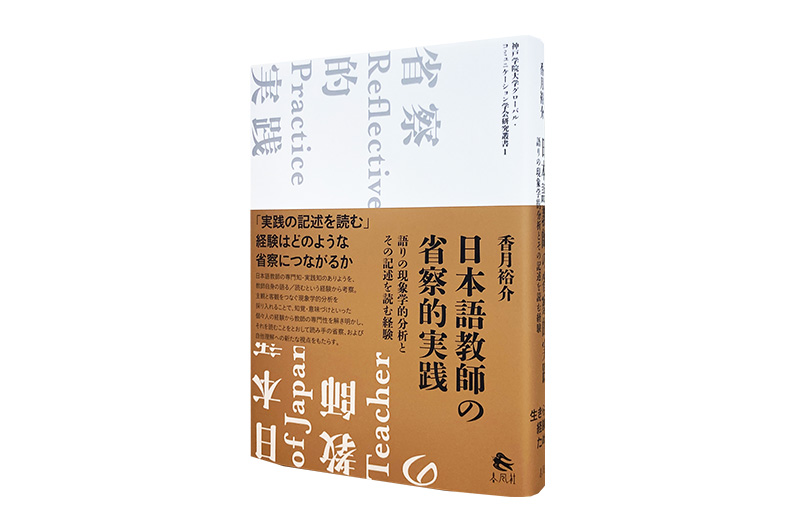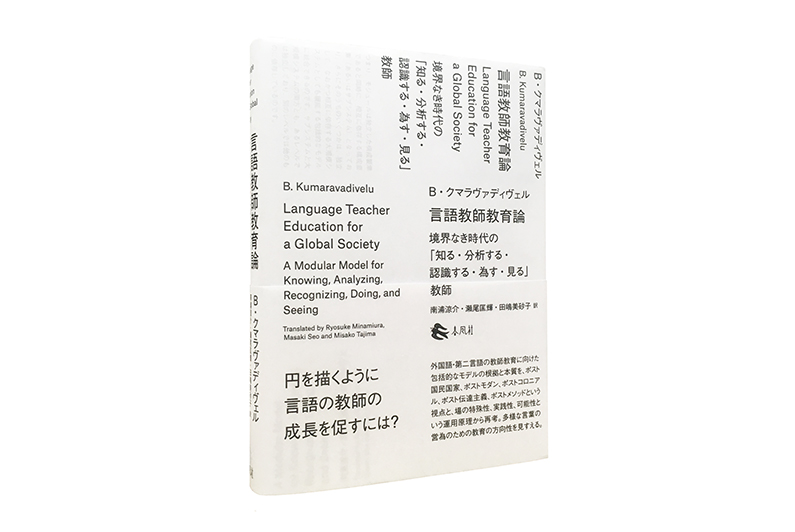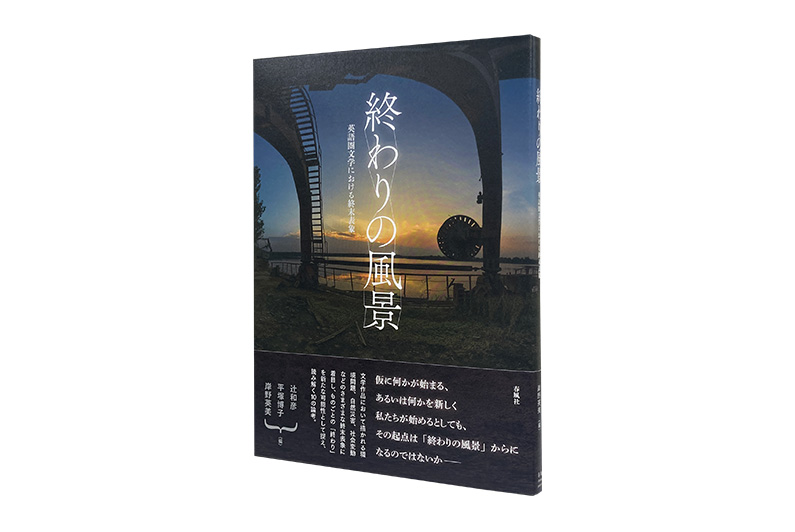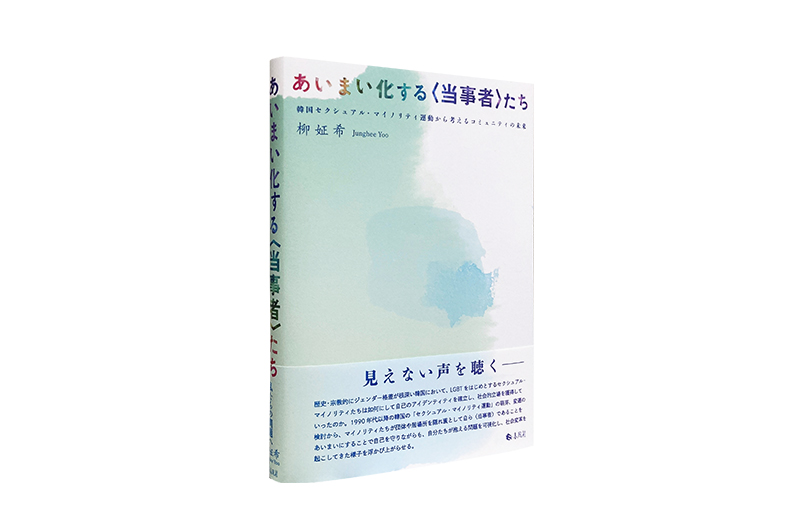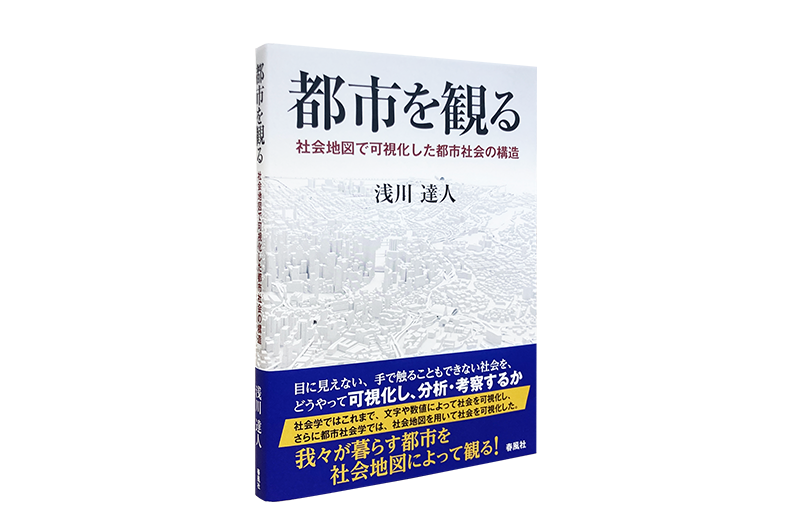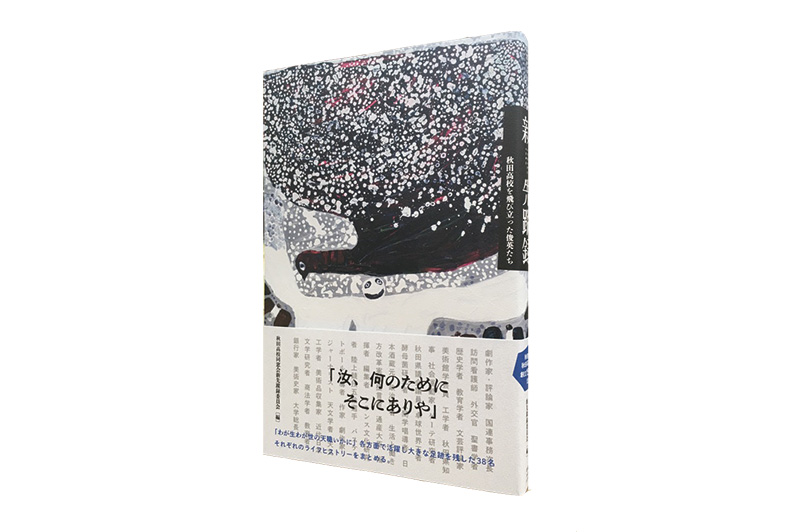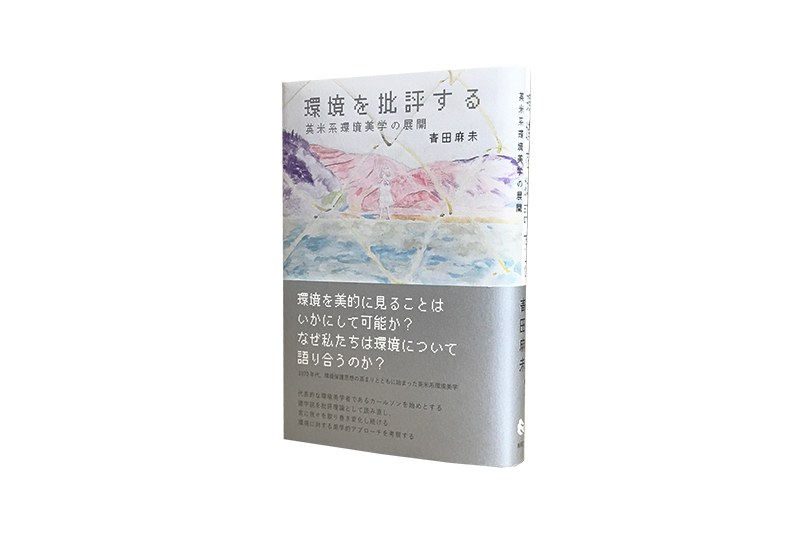立教大学ジェンダーフォーラム『ニューズレターGem』Vol. 49/2023年10月号で、佐野敦子著『デジタル化時代のジェンダー平等―メルケルが拓いた未来の社会デザイン』が紹介されました。「ジェンダー平等の実現は、人権と民主主義の体現」
■ニューズレター全文は、下記の同大学・ジェンダーフォーラム>刊行物よりご覧になれます。
[https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/gender/]
『異文化間教育』第58号(異文化間教育学会編/2023年8月)に、香月裕介著『日本語教師の省察的実践―語りの現象学的分析とその記述を読む経験』の書評が掲載されました。評者は大舩ちさと先生(国際交流基金ロンドン日本文化センター)です。「実践者の意識しないレベルの知を描き出すことにとどまらず、その記述を読む行為が読み手にどのような影響を与えるのかに注目し、読後の省察の語りを丁寧に解釈し記述した点で意義がある」
『異文化間教育』第58号(異文化間教育学会編/2023年8月)で、B・クマラヴァディヴェル著/南浦涼介、瀬尾匡輝、田嶋美砂子訳『言語教師教育論―境界なき時代の「知る・分析する・認識する・為す・見る」教師』が紹介されました。「省察という文脈知が強調される一方で、教員養成や研修の体系は学問体系知が網羅的に示されるように、双方の知は分離したままであることもまた多い。……こうした教師の文脈依存的な成長を促すためには、いかなる知をいかなる行為と結びつけていくかという視点から言語教師教育の知を再体系化」
『mr partner』No. 381(2023年9月)で、辻󠄀和彦・平塚博子・岸野英美編『終わりの風景―英語圏文学における終末表象』が紹介されました。「様々な「終末」モチーフを最新の研究によって論考する……文学研究の醍醐味と言える「最新の研究成果」は実に刺激的」
『図書新聞』2023年9月23日号に、柳姃希著『あいまい化する〈当事者〉たち―韓国セクシュアル・マイノリティ運動から考えるコミュニティの未来』の書評が掲載されました。評者は福永玄弥先生(東京大学)です。「本書をきっかけに韓国を対象としたクィア・スタディーズが日本でも盛んになることを期待する」
『日本都市社会学年報』第41号(日本都市社会学会編/2023年9月)に、浅川達人著『都市を観る―社会地図で可視化した都市社会の構造』の書評が掲載されました。評者は西村雄郎先生(広島大学)です。「社会空間構造分析は、地域社会、都市社会分析に有用な方法である。とすれば、この方法を適用するための前提的な議論を深める必要がある」
『秋田魁新報』2023年8月30日号で『新先蹤録―秋田高校を飛び立った俊英たち』が紹介されました。「親近感をもって読んでもらおうと現役で活躍する人材にまで対象を広げた」
また、弊社代表・三浦衛の寄稿記事「内と外との美しい調和」が併載されました。
◆秋田魁新報電子版ウェブサイトは下記よりご覧になれます。
https://www.sakigake.jp/
『環境を批評する―英米系環境美学の展開』(青田麻未 著)オンデマンド版が出来しました。オンデマンド版は、Amazonウェブサイトにてお求めになれます。
『昭和文学研究』第87集(昭和文学会/2023年9月)に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は尾西康充先生(三重大学)です。「作家たちは、自己の内部に渦巻く怒りを言葉にできないのはなぜか、という問いを繰り返し投げかけつつ、何も変わらないという「諦念」や「暴力の有効性を支える言辞の呪縛」から逃れようとして葛藤し続けてきた」