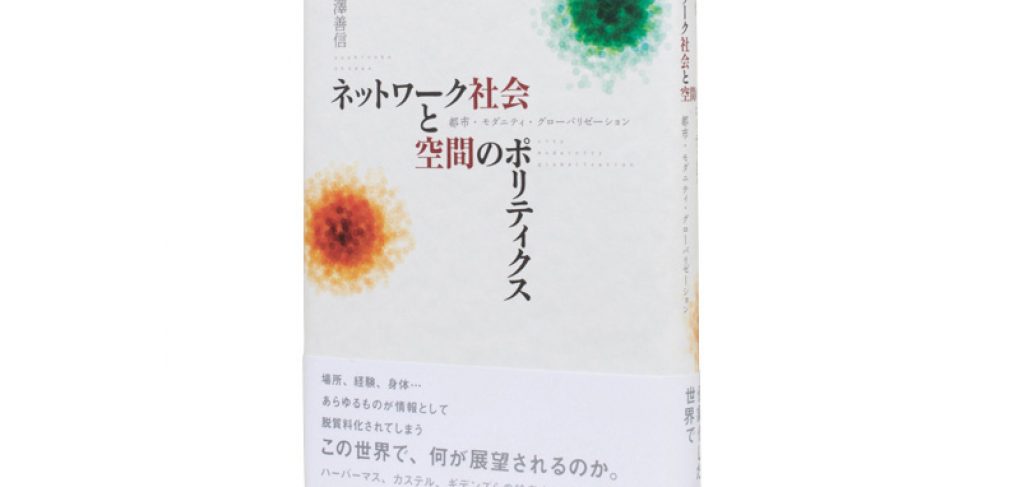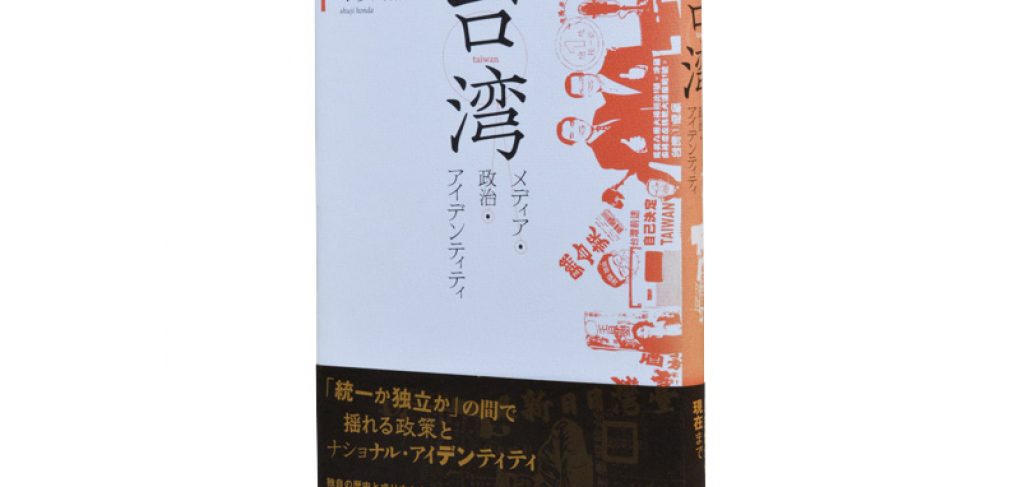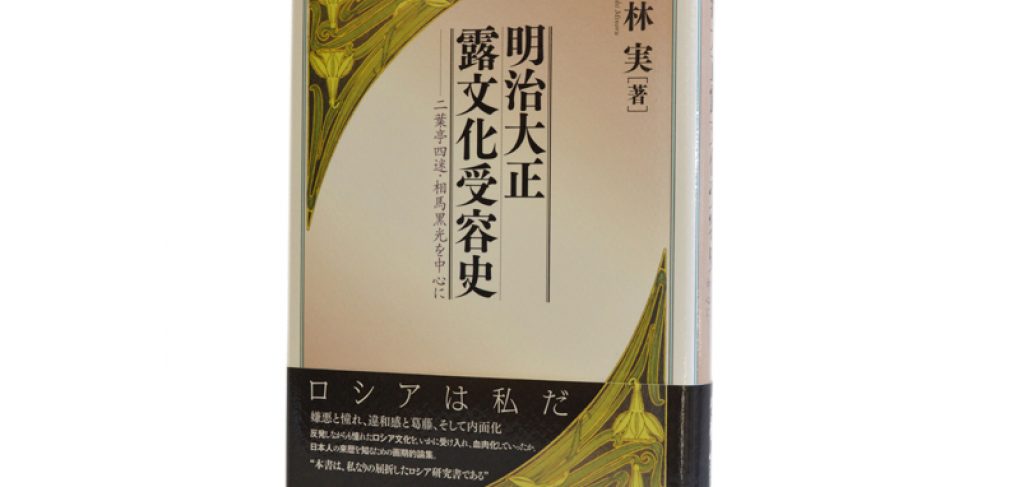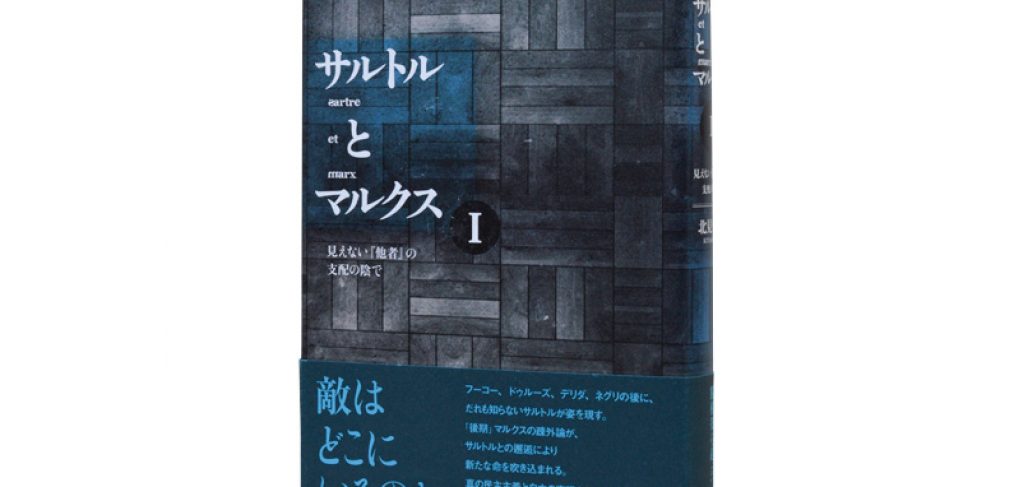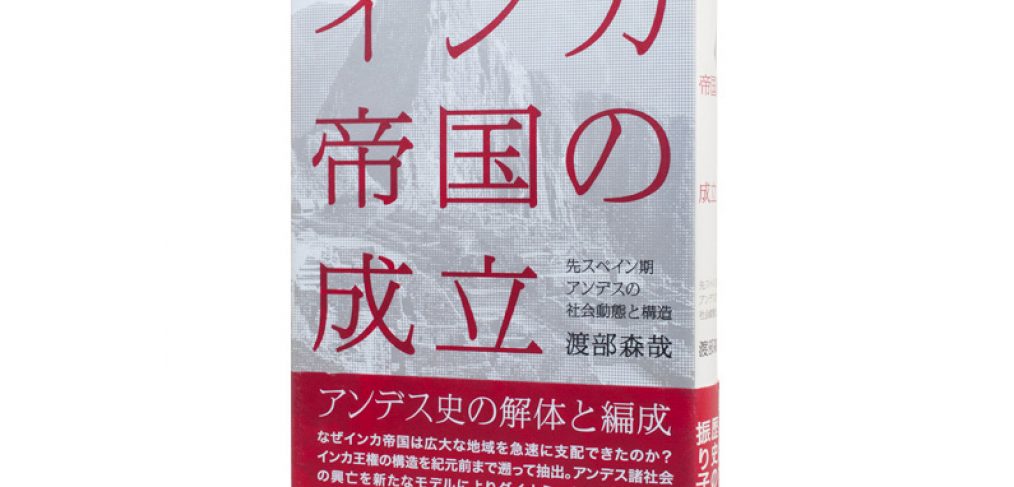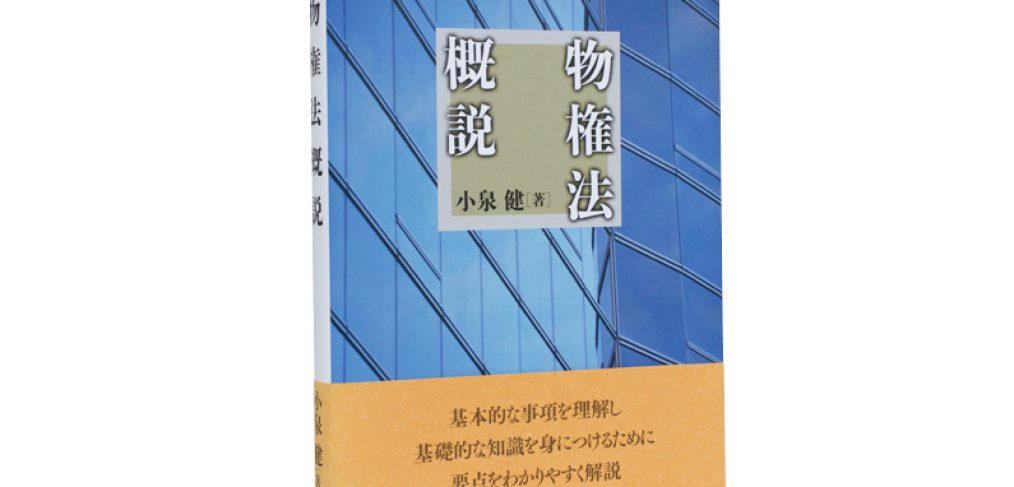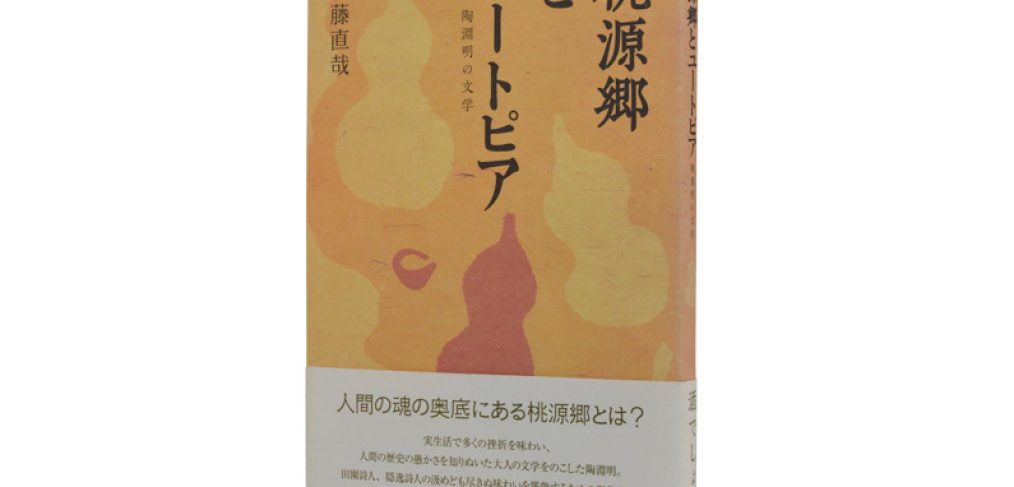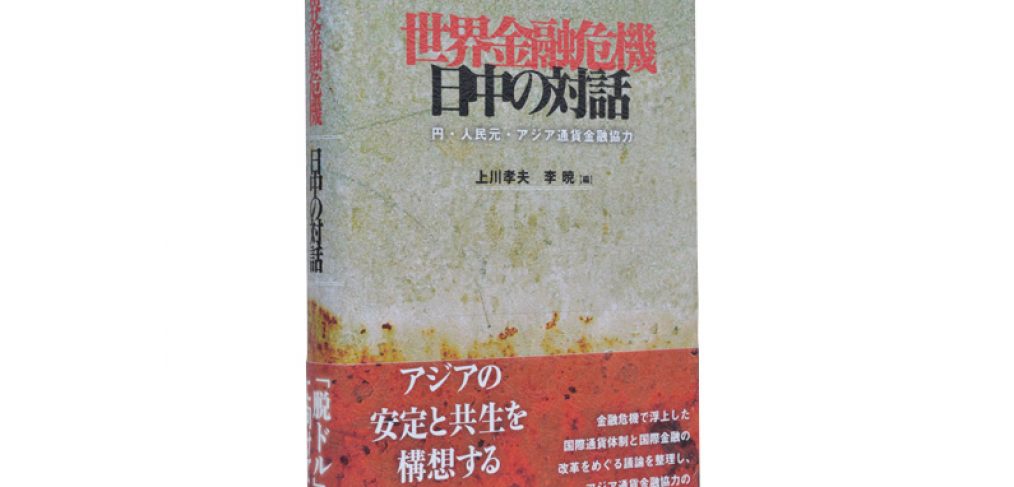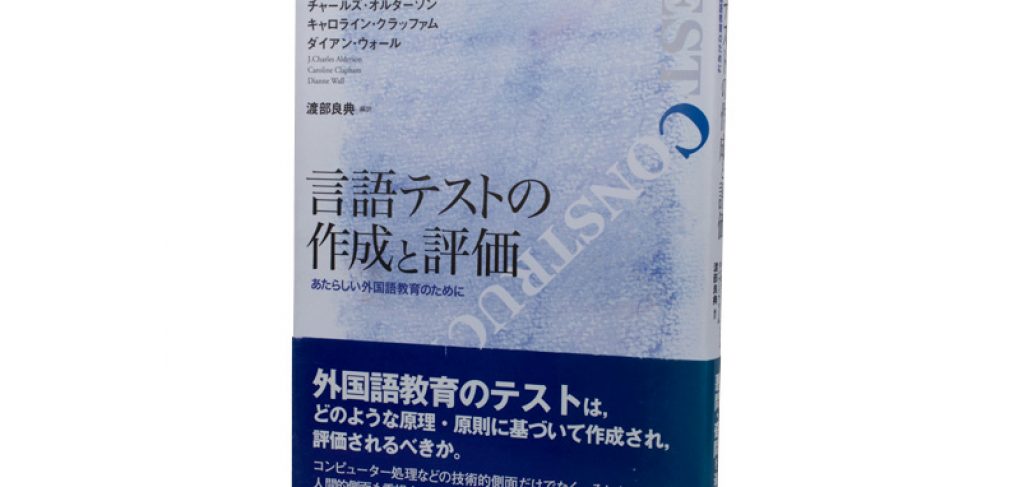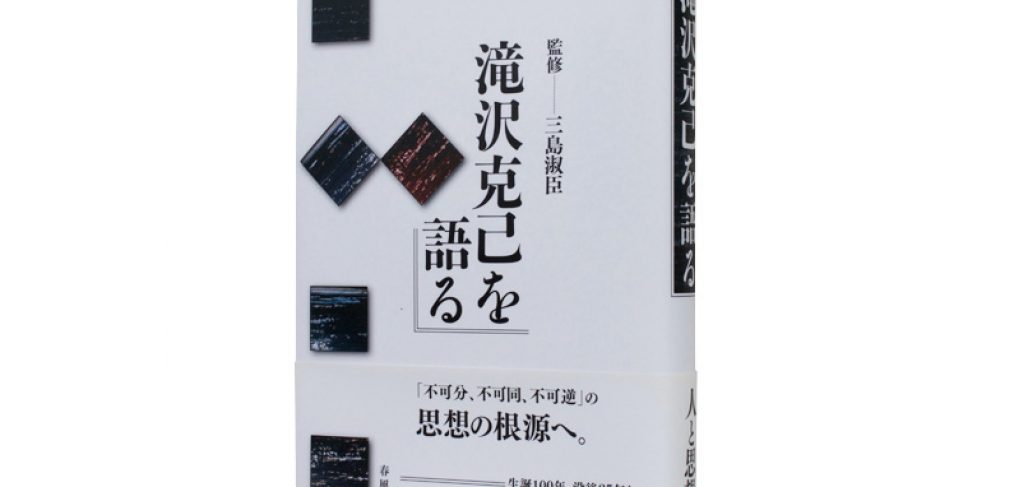言語テストの作成と評価
あたらしい外国語教育のために
- チャールズ・オルダーソン,キャロライン・クラッファム,ダイアン・ウォール(著)/渡部良典(編訳)/2010年2月
- 2800円(本体)/A5判・並製・276頁
- 装丁:難波園子
外国語教育のテストは,どのような原理・原則に基づいて作成され,評価されるべきか。コンピューター処理などの技術的側面だけでなく,それを利用する人間的側面も重視することで,テスト開発の方法を批判的に検討する。
(ISBN 9784861102011)
目次│indexs
第1章 本書の由来と概観
第2章 テスト細目の作成
第3章 テスト項目の作成と調整
第4章 事前テストの結果の分析
第5章 テスト採点者の訓練
第6章 試験官の信頼性検証
第7章 テスト結果の報告と合格点の決定
第8章 妥当性の検証
第9章 テストの事後報告
第10章 テストの開発と改訂
第11章 言語テストのスタンダード
著者│authors
チャールズ・オルダーソン(J. Charles Alderson)
ランカスター大学言語学科教授。オックスフォード大学修士課程,エディンバラ大学博士課程修了。言語学博士。Language Testingなど学術誌の編集主幹,DIALANGのコーディネーター,国際言語テスト学会会長を歴任。ケンブリッジ大学出版のテスト研究シリーズの編集主幹。言語テスト,リーディングに関する編著書,学術論文,口頭発表多数。2008年には長年にわたる貢献に対して国際言語テスト学会功労賞が授与された。近著にDiagnosing Foreign Language Proficiency(2006),Politics of Language Education(2009)等がある。
キャロライン・クラッファム(Caroline Clapham)
ランカスター大学修士,博士課程修了。言語学博士。ランカスター大学言語学科専任講師,ケンブリッジ大学シニア・レクチャラー歴任。The Development of IELTS: a Study of the Effect of Background Knowledge on Reading Comprehension(1996)など言語テストに関する論文著書多数。2009年12月永眠。
ダイアン・ウォール(Dianne Wall)
ランカスター大学シニア・レクチャラー。言語学博士。メキシコ国立自治大学修士。英国ランカスター大学修士課程修了。ランカスター大学で博士号取得。最も優れたテスト関係の博士論文に贈られるTOEFL賞を2001年度に受賞。現在TOEFLの影響の実証研究プロジェクトのチーフディレクターなど様々な活動を行っている。著書論文多数。近著にThe Impact of High-Stakes Testing on Classroom Teaching: A Case Study Using Insights from Testing and Innovation Theory(2005)がある。
編訳者│translator
渡部良典(わたなべ・よしのり)
1956(昭和31)年神奈川県生まれ。上智大学外国語学部教授。言語学博士。上智大学外国語学部卒業,同大学院修了,英国ランカスター大学修士,博士課程修了。聖霊女子短期大学,国際基督教大学,秋田大学などを経て現職。専攻分野は外国語の教育評価,授業研究。「入試から英語をはずすと授業は変わるか」,「学校のテストは何のために行うのか」,“Does grammar-translation come from entrance examinations?”(Language Testing),『〈実践〉言語テスト作成法』(大修館書店,共訳),『応用言語学辞典』(研究社,執筆担当),Washback in Language Testing: Research Methods and Contexts(共編著)など論文著訳書多数。Language Assessment Quarterly編集委員。
書評(「英語教育」5月号)
テスト開発のためのバランスの取れた手引き書
言語テスト研究者として最も著名な英国人であるといってよいCharles Aldersonらによる共著の編訳である。ここで「編訳」とは,著者の了解のもとに日本に直接当てはまらない部分や,原著の出版以降の言語テスト界の発展により必要性の薄れた内容を省略し,逆に読者の便を考えて欄外に重要事項の書き出しを追加するなど,訳者が積極的に「編集」を行ったことを指す。
この作業により95年に出版された原著のなかで15年の「時のテスト」に耐えた,すなわち現在もなお価値のある内容だけが精選され,これからも長く日本の読者の役に立つ著作になっている。
本書の特徴は,いたずらに理論やデータ処理のテクニカルな側面ばかりに焦点を当てず,テスト作成にあたっての心構えや,結果の解釈にあたって留意すべき点など「人間的側面」をも詳述している点にある。読みやすくかつ内容の充実した,テスト作成および評価の手引き書と言って良いだろう。
章立ては,「テスト細目の作成」「テスト項目の作成と調整」「事前テストの結果の分析」「テスト採点者の訓練」「試験官の信頼性検証」「テスト結果の報告と合格点の決定」「妥当性の検証」「テストの事後報告」「テストの開発と改訂」「言語テストのスタンダード」と,開発過程の時系列にそって構成されており,過不足がない。
訳者は,本書を読めばテストについて「理性的な判断に基づいて批判検討」ができるようになり,「1ページ読めばそれだけ確実に知識が増す」としているが,その言葉に偽りはない。評者自身,かのAldersonがこのように喝破していたかと再認識させられる記述をいくつも見つけることができた。
曰く「理想的なテスト項目作成者とは,対象受験者と同じ環境で同じような背景をもった学習者を教えたことのある教員である」「英語を正確に発音できる能力と発音のテストに正しく答えられる能力にはまったく相関がない」「定期的に同じ受験者テストを行う場合はテスト方法を変え,予測できないようにするのがよい」「指示文は受験者の母語で書くことが望ましい」「4つの選択肢を作るのが無理な場合は3つにしておくのが無難である」「受験者が実際にどのような解答を行うかは実施するまでわからない」等々。
最後に,類のないほど訳文が自然で読みやすいことを指摘したい。ランカスター大学で直にAldersonの薫陶を受けた訳者が師の教えを完全に消化吸収した上で日本語化した結果であろう。
テストに関して論文を書こうとしている学生,入学試験や実力テストを作成する委員会のメンバーはもちろん,定期テストを作らねばならぬ中学・高校教員にも是非読んで欲しい一冊である。
(埼玉大学教授 靜哲人)
※この書評文は大修館書店「英語教育」編集部の許可を得て転載しています。
この本を注文する
Amazonで注文する Hontoで注文する 楽天ブックスで注文する