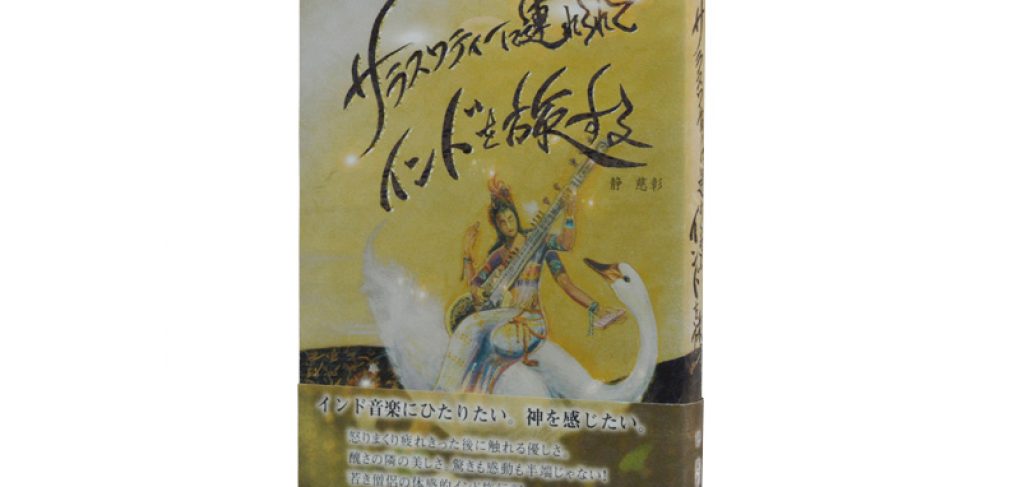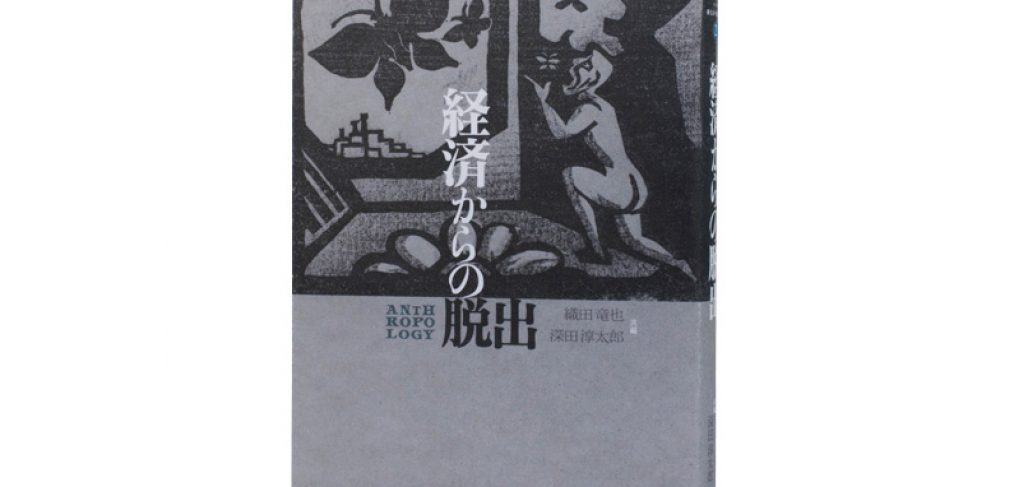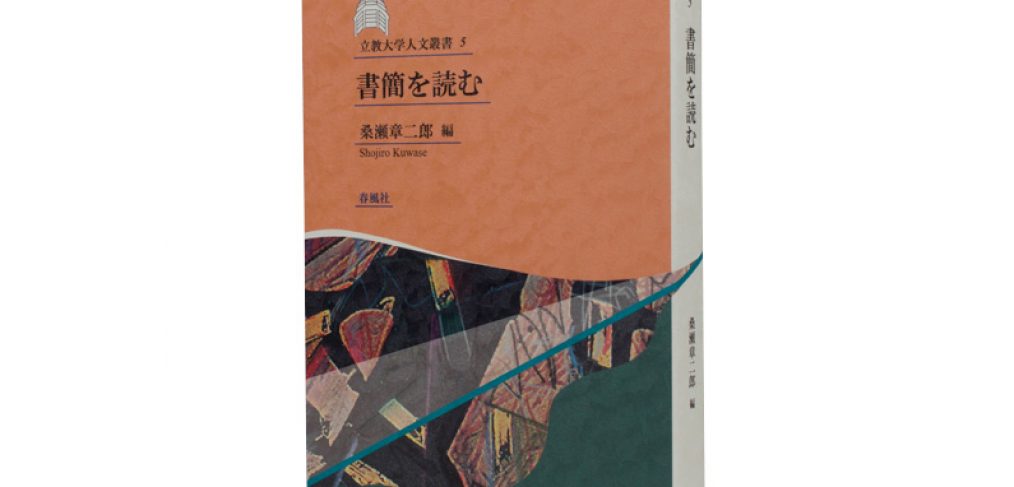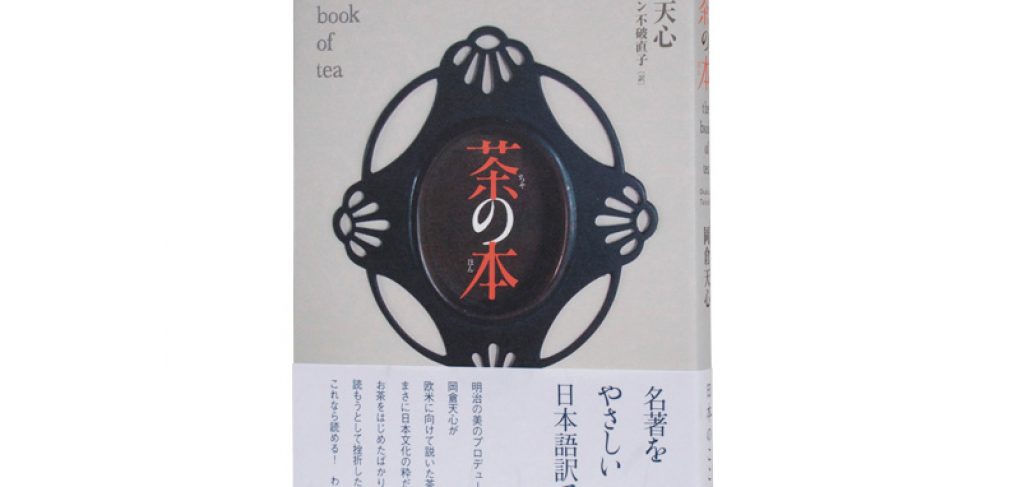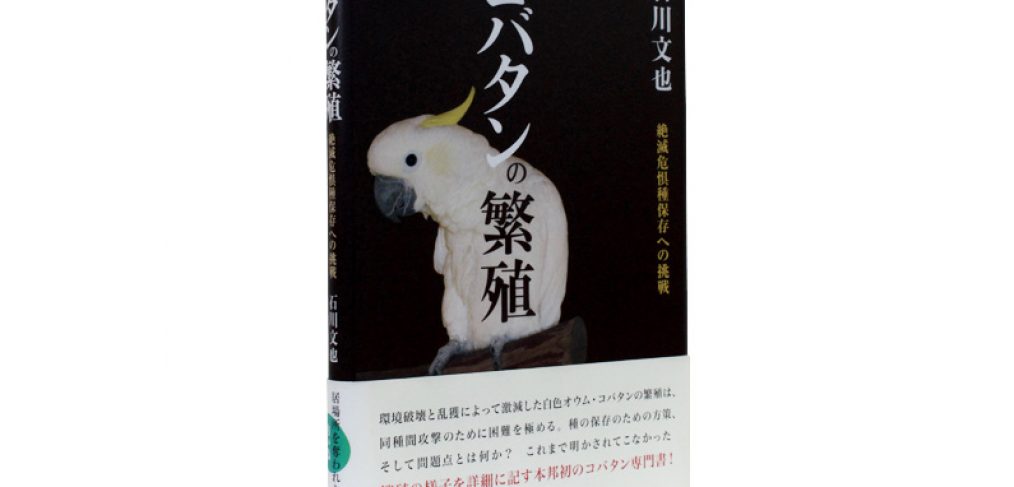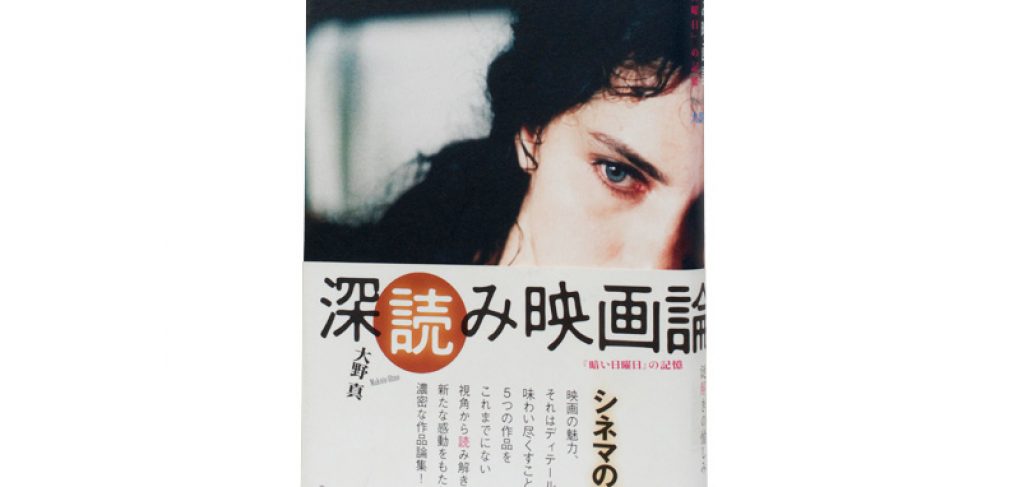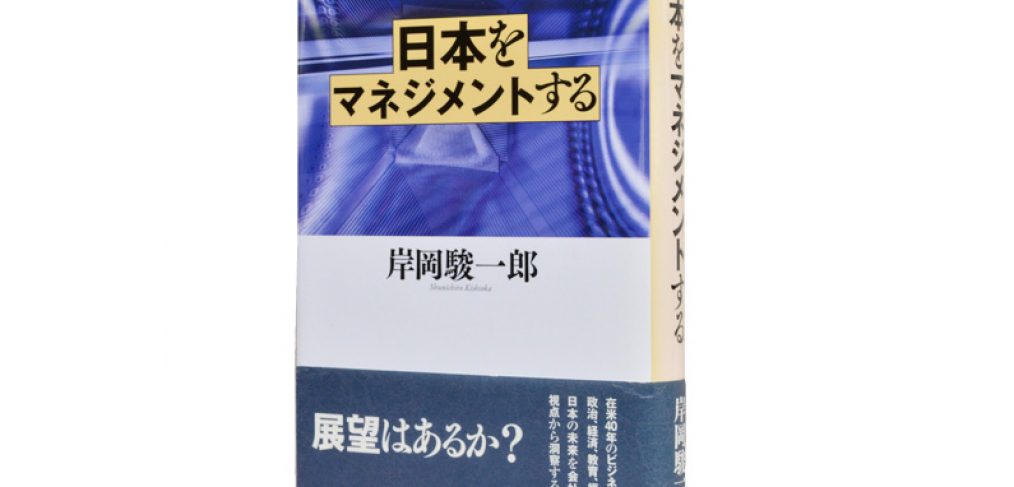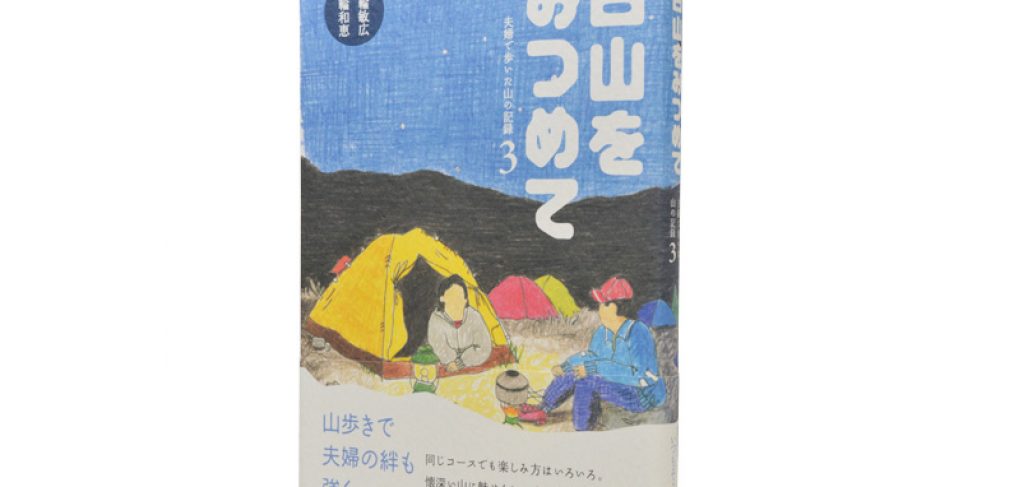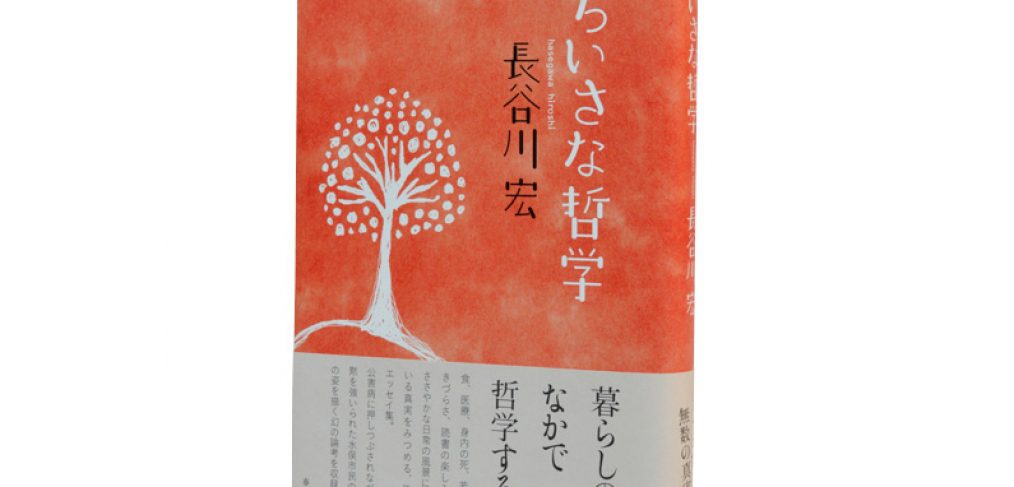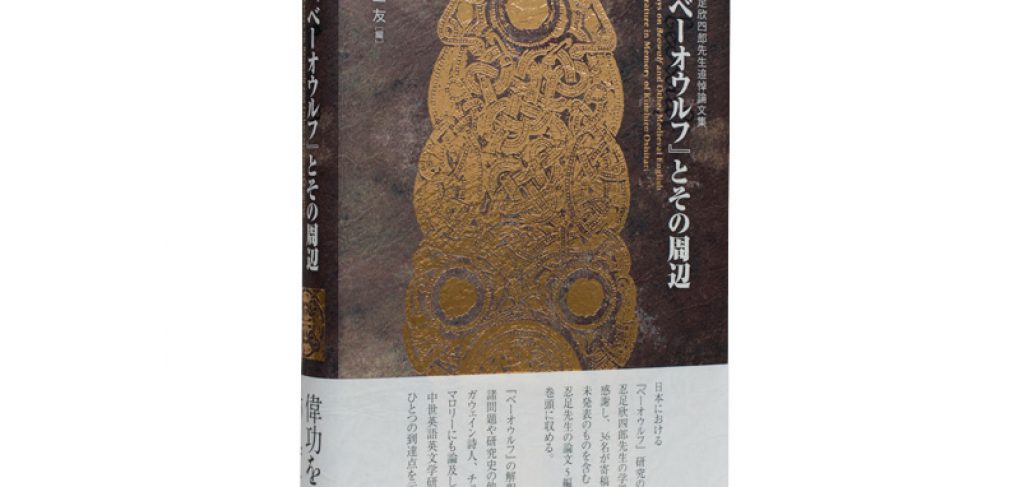サラスワティーに連れられてインドを旅する
- 静慈彰/2010年1月
- 1500円(本体)/四六判・並製・256頁
インド音楽にひたりたい。神を感じたい。ロックな坊主がインドを旅して見つけたものとは? 怒りまくり疲れきった後に触れる優しさ。醜さの隣の美しさ。驚きも感動も半端じゃない! 若き僧侶の体感的インド旅行記。
(ISBN 9784861101960)
目次|indexs
それは西からやってきた
インドが呼んでいる/インド日和/ムンバイー/聖者とコンサート/夢行列車/アウランガーバードの教訓
雑踏の中の神々
アジャンターの神々/エローラの宗教/雑踏のハイダラーバード/南へ/チェンナイの信仰/インドに迷い込む/修行するのだ!/ヴィパッサナー
南インドの風
バスこりごり/プリスバティー寺院/信仰と共に生きる/シュリー・ミナクシー寺院/ミナクシーの歓迎/アーユルヴェーダ/カンニャークマーリーの風/いざ、北上!
嵐の北インド
北の衝撃/ヴリンダーヴァンへ逃れる/宗教のるつぼ/アーグラーの世界遺産/旅人、ガンジスに至る/神の子
ライヴ! ライヴ! ライヴ!
バースディ・コンサート/ザキール降臨!/孤高のダンサー/求めよ、さらば与えられん/光と影/手紙/伝説の吟遊詩人
奇跡の音楽
ムンバイー再訪/青空/神の歌/コンニャク・ソング/サラスワティーの饗宴/愛の別れ道/たどり着けば、コールカーター/monoj/ラーマクリシュナの啓示/カーリー女神の祝福
久遠の未来へ
最後の旅/仏陀の里/ホーリー/旅の終わり/さらばインド
※インド音楽についてのコラムあり
著者|author
静慈彰(しずか・じしょう)
1978年、和歌山県高野山生まれ。
私立洛南高等学校、京都府立大学国際文化学科卒業。
2008年まで高野山大学大学院密教学専攻博士課程在籍。
2003年-2006年、真言宗海外布教師として、ロサンゼルス別院、シアトル仏教会勤務。阿字観瞑想会を指導、Loyola College、 世界宗教会議(American Academy of Religion)にて声明公演を行う。他、アメリカ最大のレイヴ「バーニングマン」にて護摩供を厳修、本堂にてロックコンサート「仏教ライヴ!」を行うなど、先鋭的な活動を展開する。
2007年夏、高野山にて野外フェス「大音楽集会(だいおんらくしゅえ)」主催。
2008年1月26日、渡印。
2009年、「東京ヴィパッサナー瞑想道場」開講。