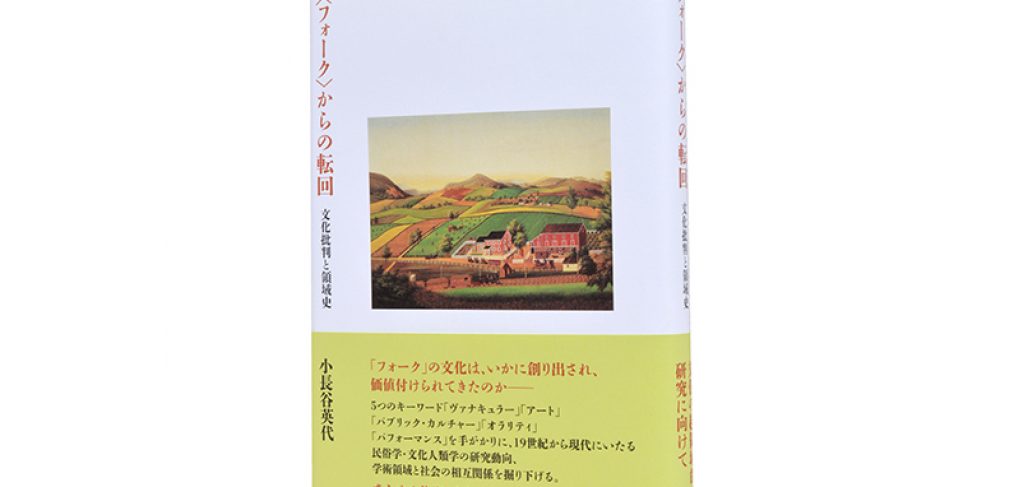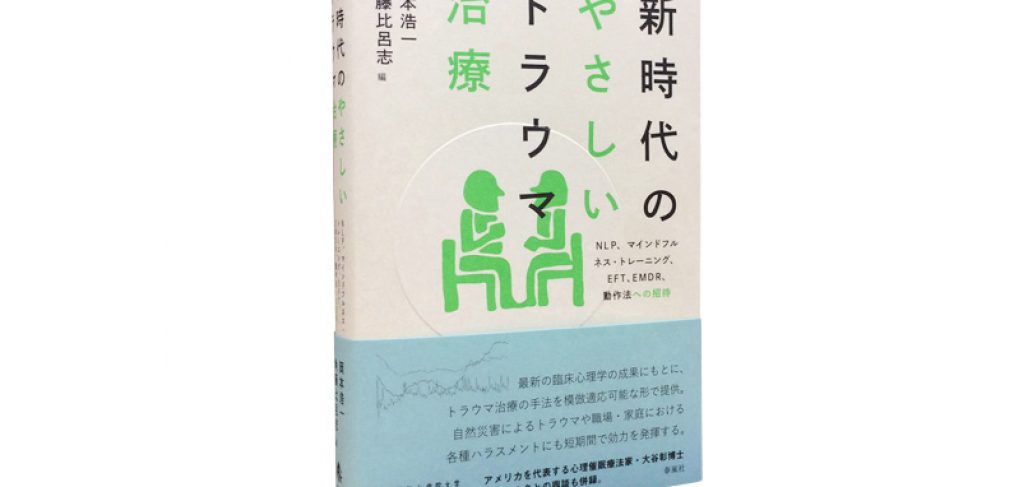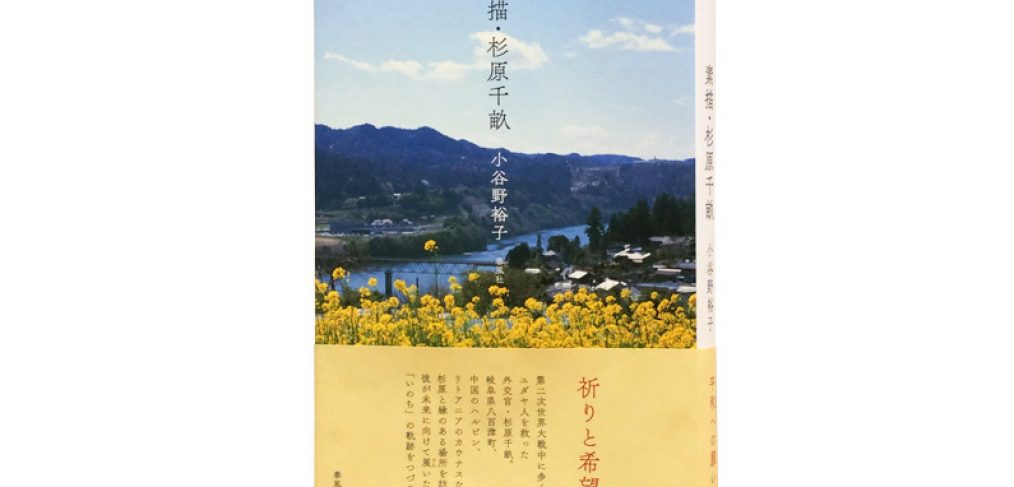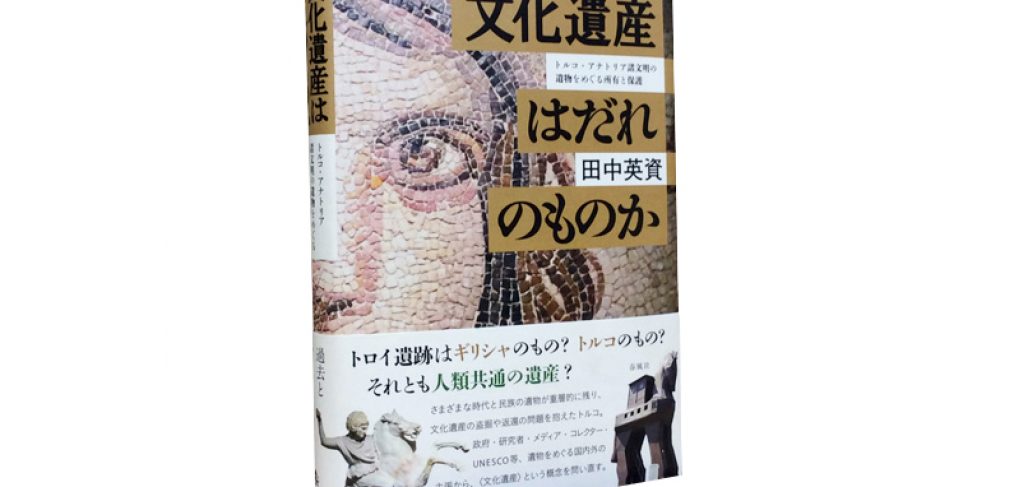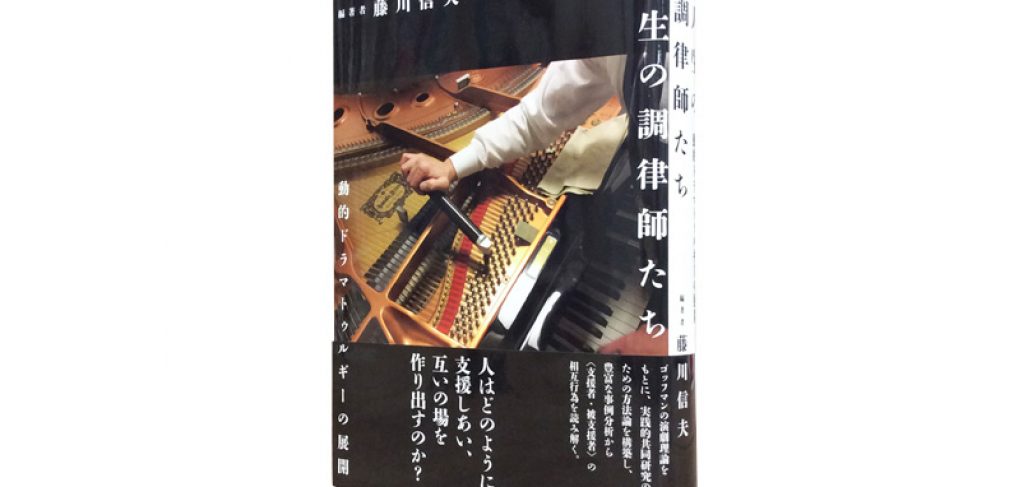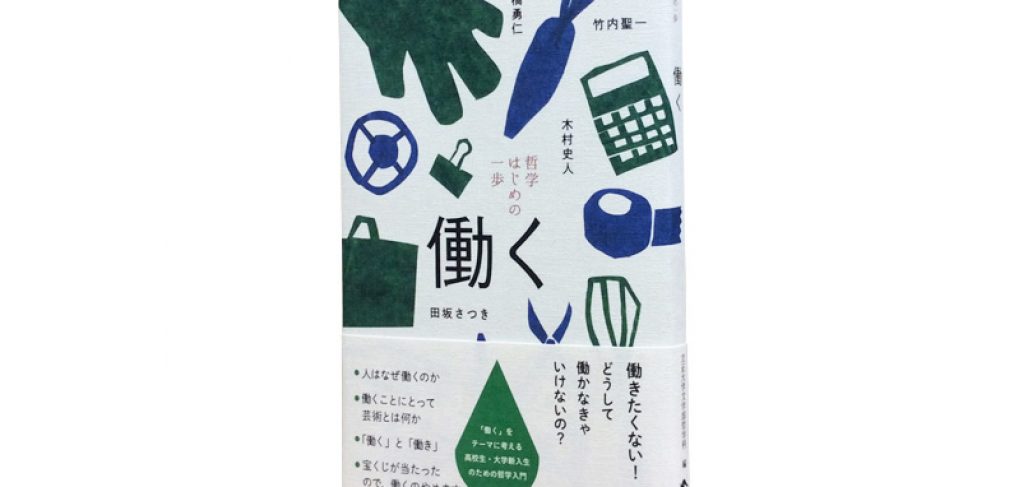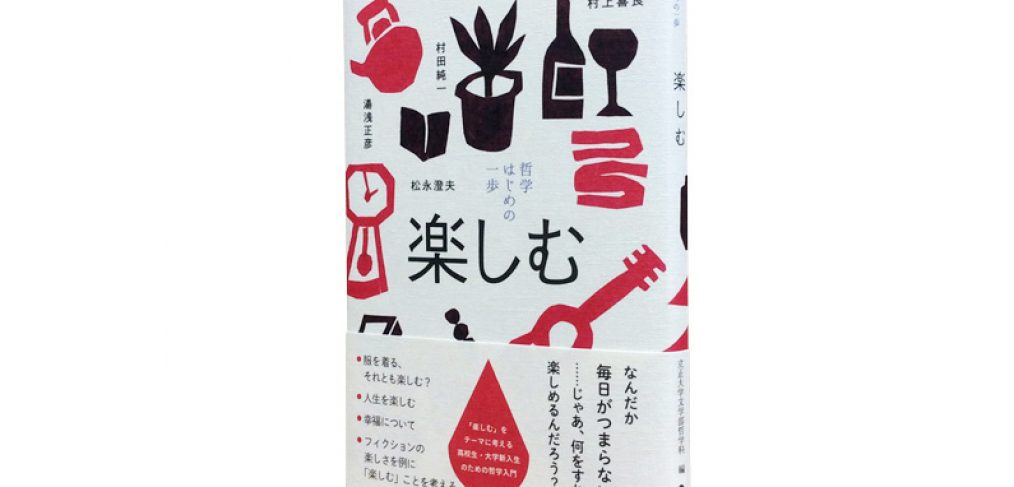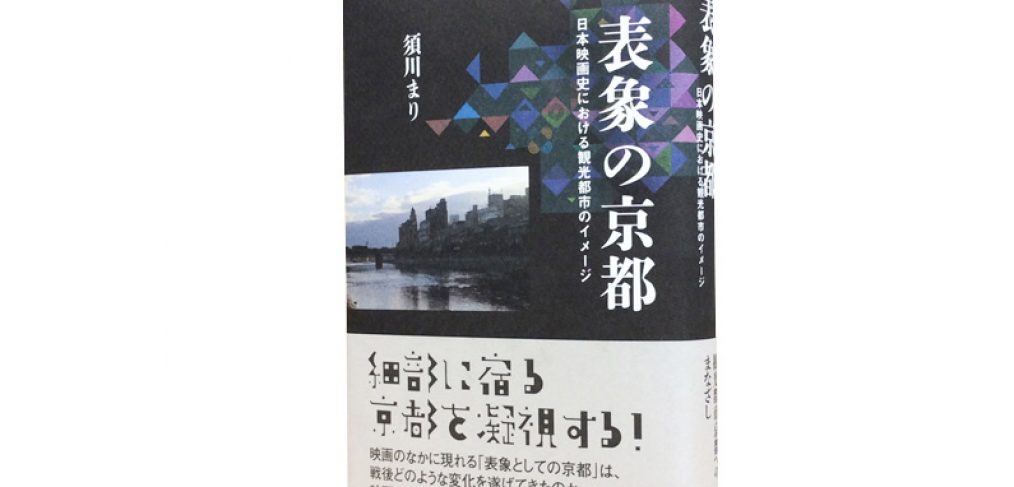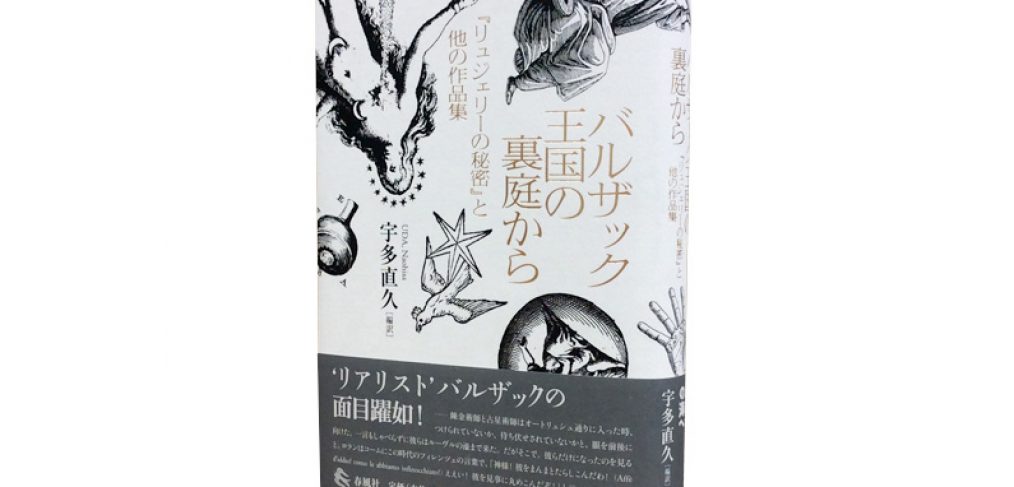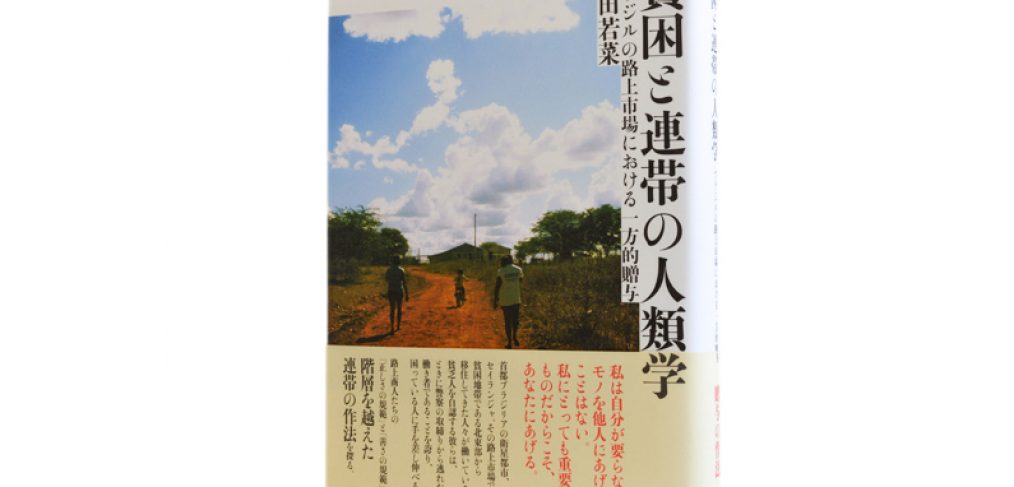〈フォーク〉からの転回
文化批判と領域史
- 小長谷英代(著)/2017年4月
- 4300円(本体)/四六判上製216頁
- 装丁:長田年伸
アメリカ独自の「フォーク」は、どう見いだされ、位置づけられてきたか?
「ヴァナキュラー」「アート」「パブリック・カルチャー」「オラリティ」「パフォーマンス」
という5つのキーワードから、19世紀から現代にいたる民俗学・文化人類学の研究動向、
美学・美術史学など「文化」を扱う隣接分野との関係、そして学術領域と社会の相互関係を掘り下げる。
(ISBN 9784861105357)
目次|indexes
まえがき
1 「ヴァナキュラー」―「文化」への超領域的視点
2 「アート」―「フォーク」と「プリミティヴ」の展示、学術領域、社会運動
3 「パブリック・カルチャー」―アメリカ的「フェスティヴァル」の系譜とスミソニアン
4 「オラリティ」―アメリカの「バラッド」における「他者」とナショナリズム
5 「パフォーマンス」―「ポスト」領域の民俗学
あとがき
事項索引・人名索引
著者|author
小長谷英代(こながや・ひでよ)
ペンシルヴァニア大学大学院・人文科学科卒業。Ph.D。
現在、早稲田大学・社会科学総合学術院・教授。
専門:文化人類学・民俗学、カルチュラル・スタディーズ
主著:『アメリカ民俗学−歴史と方法の批判的考察−』(岩田書院)(共編訳)、Manly Traditions: The Folk Roots of American Masculinities. (Indian Univ. Press)(共著)、他。