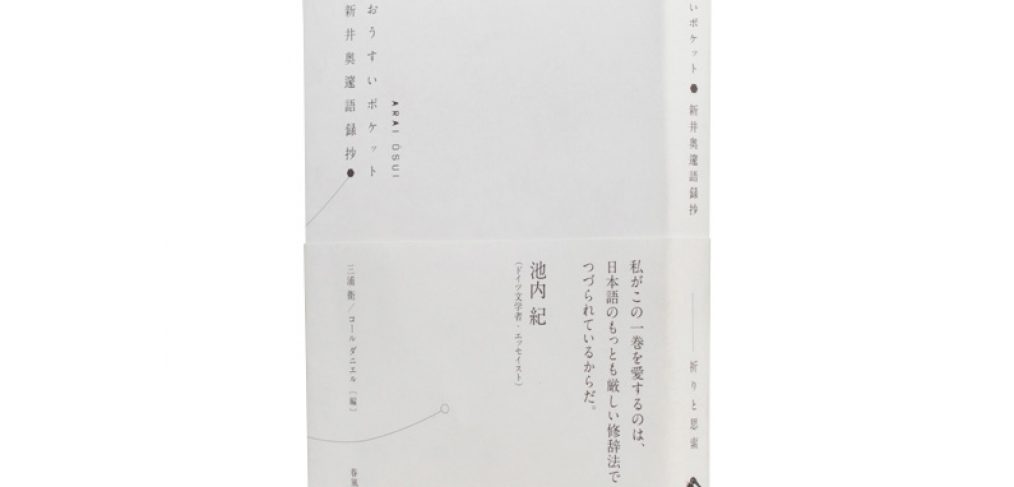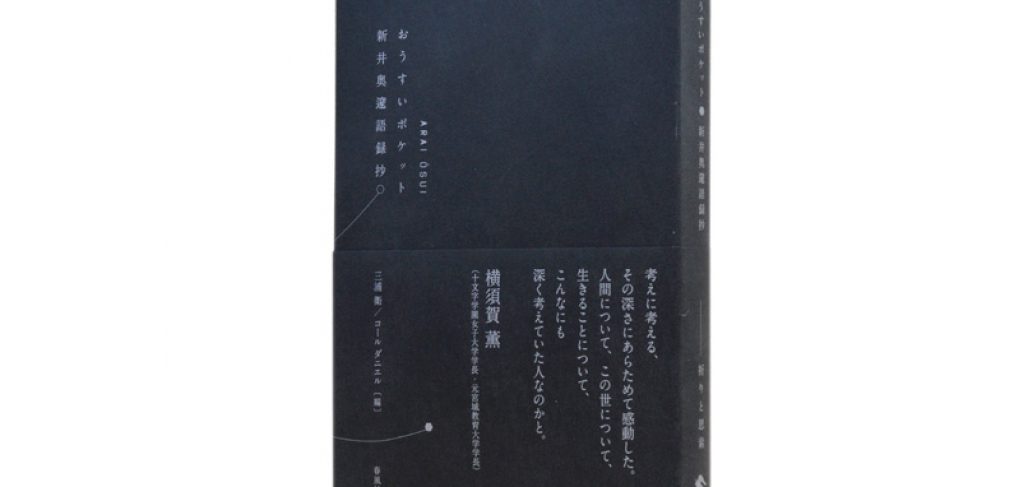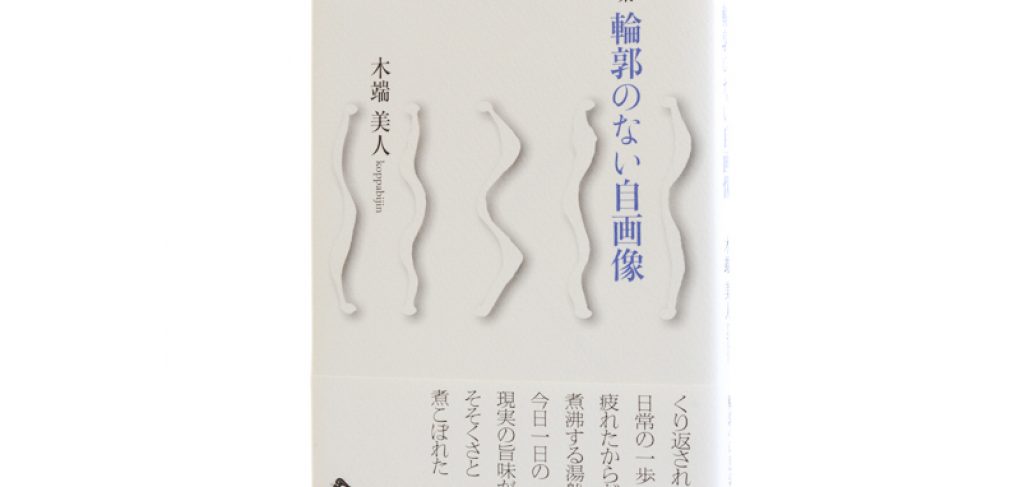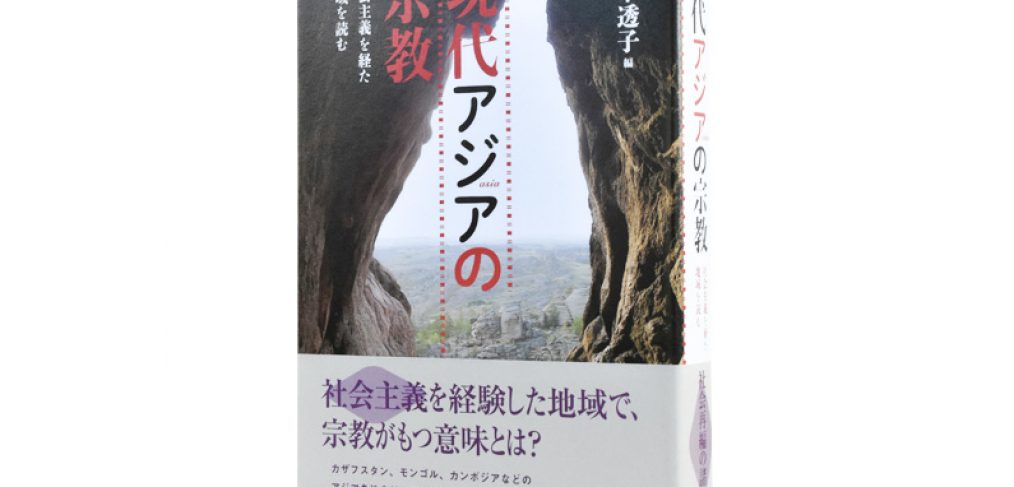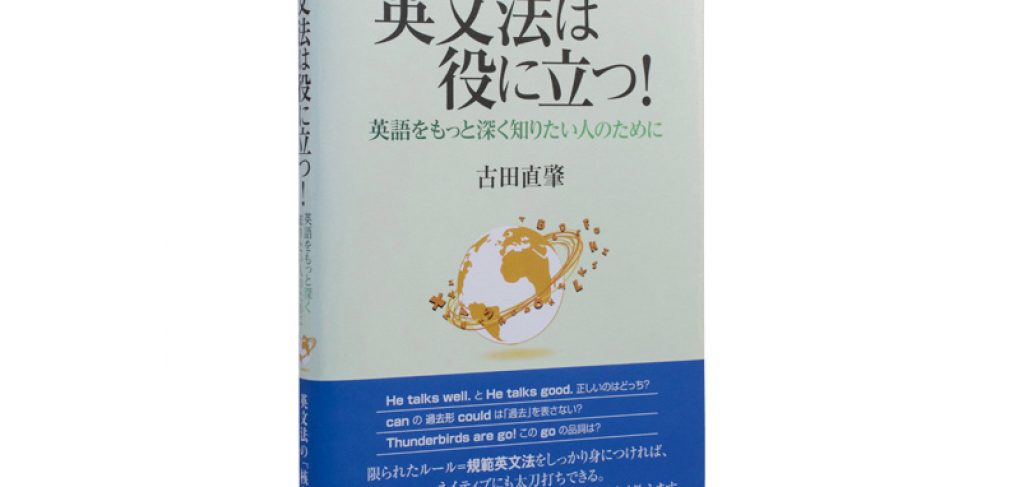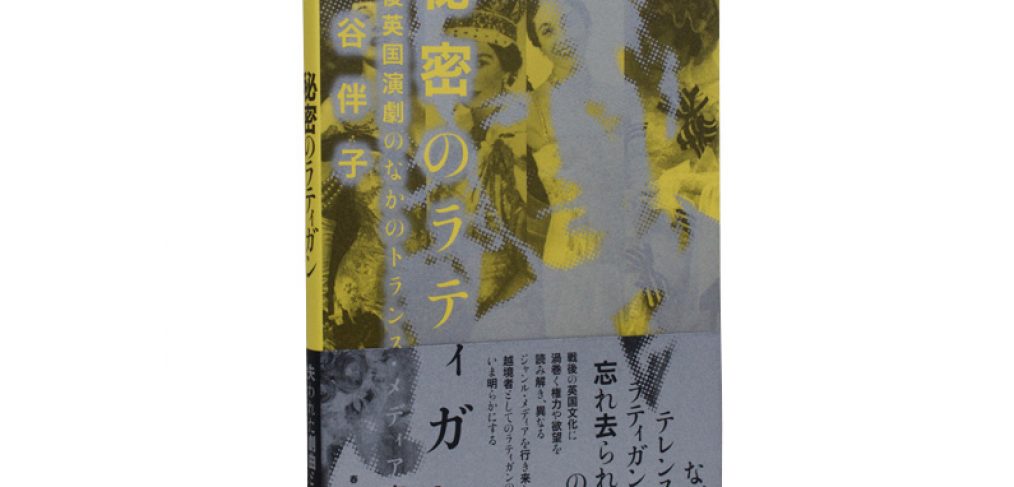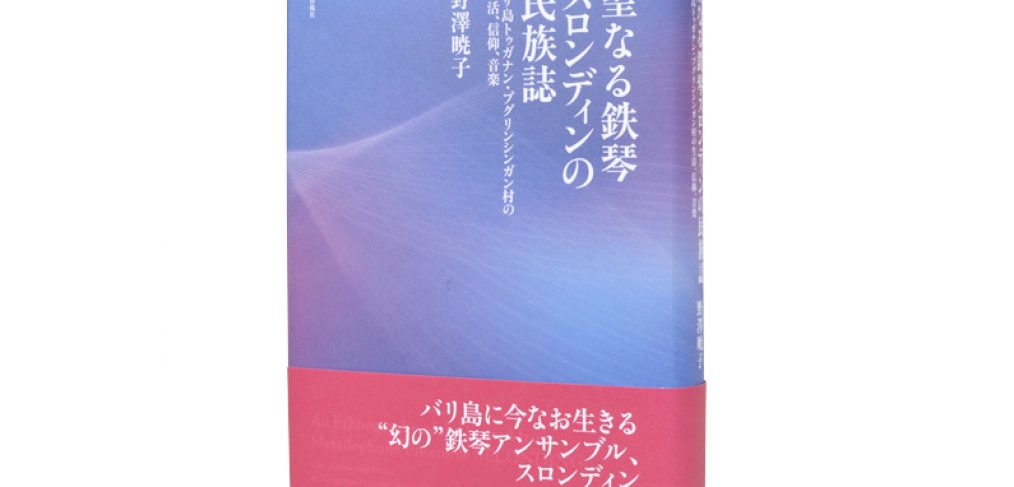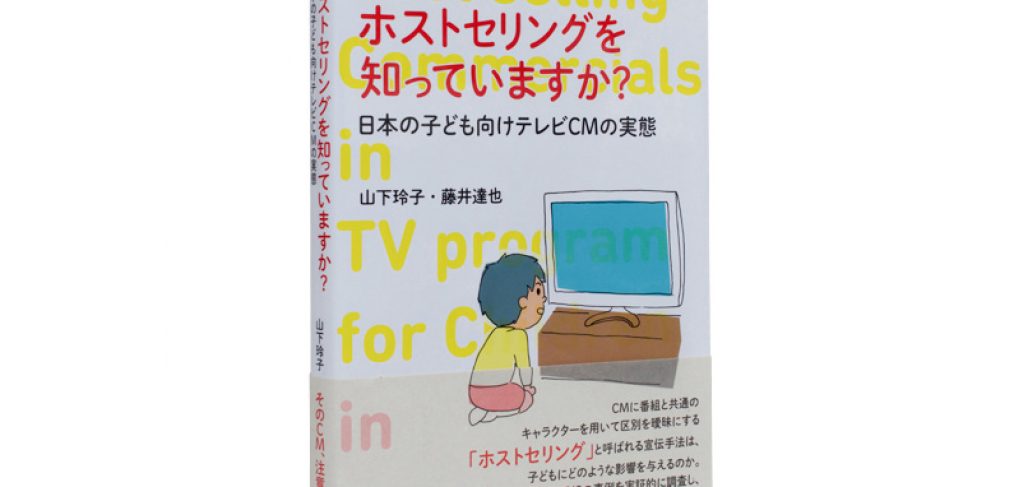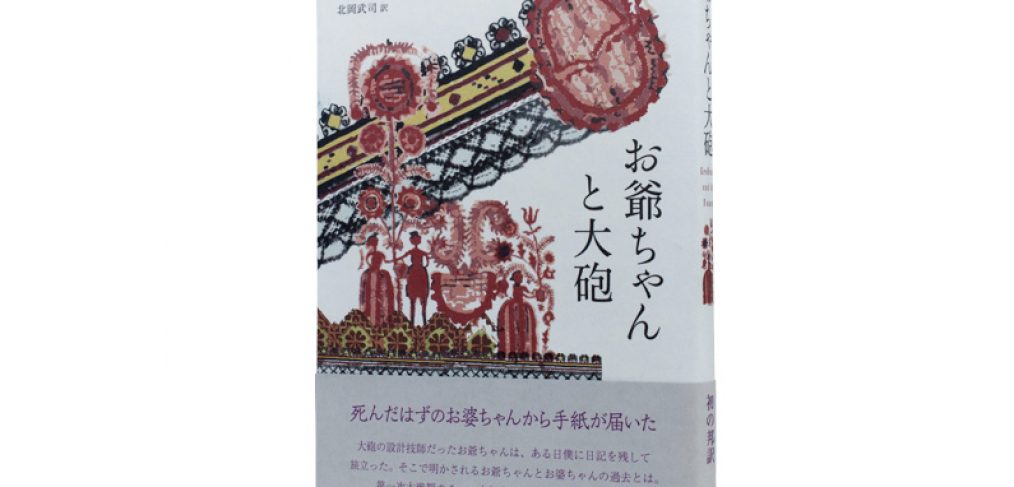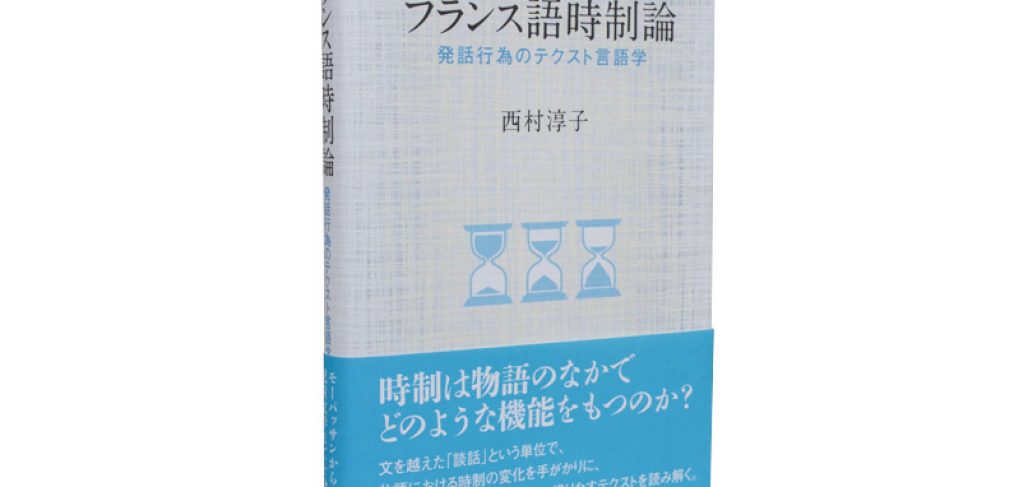おうすいポケット
新井奥邃語録抄 白表紙
- 三浦 衛・コール ダニエル(編)/2015年6月
- 2200円(本体)/四六変型判・320頁
- 装丁:矢萩多聞
「私がこの一巻を愛するのは、日本語のもっとも厳しい修辞法でつづられているからだ」(池内紀)
田中正造が「亜聖」と評し、高村光太郎が愛読し、「全一学」の哲学者森信三が「わが幻の師」と敬仰した“いのちの思想家”新井奥邃。
現代日本をうがつ珠玉の語録を全集より精選し、キーワードに語釈を付す。
巻頭言、池内紀氏。語録本文は黒表紙と同じ。
(ISBN 9784861104541)
★好評既刊★
『奥邃論集成』 (春風社編集部 編)
『新井奥邃著作集』全9巻+別巻(工藤正三・コール ダニエル 編)
新井奥邃とは?
1846(弘化3)年、仙台藩に生まれる。本名は常之進《つねのしん》安静《やすよし》。
若い頃より秀才の誉れが高く、6歳で藩校の養賢堂に入学、1866年に江戸に遊学し安井息軒の三計塾に入門、学を磨いた。
1871年、森有礼の知遇を得、キリスト教を深く学ぶため、森に伴われ渡米。
トマス・レイク・ハリスのコミュニティ新生同胞教団に入団、生活しながら特色のあるキリスト教を学ぶ。1899年に帰国。
奥邃に親炙また私淑した人物に、田中正造、高村光太郎、柳敬助、野上弥生子、森信三、林竹二らがいる。
編者|editors
三浦衛(みうら・まもる)
春風社代表取締役。1957年秋田県生まれ。東北大学経済学部卒業後、神奈川県内の私立高校で社会科教諭を7年間務める。
その後、東京都内の出版社に勤務。99年、仲間二人と春風社を創業。学術書を中心に現在まで約600点を刊行。
コール ダニエル(Daniel E. Corl)
福岡女学院大学教授。1953年生まれ、岩手育ち。日本在住44年。
関心分野はキリスト教思想史、宗教哲学、異文化表現史。
著書に『知られざるいのちの思想家 新井奥邃を読みとく』(共編著、春風社 2000年)、『新井奥邃著作集』全9巻+別巻(共編, 春風社 2000-2006年)、『公共する人間5 新井奥邃 公快共楽の栄郷を志向した越境者』(共編著、東京大学出版会 2010年)がある。