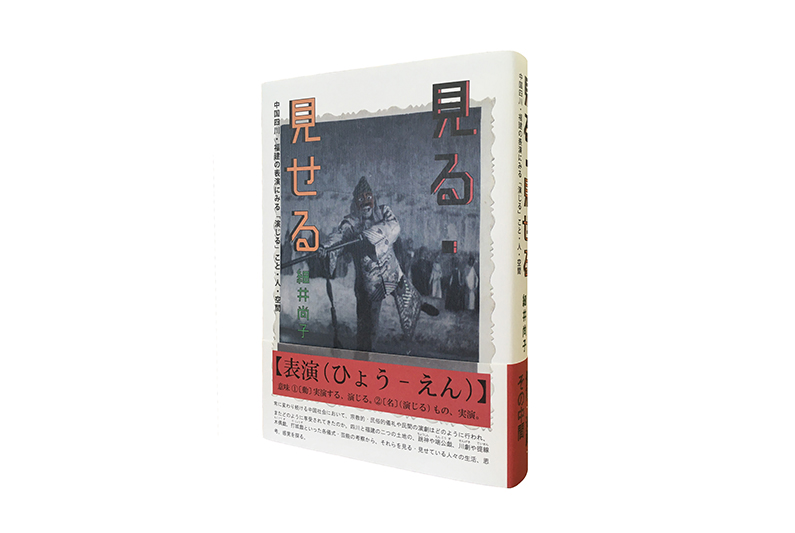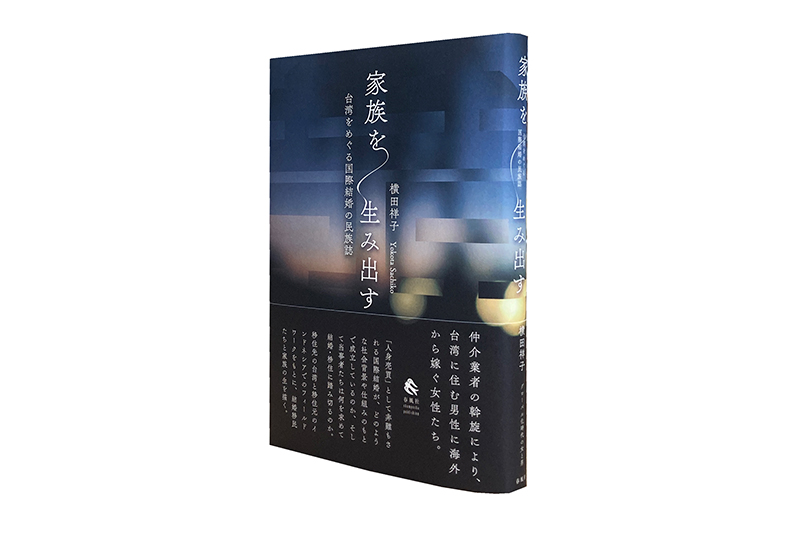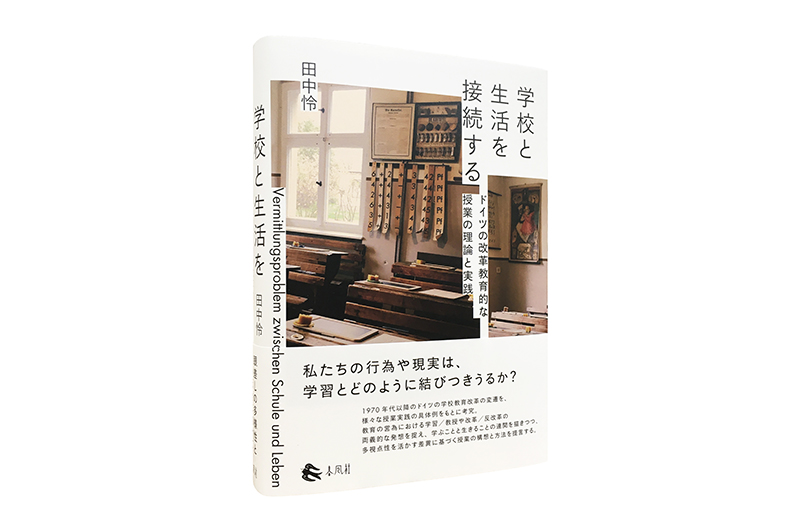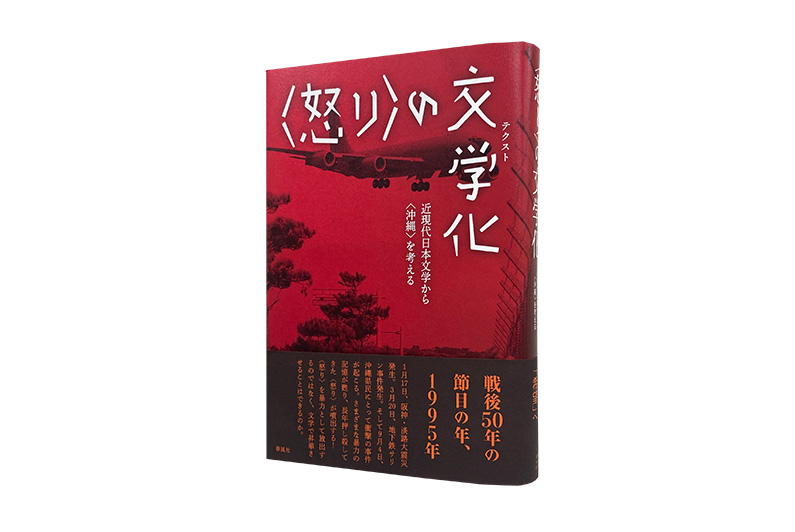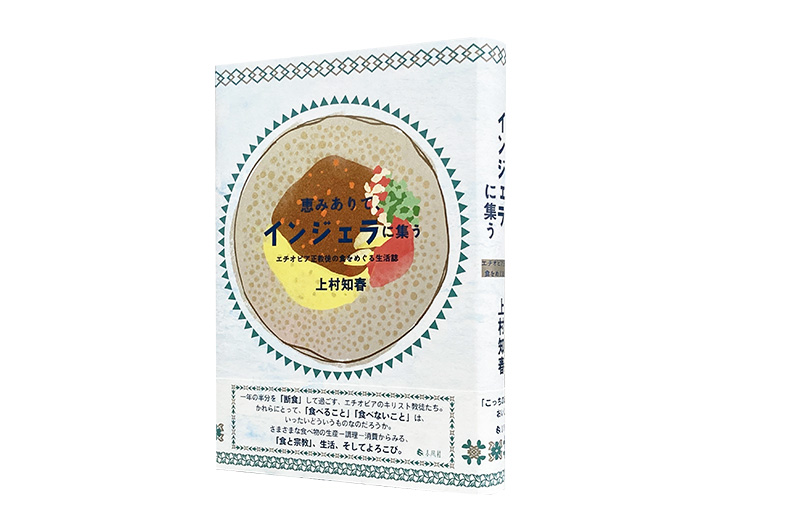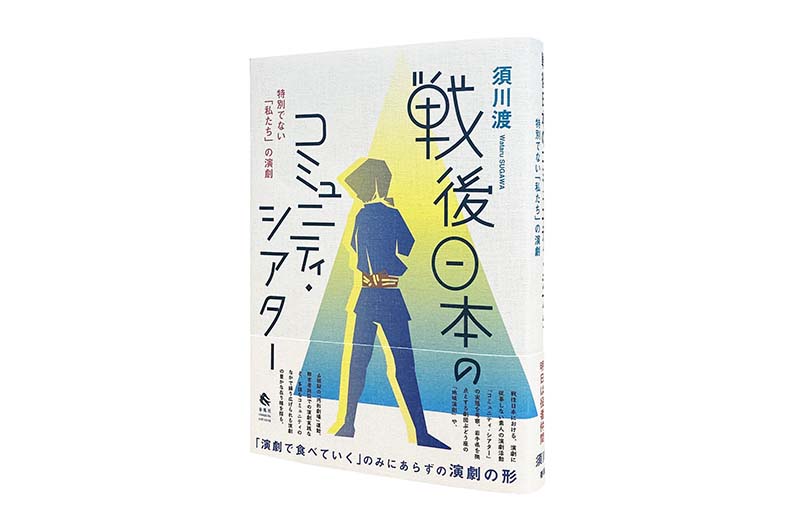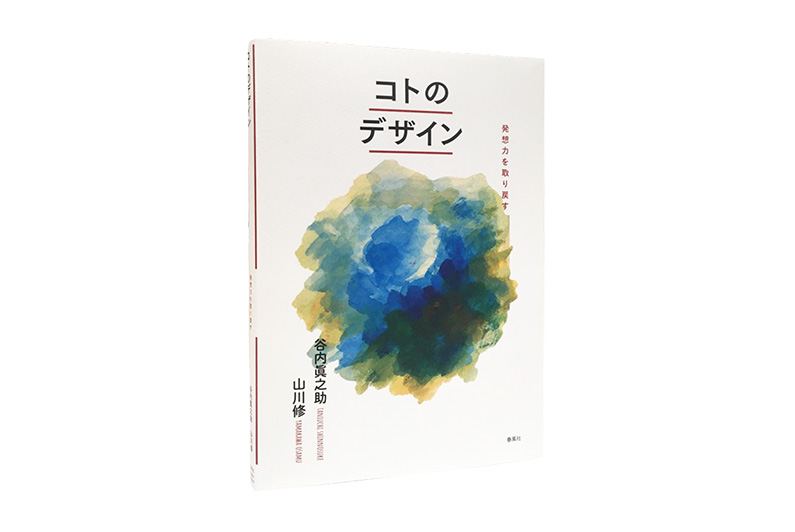日本教育方法学会編『教育方法学研究』第48巻/2023年3月に、田中怜著『学校と生活を接続する―ドイツの改革教育的な授業の理論と実践』の書評が掲載されました。評者は伊藤実歩子先生(立教大学)です。「ドイツの戦後教育学、とりわけ1960年代以降の教育学において、特に教育実践を含む教育方法学史を、系統的かつ包括的にまとめた」
『沖縄タイムス』2023年7月22日号に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は大城貞俊先生(作家)です。「さまざまな暴力によって奪われた「言葉」をどのようにして取り戻すか」
『琉球新報』2023年7月16日号に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は高良勉先生(詩人/批評家、沖縄大学客員教授)です。「〈一九九五年九月〉をキーワードに沖縄内の〈怒り〉の発露や戦時性暴力の記憶の継承について、一貫して論究している」
『図書新聞』第3600号(2023年7月22日号)に、半田幸子著『戦間期チェコのモード記者 ミレナ・イェセンスカーの仕事—〈個〉が衣装をつくる』の書評が掲載されました。評者は三輪智博先生(現代史研究者)です。「モード記者としての本来の仕事を明らかにし、分析を加えた本邦初の研究書だ。「ミレナ神話」を解体する神話崩しの書である。」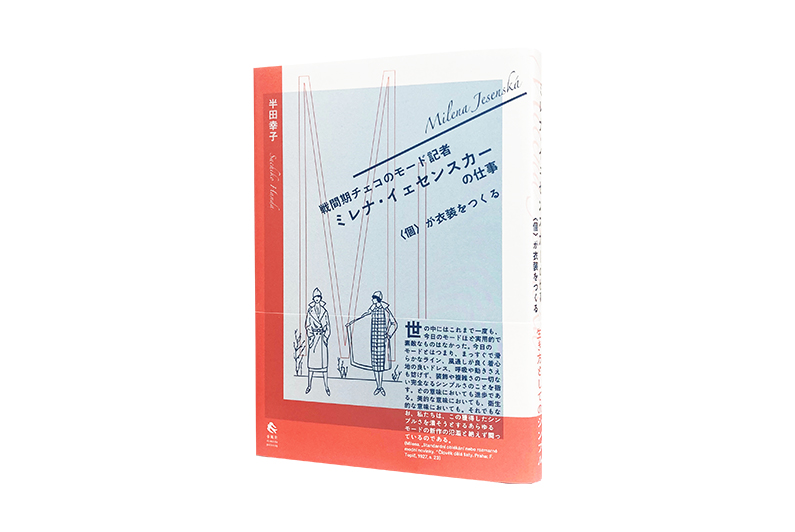
『図書新聞』第3600号(2023年7月22日号)に、上村知春著『恵みありて、インジェラに集う―エチオピア正教徒の食をめぐる生活誌』の書評が掲載されました。評者は藤本武先生(富山大学教授)です。「ユニークな信仰生活を送る人びとを調査対象に エチオピア北部の農村に暮らすアムハラの人びとの食生活と彼らのエチオピア正教徒としての宗教実践を丹念に記述した民族誌」
『図書新聞』2023年7月22日号に、高橋優著『ロマン主義的感性論の展開―ノヴァーリスとその時代、そしてその先へ』の書評が掲載されました。評者は武田利勝先生(早稲田大学)です。「「意識と感覚のロマン化」という壮大なプロジェクト ノヴァーリスを中核とした「ロマン主義的感性論」を克明に描き出す」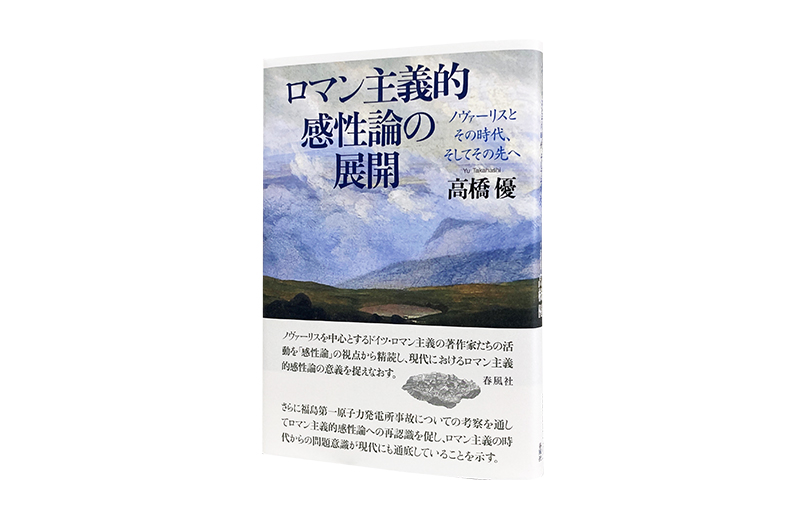
『演劇学論集』76号(2023)に、須川渡著『戦後日本のコミュニティ・シアター―特別でない「私たち」の演劇』が掲載されました。評者は五島朋子先生(鳥取大学)です。「演劇研究者や演劇実践者のみならず、地域や多様なコミュニティにおける文化の役割と意義に関心を持つ人々に幅広く手に取っていただきたい一冊」
書評全文は、J-STAGEの「演劇学論集 日本演劇学会紀要/76巻(2023)」本書書評頁よりお読みいただけます。
『日本教育新聞』2023年7月3日号に、谷内眞之助・山川修著『コトのデザインー発想力を取り戻す』が掲載されました。評者は都筑学先生(中央大学)です。「「コトのデザイン」には、自分自身の生き方をデザインすることも含まれる」
書評全文は、日本教育新聞ウェブサイトNIKKYO WEBよりお読みいただけます。