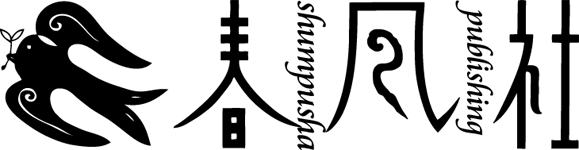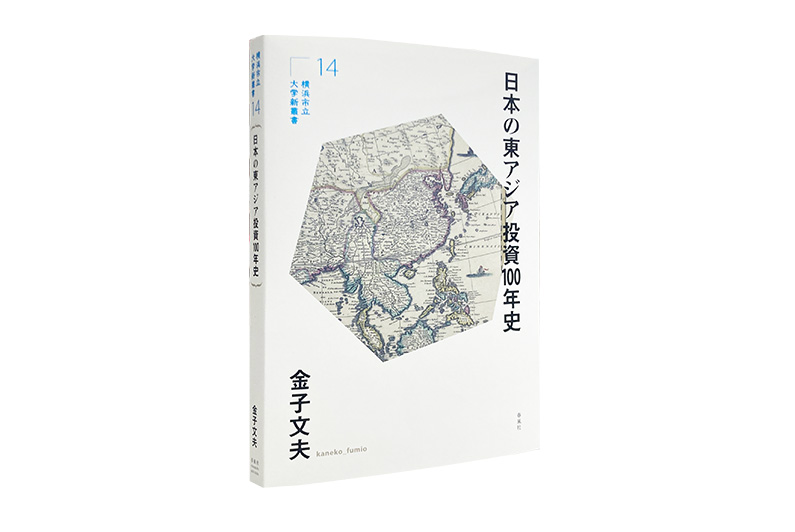『イギリス・ロマン派研究』No.46(イギリス・ロマン派学会/2022年3月)に、岡本由恵著『ジェイン・オースティンのグロテスクな笑い―困った人たち』の書評が掲載されました。評者は鈴木美津子先生(東北大学)です。「笑いを誘う人物の多様さ、複雑さ、豊かさ、面白さがあらためて浮き彫りに」
『イギリス・ロマン派研究』No.46(イギリス・ロマン派学会/2022年3月)に、木村正俊編『スコットランド文学の深層―場所・言語・想像力』の書評が掲載されました。評者は林智之先生(和歌山大学)です。「英国文学という表面の下のスコットランド独自の文学追求の問題」
『日本教育新聞』2022年4月18日号に、ヘレン・M・ガンター著/末松裕基・生澤繁樹・橋本憲幸訳『教育のリーダーシップとハンナ・アーレント』の書評が掲載されました。評者は元兼正浩先生(九州大学)です。「無思考(凡庸さ)を招き入れる危険性」
書評は下記URLよりご覧になれます。
◆日本教育新聞ウェブサイト https://www.kyoiku-press.com/post-243173/
※期間限定公開※
『記憶のなかの「碧南方言」』(石川文也 著)刊行を記念し、愛知県三河方言のひとつである「碧南方言」への理解度をはかる「『碧南方言』親近感診断テスト」(碧南言語歴史研究会)を公開中です。
『宗教研究』2021年95巻3号に、長岡慶(著)『病いと薬のコスモロジー―ヒマーラヤ東部タワンにおけるチベット医学、憑依、妖術の民族誌』の書評が掲載されました。評者は宮坂清先生(名古屋学院大学)です。「多彩かつ示唆に富む事例の数々に簡潔にして要を得た分析が加えられ、テンポよく展開し、読む者を飽きさせない。」
書評全文はこちらから読むことができます。

『アジア・アフリカ地域研究』第21-2号/2022年3月号に、長岡慶(著)『病いと薬のコスモロジー―ヒマーラヤ東部タワンにおけるチベット医学、憑依、妖術の民族誌』の書評が掲載されました。評者は鈴木正崇先生(慶應義塾大学 名誉教授)です。「本書で最も生彩を放つのは魅力的な対話である。ここの語り口が生き生きしていて小さな物語の連鎖として読める。〔…〕話者と筆者のかなりの信頼関係がなければこれだけのフィールドワークは出来ない」

『アジア・アフリカ地域研究』第21-2号/2022年3月号に、ボニー・ヒューレット(著)、服部志帆、大石高典、戸田美佳子(訳)『アフリカの森の女たち―文化・進化・発達の人類学』の書評が掲載されました。評者は田中文菜さん(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)です。「現地の人々と著者の関わり方がみえてくる丁寧なフィールドワークの記述は、スキルの伝達が難しいナラティブ・インタビューのひとつの手本として貴重だといえる」

『アフリカ研究』Vol.100 (2022)に、ボニー・ヒューレット(著)、服部志帆、大石高典、戸田美佳子(訳)『アフリカの森の女たち―文化・進化・発達の人類学』の書評が掲載されました。評者は今村薫先生(名古屋学院大学)です。「ヒューレット博士と、訳者たちの共同作業によって、熱帯雨林の世界が多面的に描かれることに成功したといえよう」

『「私らしさ」の民族誌―現代エジプトの女性、格差、欲望』(鳥山純子 著)の刊行にあわせて、本書の「はじめに」を公開します。

はじめに
本書は、3人のエジプト人女性と私、という4人の「こじらせ女子」の民族誌である。登場するのは優しい優等生でありながら口うるさいところのある20代未婚学校教員のシャイマ、大して仕事ができないのに美貌と依怙贔屓で生徒の人気者になろうとする、2人の子を持つ学校教員サラ、そして貫禄たっぷりに相手を威圧することに長けた60代のリハーム校長、そして私である。彼女たちは、2000年代初頭のカイロで国家、消費社会、さらには学問的枠組みにまで「私らしさ」を強制され、それぞれに夢見て、その実現に邁進していた。
2007年9月から2008年3月までの秋学期、私たちはみなエジプトのカイロ郊外にある、自称アメリカンスクールの私立学校(本書では以下A校と記す)で教員として働いていた。本書で扱う出来事のほとんどは、A校における日常生活の一部である。登場する女性たちは三者三様(四者四様?)に「私らしさ」をこじらせていた。私たち4人は他人からみれば、それなりに恵まれ、それなりに充実した日々を過ごしていた。しかしまた自分たちの生活に対してどこか割り切れないものを抱えていた。それは、あえて声高に語る必要のあるような重大な問題ではなかったし、意識的に無視することができないものでもなかった。それでも、一度考え始めると、いつまでも話し続けられるようなものだった。
本書の特徴は、自分の描く理想と現実とのずれに思い悩む、女性たちの「こじらせ」に着目することにある。彼女たちが自分らしさをこじらせていたのも無理はない。欧米中心主義的植民地構造の中でグローバル化が進行する00年代のカイロでは、格差の拡大、汚職、コネ至上主義がはびこっていた。その一方で、消費環境は豊かになり、誰もが消費主義的豊かさを求め、またそれが努力次第で手に入るような幻想を生きていた。人々は手に入れたいものと、実際に手に入れることができるものとの狭間に自分を見出すことを余儀なくされていた。本書では人々の欲望や希求を起点に、制約や限界と期待や希望の間で、なりたい自分になるべく日々生きる人々の独創性や柔軟性、そしてエネルギーに目を向ける。
私にとって本書で行うことは大きく二つに分けられる。まず一つ目は、2007年8月から2008年2月にかけて、同じ場と時間を過ごした女性たちについて整理し、彼女たちが提示した「私らしさ」に従って彼女たちについての理解を深めることである。「私らしさ」は「誰でもない唯一無二の私」に関わる表現ではあるが、社会的に作られたものでもある。それは自分を定義し、自己の尊厳を主張する拠り所であると同時に、自己を制約するものでもある。「私らしさ」に則してA校で働く彼女たちを描写し、彼女たちと共に時間を過ごした私の姿を振り返ることで、21世紀になって間もないカイロ近郊に生きた、3人の女性たちについて考えてみたい。
二つ目に試みたいのは、人々の包括的な生の描き方、すなわち民族誌の「書き方」に関わる取り組みである。実際のところを言えば、調査とはいえ当時は、突然成り行きで教員になることになり、私は日々の業務をこなすだけで精一杯だった。本書で描く3人の女性学校教員は、私にとっては同僚や上司であり、A校で児童・生徒やその保護者たちに対して共に戦う同志だった。彼女たちとは、日々共に働く中で、協力することもあれば、衝突することもあった。彼女たちの言動には、当時の私にとって不可解なものも数知れず、疑問に思ったものもあれば、その時は気にも留めなかったものもある。特に彼女たちの悩みには、私には取るに足らないと思えるものや、誤った認識に基づくように思えたものが多かった。彼女たちが何かを語る時には精一杯聞いているフリをしたが、今振り返ってみれば、自分がそれらにきちんと向き合えていたとは言い難い。日本に戻り、彼女たちの言動について議論を組み立てようとしたものの、驚くほど私には彼女たちのことが理解できていなかった。そうした理解不可能性を含みつつ、私が調査地で出会った人々を包括的に描くには、どのような方法があるのだろうか。
こうした問いを念頭に、本書では、当時理解できなかった言動を、今更無理に解釈しようとすることは止めることにした。わからなかったことはわからないなりに、自分の思い込みはそのままに、まずは文章として書き記してみることにした。当時彼女たちの話を十分に理解する努力ができなかった自分への反省もこめて、せめて彼女たちの言動を都合の良い枠組みでまとめることは避けたいと思う。
もしあの瞬間に時間を戻して、彼女たちの話を真摯に聞き、わからないことは粘り強く質問を重ね、一緒に悩むことができるなら、それに越したことはないかもしれない。ただ、それができない代わりに、今持てる私の精一杯の誠意として、彼女たちの多様な側面をできるかぎり描き出すことにする。正直なところ、今に至るまで私にはよくわからないことは多々あるが、それらをそぎ落とさずそのままに記すことで、私の理解の限界を示すと同時に、今後より優れた解釈が出てくることを期待したい。
(ウェブ公開に際して、一部表記を書籍から変更しています)